✅「従業員が作業中に機械で指を挟んで怪我をした」
✅「通勤途中に交通事故に遭い、従業員が入院することになった」
✅「長時間労働が原因で従業員が精神的な病気になってしまった」
このような労災が発生した際、経営者として「労災保険から給付があるから大丈夫だろう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、実際には会社側にも追加の負担が発生することがあり、「会社はどこまで補償すべきか?」「弁護士に相談すべきか?」といった疑問を抱くケースも少なくないでしょう。
労災保険からは給与の約6割しか支給されないため、会社の責任による労災の場合、残りの4割分を会社が負担する必要があります。
労働基準法では、業務上の災害で従業員が働けない期間中、平均賃金の6割以上の休業補償を会社が支払うことを義務付けており、労災保険給付との差額分が会社負担となります。
※通勤災害の場合は会社に責任がないため、この追加負担は発生しません。
本記事では、労災発生時の会社負担の仕組みや具体的な計算方法、支払い期間、税務上の取り扱いについて、詳しく解説していきます。
「弁護士に相談なんて大げさな・・・」という時代は終わりました!
経営者・個人事業主の方へ
労災が発生した場合の基本的なルールについて確認

まず、労災が発生した場合の基本的なルールについて確認しましょう。
会社の責任で従業員が怪我・病気になった場合は治るまでの給与の全額を支払う

会社と従業員の間の労働契約については、会社が従業員の業務が原因で怪我をしたり病気にならないように、安全に配慮しなければならないという義務があります(安全配慮義務:労働契約法5条)。
これに違反して従業員が怪我をしたり病気になってしまい、労務の提供ができなくなってしまった場合、民法536条2項によって会社が行うべき債務の履行、つまり給与の支払いをしなければならないことになります。
そのため、会社の責任で従業員が怪我をしたり病気になってしまった場合には、給与の全額を支払う義務があります。
労災保険から給与の6割が補償される
以上が労働契約上での権利義務関係になりますが、会社は従業員を雇用する際に労災保険に入る必要があり、労災が発生した場合には休業補償給付(通勤災害の場合には休業給付)を受けることができます。
なお、休業補償給付・休業給付は休業4日目から支給される点に注意が必要です。
労災の場合には休業補償給付を差し引いた支払いを行う
労災の場合に会社が従業員の給与の支払いをしなければならない
労災保険から休業補償給付を受けることができる
という点を考慮します。
その結果、給与から得る休業補償給付額として労災保険から労災に遭った従業員に対して支払われる金額になります。
そのため、最初の3日間の休業補償給付を受けられない部分については全額を会社が従業員に支払い、4日目以降には、通常給与の60%にあたる休業補償給付が受けられます。
この期間において残りの40%は、従業員に対して支給される基本的な原則となります。
休業特別支給金との関わり
なお、労災補償給付を受ける資格がある場合には、休業特別支給金として給与の2割の金額を受け取ることができます。
休業特別支給金は、労働者災害補償保険法29条の社会復帰促進等事業として受け取ることができるもので、給与の補填という休業保証給付とは目的を異にするものです。
これを受け取れる場合には、給与の8割が労災保険から補填されることになるのですが、休業特別支援金として受け取る金額については、会社から従業員に対して支払う金額で差し引きません。
つまり、会社は8割が払われるので2割のみ支払えば良い、のではなく休業特別支援金を受け取れる場合でも会社4割の支払いをしなければなりません。
これは、休業特別支援金は給与の補填ではなく、社会復帰という福祉目的で支払われるという性質の違いに基づきます。
会社が労災保険で支給されているものを差し引け無いケースもある
なお、会社が労災保険から支給される資金に対して、差し引くことができないケースもあるので確認しましょう。
労災保険の給付に関する労災保険法14条は、休業補償の給付において、「賃金未受給の日」に対する支給を行うことになっています。
そのため、従業員が上述した民法536条2項によって給与の請求をすることができるのであれば、休業補償給付の請求が不可能であると考えることができます。
この考え方に基づいて、会社がすべての負担を行い、従業員が休業補償給付で得た金銭については不当利得となるので労災保険に返すべき、という趣旨の次のような判例があります。
- 東京高等裁判所 平成23年2月23日判決
- 大阪高等裁判所 平成24年12月13日判決
- 長崎地方裁判所 平成30年12月7日判決
このような判決が下った事情として、例えば東京高等裁判所平成23年2月23日判決では、休業補償給付を受け取る前に従業員側から裁判を起こされた、という特殊な事情が影響したと見られています。
そのため、先に休業補償給付の支給がされている場合には、残った4割の給付でかまいません。
このことから、休業補償給付を速やかに受け取り、会社からの支給については残りの4割を支払うことに合意するなどして、労働災害となった場合にはなるべく訴訟にならないような注意が必要です。
労働基準法76条との関係で会社が6割の休業補償を行う際
労働基準法76条は、従業員が業務上怪我をした・病気なって療養が必要な場合に、療養期間中平均賃金の60/100(=6割)の休業補償の支払いを必要とする旨を規定しています。
この規定は、次の2つの例外に当てはまる場合でも、会社に負担をさせるための規定です。
- 労災が発生した原因が従業員の過失によるものであり会社の過失ではない
- 民法536条2項の規定の適用を就業規則などで排除している
これらの場合には、労働者は民法536条2項を理由として、会社に対して給与の請求をすることができません。
その場合でも、労働基準法76条の規定で6割の給付をすべきことになります。
この場合でも労災保険の休業補償給付は支払われるので、この場合には会社負担分は休業補償給付が行われてない最初の3日分のみとなります。
通勤災害の場合には会社の負担はない
労災保険は通勤中の災害にも給付されます。
通勤災害によって引き起こされた場合、会社での休業の際には、536条2項によって給与を支払うことにはならないので、会社の負担はありません。
この状況では、労災保険からの休業給付が提供されるだけです。
労災で会社負担分の計算方法
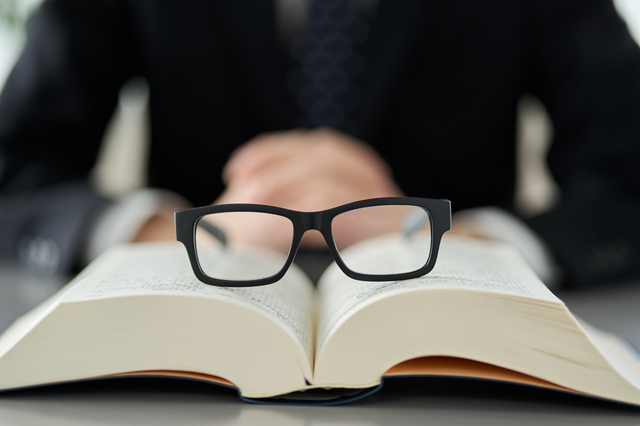
労災が起きた場合の、会社負担分の計算方法は次の通りです。
休業給付補償の計算方法
会社負担分は、給与から休業給付補償を差し引いた金額に対して行われます。
それゆえに、最初に休業給付補償の金額を算定します。
休業補償は、給付基礎日額に60%を乗じて計算されます。
この計算で発生する1円以下の端数が出た場合には切り捨てをすることになっています。
給付基礎日額の計算方法
給付基礎日額とは、通常は平均賃金に相当する金額となります。(労基法)
平均の賃金は原則として、事故が発生した日の前の3か月間に、該当する従業員への支払総額を、その期間の通算日数で除した、1日あたりの賃金額を指します。
この計算で発生する1円以下の端数については切り上げをすることになっています。
計算例
例えば、25万円の給与を得ている人が10月1日に怪我をした場合、7月8月9月の合計92日分で計算することになり、次のような計算式で求められます。
となります。
1円以下の端数については切り上げで計算することになっており、給付基礎日額は8,153円になります。
そのため、休業給付補償は
となり、ここでは1円未満は切り捨てのルール、1日あたり4,891円が休業給付補償となります。
従業員に負担をかけないように受任者払いを活用することも

従業員に負担をかけないように受任者払いの制度を活用することも検討しましょう。
休業給付補償については、申請をしてから1ヶ月以上かかることが通常であり、給付を受けるまでに時間がかかることになります。
その間は給与の支払日に会社から給与のうち4割の支払いを受けるにとどまり、従業員に負担をかけることになります。
そのため、会社が休業給付補償分も含めて支払ってしまい、休業給付補償分を後日会社から受け取ることができれば、従業員の負担を取り除くことができます。
会社負担分の支払いはいつまで行わなければならないか

会社負担分の支払いはいつまで行わなければならないのでしょうか。
会社負担分が発生するのは、民法536条2項をもとに、従業員の給与を補完するためです。
そのため、従業員の怪我・病気が治り、仕事ができる状況になったときには支払う必要がなくなります。
また、従業員が退職したときにも、労働契約が無くなるわけですから、支払う必要がなくなります。
怪我・病気が治って仕事ができる状況で、労災保険の給付の打ち切りがされたような場合には、会社が負担する支給も中止されることになります。
労災で会社負担分については原則所得税の課税対象となる

ここまでお伝えしているように、労災で会社負担分の支給については、給与として支払うべきものになります。
そのため、所得税の課税対象となり、源泉徴収が必要です。
労災が発生した場合は従業員のフォローが一番

労災が発生した場合には何より従業員のフォローを一番に行動するようにしましょう。
上述したように、裁判で民法536条2項を根拠として、差額だけではなく全額の支払いを命じられることになったようなケースは、もっとも避けるべき事態です。
3つの判例のうち東京高等裁判所のものは、休業給付補償についてうつ病になったことと会社の業務との因果関係について争っている間に、会社に対しても安全配慮義務違反・民法536条2項に基づいて裁判で請求をしてきたことによります。
この件で従業員のフォローをしっかり行い、休業給付補償の取得ができていれば、このような結果にならなかったとされています。
従業員のフォローを手厚く行い、どのような結果になる場合でもトラブルに発展しないようにつとめるべきであるといえるでしょう。
まとめ
このページでは、労災が発生した場合の従業員の休業補償についてお伝えしました。
労災保険から休業給付補償が支払われるのですが、会社の負担分については労災の内容によって異なることになります。
労災の認定をめぐってトラブルになるようなケースでは、従業員の適切なフォローが欠かせないので、弁護士に相談するなどして適切な処理に務めるようにしましょう。
あらかじめ弁護士保険などで、今後の様々なリスクに備えておくことをおすすめします。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










