
作業中のケガで従業員が長期休業…
過労による精神疾患で訴えられるかも…
労災事故が起きたら、どう対応すべきか分からない…
多くの企業担当者がこうした不安を抱えていることは珍しくありません。労災が発生した場合、企業はどのような責任を負い、どのような対応をすべきなのでしょうか?
労災事故は企業にとって損害賠償責任だけでなく、刑事罰や行政処分といった深刻なリスクをもたらします。
特に安全配慮義務違反や過労による健康被害が認められると、企業の責任が厳しく問われるケースが増加しています。
本記事では、近年の重要な労災判例を解説していき企業が取るべき対策について紹介します。
各事例から学ぶべき点を理解し、より安全な職場環境づくりを目指しましょう!
「弁護士に相談なんて大げさな・・・」という時代は終わりました!
経営者・個人事業主の方へ
判例から学ぶ労災の損害補償

労働災害に関する裁判例は、企業の安全配慮義務の範囲や損害賠償の基準を示す重要な指針となります。
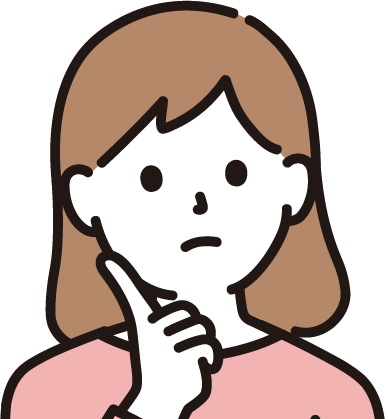
ニュースなどでも、労災に関する話題が上がったりしていますよね。
 弁護士
弁護士近年の判例では、企業の責任が厳しく問われる傾向にあり、適切な労務管理と安全対策の重要性が増しています。
過労自殺と企業の賠償責任(2008年)
2008年4月、大阪地裁は精密機器メーカーに対し、約1億9000万円の損害賠償支払いを命じました。
この事案では、製造管理部署に異動した従業員が、わずか2週間後に脳出血で倒れ、寝たきり状態になったことが問題となりました。
裁判所は、12日間で約61時間の時間外労働があったことを指摘し、「業務は質的・量的にも著しく過重だった」と病気と過労の因果関係を認めました。
この判例から、企業は以下の点に注意する必要があるでしょう。
- 異動直後の従業員への配慮
- 短期間であっても、集中的な長時間労働の回避
- 業務の質と量の適切な管理
 弁護士
弁護士過重労働による従業員の健康被害を防ぐには、労働時間の適切な管理はもちろん、業務内容や負荷の質的な面にも注意を払う必要があります。
作業環境の安全配慮義務違反(2004年)
2004年2月、和歌山地裁は運送会社に対し、約6886万円の損害賠償を命じました。
この事例では、海産物運送を行う会社の傭車運転手(運送業者から委託された輸送業務を行う人のこと)が、過重労働により高血圧性脳内出血及び脳梗塞を発症し、重度の後遺障害を負った事案です。
裁判所は「企業には傭車運転手の労働状態を把握し、健康管理を行う安全配慮義務があった」と判決を下しました。
ここで重要なのは、正社員ではない傭車運転手に対しても、企業の従業員と同様の配慮が必要だと判断された点です。
この判例から、企業は雇用形態に関わらず指揮命令下にある労働者への安全配慮義務を果たす必要があることを読み取ることができます。
 弁護士
弁護士運送業特有の労働環境に対する配慮や、長時間労働・不規則な勤務による健康リスクについて適切に管理・対応することも大切です。
派遣労働者の過労死と派遣元の責任(2022年)
2022年4月、横浜地裁は派遣元企業に対し、派遣先で心筋梗塞を発症して死亡した労働者の遺族への損害賠償を命じました。
この事例では、派遣労働者が発症前3ヶ月間に月平均150時間を超える時間外労働を行っており、特に過重な業務であったと横浜地裁は判断しました。
裁判所は、派遣元企業にも労働者の健康管理責任があるとし、以下の点を指摘しました。
- 派遣先での労働時間や業務内容の把握義務
- 過重労働を防ぐための適切な措置を講じる義務
- 派遣労働者の健康状態に配慮する責任
 弁護士
弁護士また、この判例では、派遣労働における「二重の使用者責任」を明確にしました。
精神障害の業務起因性(2024年)
2017年4月、うつ病を発症して従業員が自殺した事案で、遺族が新宿労働基準監督署の労災不認定の判断を取り消すよう求めた裁判が行われました。
東京地裁は2024年2月28日、遺族の請求を棄却しています。
男性は2015年に入社し、総務課で働いていましたが、業務の増加に伴い2017年4月にうつ病と診断され、9月に自殺。
遺族は労災を申請しましたが不認定となり、その後裁判を起こしていました。
裁判所は、男性のうつ病発症前の時間外労働が74時間であったと認定。
しかし、労働環境を総合的にふまえ、心理的負荷が「強い」とは認められないと判断しました。
- 遺族の主張する、長時間労働の事実がありながら請求を棄却されたこと
- 心理的負荷と自殺との因果関係が認められなかったこと
この2点がポイントとなり、精神疾患の労災認定の複雑さが浮き彫りになる判例となりました。
歓送迎会後の事故と業務関連性(2016年)
2016年7月、最高裁は会社の歓送迎会後の送迎中の事故死を、業務上の災害と認める判決を下しました。
これは、会社の指示で留学生の歓送迎会に参加し、その後の送迎中に交通事故で死亡した従業員の遺族が労災認定を求めたものです。
一審と二審では労災が否定されましたが、最高裁は、死亡した従業員が上司の意向で参加せざるを得ない状況にあり、事故が業務の一環であると判断しました。
この判決のポイントは、
- 歓送迎会が会社の事業活動に密接に関連していた
- 従業員が業務の都合で歓送迎会に参加せざるを得なかった
- 事故が業務再開のための移動中に発生した
という3点にあります。
 弁護士
弁護士この判例は、業務の範囲に関する解釈を拡大したものとして注目されました。
マイカー通勤中の事故と企業責任(2010年)
2010年5月、神戸地裁はマイカー通勤中の事故について企業の管理責任を認める判決を下しました。
この判決では、企業はマイカー通勤者に対して以下の義務があるとされました。
- 日常的な安全運転指導
- 十分な保険契約の締結状況の確認と指導
また、事故に備えるための車の点検においても、留意する必要があると判断されました。
 弁護士
弁護士この判例は、通勤手段に関する企業の責任範囲を拡大したものとして注目されました。
過労による適応障害と素因減額(2018年)
2018年12月、福岡地裁は過労により適応障害を発症して自殺に至った労働者の遺族からの損害賠償請求において、35%の素因減額を認めました。
裁判所は、
- 精神疾患があったことを、労働者が企業側に知らせなかった
- 労働者がサポート要員を断った
- 遺書に記載されていたとおり、業務ミスが自殺の要因になっており、過失相殺が認められた
という3点から、企業の責任を一部軽減する判決を下しました。
 弁護士
弁護士この判例は、労働者の個人的要因と企業の責任のバランスを示す事例となりました。
産婦人科医師の過労自殺と業務起因性(2019年)
2019年5月、広島地裁は産婦人科医師の自殺について業務起因性を認め、労災認定を否定した労基署の判断を取り消しました。
自殺した原因は、過重労働によるうつ病だとして、医師の妻が労災認定を求めた裁判です。
広島地裁は、長時間労働や連続勤務の実態を重視し、医師の過重労働が自殺の原因になったと判断し、国側は控訴することなく判決が確定しました。
 弁護士
弁護士この判例は、医療従事者の労働環境改善の必要性を示しているといえるでしょう。
建設現場での転落事故と安全対策(2020年)
2020年9月、東京地裁は建設現場での転落事故について、元請け会社と下請け会社の双方に賠償責任があるとする判決を下しました。
事故の原因として、労働者が命綱をつけていなかったことと、養生網に隙間があったことがあげられています。
遺族は元請け会社と下請け会社に対し、安全配慮義務違反および不法行為に基づき損害賠償を求めましたが、労働者の過失が5割とされ過失相殺が行われました。
この判決について裁判所は、安全設備の不備や作業手順の不適切さを指摘し、重層的な責任体制の必要性を強調しています。
 弁護士
弁護士この判例は、建設業界における安全管理の重要性と責任の所在を明確にしました。
労災における賠償額の相場と法的根拠


近年になって、労災に関する裁判はたくさん行われているのですね。
 弁護士
弁護士労災における損害賠償請求額は様々ですが、ある程度の相場はあります。
また、企業が責任を求められる根拠についても解説します。
労災の損害賠償額の相場
労災の損害賠償額は、被害の程度や状況によって大きく異なります。
近年の判例を見ると、高額な賠償金を命じられるケースが増えています。
例えば、2008年の過労自殺事件では、大阪地裁が精密機器メーカーに約1億9000万円の賠償を命じました。
また、2004年の運送業における過重労働事案では、和歌山地裁が企業側に約6886万円の賠償を命じています。
後遺障害が残った場合の慰謝料については、交通事故の基準が参考になります。
等級に応じて増減し、第1級の場合は2800万円、第14級では110万円程度が目安です。
ただし、これらの金額は慰謝料のみであり、実際の賠償額はこれに休業損害や逸失利益などを加えたものになります。
重要なのは、労災保険給付では補償されない部分があることです。
例えば、慰謝料や休業開始後4日目以降は給与の4割を企業が負担する「休業損害の4割部分」は労災保険でカバーされません。
そのため、企業に別途請求がなされる可能性もあります。
労災の損害賠償額は数千万円から1億円を超える場合もあり、企業にとって大きなリスクとなっています。
適切な労務管理と安全対策が、結果的として高額賠償リスクの回避につながるといえるでしょう。
労災で企業側に責任が認められる法的根拠
労災事故における、企業側の責任が認められる主な理由は、以下のとおりです。
- 安全配慮義務
労働契約法第5条に基づき、使用者は労働者の安全に配慮する義務があります。 - 使用者責任
民法第715条に基づき、従業員が業務中に起こした事故については、使用者である企業も責任を負うことがあります。 - 労働安全衛生法上の責任
職場の安全衛生に関する法的義務を怠った場合、企業に責任が発生します。 - 過重労働の防止責任
心身ともに大きな負担がかかる過重労働は、企業側で防止する責任があります。 - パワーハラスメント防止責任
労働契約法第5条に基づき、企業は労働者が快適な就労ができる義務を負います。
そのため、パワーハラスメントの発生防止にも努めなければなりません。 - 複数就業者への配慮
2020年の労働者災害補償保険法改正により、副業・兼業者の労災についても、使用者の責任が明確化されました。
ただし、因果関係が立証できない場合や、労働者側の重大な過失がある場合は、企業の責任が軽減されたり、免責されたりすることもあります。
企業は適切な安全対策と労務管理を行うことで、労災リスクや責任の軽減につながります。
労災に関する法改正

 弁護士
弁護士多様な働き方や、パンデミック時における労働者の保護等、様々な場面で労働者を守るための法改正が行われています。
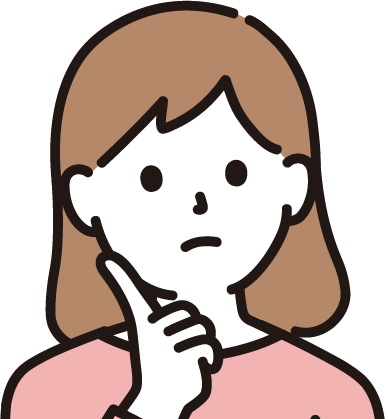
特に、ここ数年では細かい法改正が行われている印象があります。
複数就業者の労災認定基準の変更(2020年)
2020年9月、労働保険法が改正され、複数の職場で働く労働者の労災認定基準が変更されました。
新たに「複数業務要因災害」という類型が設けられ、複数の就業先での業務上の負荷を総合的に評価して労災認定を行うことになりました。
主な改正内容は、以下のとおりです。
- 休業した際の給付金が、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等が決定されることになった。
- それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断するようになった。
この法改正は、多様な働き方に対応した労災保護制度の拡充を示しています。
新型コロナウイルス感染症の業務上認定(2021年)
2021年、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に関する労災認定基準を示しました。
医療従事者や介護従事者については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災と認定するとしました。
また、新型コロナウイルスの症状が続き、療養や休業が必要と認められる場合でも労災の対象となります。
この基準は、パンデミック下における労働者保護の新たな指針となりました。
テレワーク中の事故と労災認定(2022年)
2022年、在宅勤務中に発生した事故について労災認定を行った事例が報告されました。
この事例では、テレワーク中の移動や休憩時の事故についても、一定の条件下で業務上の災害と認められることが示されました。
具体的に、労災と認められる可能性が高いのは、以下のようなケースです。
- テレワーク中にシュレッダーで指を切った
- 会社へ資料を取りに行く際に怪我をした
- パソコン作業中に立ち上がった時に転倒してしまった
この事例は、新しい働き方に対応した労災認定の考え方を示すものとして注目されています。
まとめ
労災の損害賠償は会社にとって、できるだけ避けたいものです。
過労死や重大な労災事故では、1億円を超える賠償命令も出ており、賠償額の高額化が顕著になっています。
また、企業の安全配慮義務は従来よりも広く解釈される傾向にあります。
歓送迎会後の事故など、従来のグレーゾーンにも及ぶ可能性があるため、注意が必要です。
正社員だけでなく、副業・兼業を行う従業員の労働時間管理や健康管理にも注意が必要です。
特に、うつ病などの精神疾患による労災の認定基準が明確化され、企業のメンタルヘルス対策は欠かせないものとなりました。
他にも、新型コロナウイルス感染症やテレワーク中の事故など、新しい形態の労災リスクにも企業は対応を迫られています。
企業は、これらの動向を踏まえ、より綿密な労務管理と安全対策を講じる必要があります。
同時に、労災が発生した際の適切な対応や、必要に応じた損害賠償の準備も欠かせません。
労働者の安全と健康を守ることは、結果的に企業自身を守ることにつながります。

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。
※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










