「AIで作った画像をSNSに投稿したら著作権侵害と言われた」
「会社でChatGPTを使っているが法的に問題ないか不安」
「AIイラストを商用利用したいが、どこまでが安全なのかわからない」
このように、生成AI活用における著作権問題で悩まれている個人や企業は少なくありません。
結論から言うと、AIと著作権の関係は各段階で大きく異なり、それぞれ適用される法的な基準が違います。
本記事では、AIと著作権の基本原則からリスクを回避する方法、よくある疑問への回答まで、文化庁のガイドラインや最新の法的動向を踏まえて詳しく解説していきます。
「弁護士に相談なんて大げさな・・・」という時代は終わりました!
経営者・個人事業主の方へ
AIと著作権の基本

生成AIの普及によって、創作活動における著作権の境界線が改めて注目されています。

よく話題に上がるのは目にしますが、具体的にどのようなことに気を付けた方がいいでしょうか?
 弁護士
弁護士著作権法の基本的な原則を理解し、AIを活用した創作活動でのトラブルを未然に防ぐことが重要です。
著作権法が保護するのは「創作的表現」のみ
著作権法第2条第1項第1号では、著作物について以下のように定義しています。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
この定義からわかる通り、著作権が保護するのは具体的な表現のみです。
単なる事実の記載やありふれた表現、発想段階のものは保護対象外です。
たとえば「カエルを擬人化してイラスト化する」という発想そのものは、著作権で保護されません。
しかし、実際に描かれたカエルのキャラクターの表現は保護されます。
この「アイディア」と「表現」の区別は、AI生成物の著作権を考える上での判断基準となります。
作風・画風そのものは著作権の対象外
「ジブリ風」や「ディズニー風」といった作風や画風は、著作権法の保護対象にはなりません。
これは国際的にも確立された原則で、抽象的なスタイルを特定の創作者が独占してしまうと、他の創作者の自由が過度に制限されてしまうためです。
文化庁の審議会でも、この点について明確な見解が示されました。
ただし、具体的なキャラクターや、特徴的な表現要素が含まれる場合は別です。
たとえば「トトロ」や「ミッキーマウス」といった具体的なキャラクターが生成された場合は、著作権侵害のリスクが生じます。
AIを使用する際は、この「スタイル」と「具体的表現」の違いを明確に理解しておかなければなりません。
著作権侵害の判断基準は「類似性」と「依拠性」
著作権侵害が成立するには、既存の著作物との「類似性」と「依拠性」の両方が認められる必要があります。
つまり、単に似ているだけでなく、創作的表現の核心部分が共通していることが要件となります。
偶然の一致で生じた類似では、著作権侵害が成立しません。
AI生成物の場合、利用者が元の作品を知らなくても、類似したものが出力されるかもしれず、この場合の依拠性の判断が新たな法的争点となっています。
「表現」と「アイディア」の境界線
たとえば、「恋愛小説を書く」というアイディアは誰でも自由に使えますが、特定の恋愛小説の具体的なセリフや場面描写をコピーすれば、著作権侵害に該当します。
音楽分野では、同じコード進行を使うことは自由ですが、メロディーや歌詞が類似していれば侵害のリスクが生じます。
イラストについても、「猫のキャラクター」という発想そのものは保護されません。
しかし、特定の猫キャラクターの特徴的な表現(色彩、形状、装飾など)を真似すれば問題となります。
このように、抽象的なアイディアから具体的な表現へと進むにつれて、著作権の保護範囲が強くなっていくのです。
なぜAIと著作権が問題になるのか
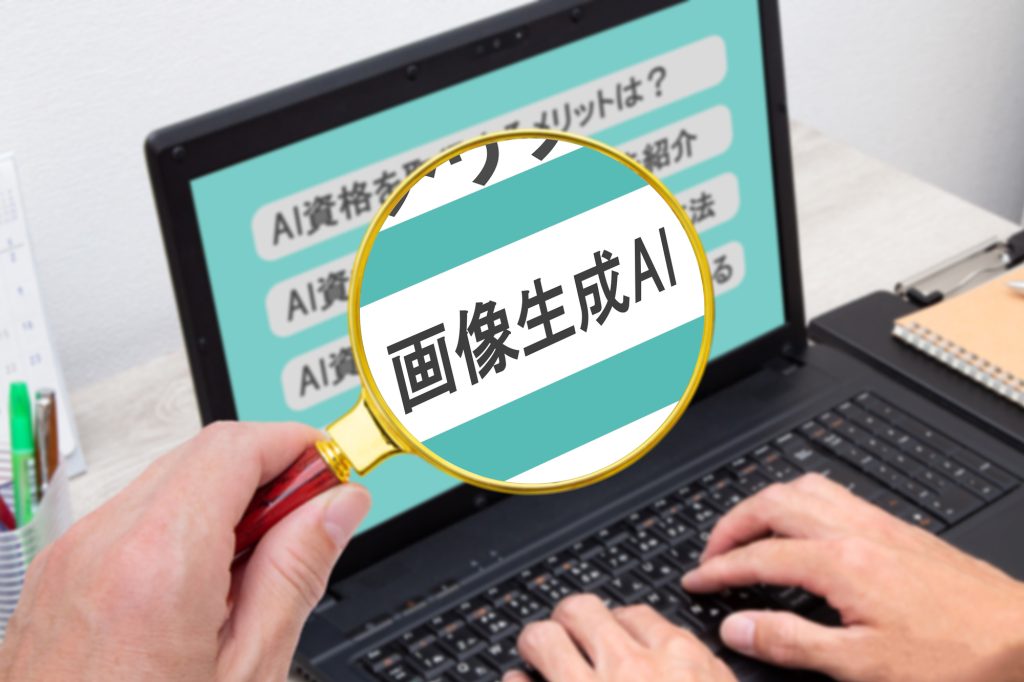
AIは大量のデータを学習して新たなコンテンツを生成する特性があります。
その仕組みが既存の著作権制度との間で様々な摩擦を引き起こしています。

学習段階でも違法性があるということでしょうか?
 弁護士
弁護士直ちに違法とは言えませんが、十分に注意が必要です。
著作物を学習データに使う場合は原則OKだが制限あり
日本では、著作権法第30条の4により、情報解析目的での著作物利用が原則として認められています。
この規定は2018年の法改正において導入されたもので、AI学習も情報解析に含まれると解釈されています。
ただし、無制限に利用できるわけではありません。
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は例外とされ、情報解析用に販売されているデータベースを無断で利用することはNGです。
また、文化庁のガイドラインでは、海賊版サイトからの学習データ収集は慎むべきとしています。
さらに、学習を拒否する技術的措置(robots.txtなど)が講じられている場合に、これを回避してデータを収集することも問題となる可能性があります。
既存作品との「類似性・依拠性」で侵害になることも
前述のとおり、AI生成物による著作権侵害は、従来と同じ「類似性」と「依拠性」の基準で判断されます。
特に注目すべきは依拠性の判断方法です。
利用者が認識していなくても、学習データに既存作品が含まれていた場合は依拠性が推認される可能性があります。
たとえば、特定の作品のみを学習させたAIを使用した場合、“その作品の創作的表現を模倣する目的があった”と評価される恐れがあります。
ただし、学習した表現がそのまま出力されないよう、技術的に制御されている場合は、その限りではありません。
「享受目的の併存」が学習段階でのNGライン
学習段階で問題となるのが「享受目的の併存」です。
これは、著作物を鑑賞・享受する目的が同時に存在する場合、著作権法第30条の4の適用が除外されます。
具体的には、既存著作物の類似物を生成させることを目的とした学習や、特定の作品のみのデータを学習する行為が、これに該当します。
また、RAG(検索拡張生成)において、既存著作物の類似物を生成させる目的でデータ収集を行う場合も同様に制限されます。
これらの行為はいずれも、単なる情報解析を超えて、元の著作物の表現を享受する意図があると評価されるためです。
海外との法制度の違い
AIと著作権は国際的な問題も絡むため、各国の法制度の違いが複雑さを増しています。
アメリカではフェアユース原則に基づき、柔軟な判断が可能ですが、EUでは適法アクセス要件やオプトアウト制度が設けられ、より厳格な枠組みが採用されています。
日本の情報解析規定は世界の中でも早い段階で導入されたものの、海賊版利用に関する明文規定がないなど、他国より緩やかな面もあると指摘されています。
国際的なサービス展開では、どの国の法律が適用されるかが争点となります。
学習を行う国、サービス提供国、利用者の所在地によって適用法が変わる可能性があります。
この法の不確実性が、AI開発者や利用者にとって、大きなリスクとなっています。
プラットフォーム事業者の責任範囲
著作権を侵害した物が高い頻度で生成されたり、類似物が生成される可能性が高いと認識しながら抑止措置を講じなかったりした場合、AI事業者の責任が問われることもあります。
逆に、侵害防止措置を講じている事業者は、責任を負わなければならない可能性は低いでしょう。
近年、大手プラットフォームでは、特定のキャラクター名や作品名に対するプロンプトフィルタリング機能を導入するなど、技術的な対策が進んでいます。
AIと著作権の2つの段階

AI生成においては、段階ごとで適用される法的基準は異なります。
そのため、各段階に合わせた適切な対策が必要です。

どのような対策をすべきでしょうか?
 弁護士
弁護士特に販売等の公開するタイミングにおいて細心の注意を払う必要があります。
開発・学習段階は「享受目的でなければ許諾不要」
AI開発・学習段階では、著作権法により、原則として著作権者の許諾なしに著作物を利用できます。
この規定のポイントは「享受目的」の有無です。
たとえば文章であれば読むこと、音楽であれば聴くこと、画像であれば見ることが該当します。
AI学習は通常、パターン認識や統計的分析のために行われるため、享受目的には当たりません。
ただし、営利・非営利を問わず適用される一方で、享受の本意があれば、対象外となります。
公開・販売する利用段階は著作権侵害リスクが高い
生成・利用段階では、情報解析規定は適用されず、通常の著作権侵害の基準で判断されます。
個人的な利用であれば私的複製として認められる場合もありますが、SNS投稿や商用利用では著作権侵害のリスクが高くなります。
文化庁の審議会では、たとえAI利用者が既存著作物を認識していない場合でも、学習データに含まれていれば依拠性が推認されるとされています。
これは、従来の著作権侵害とは異なる特殊な判断基準です。
万が一、利用者が著作権侵害と知らなかった場合でも不当利得返還請求の対象となる可能性があり、金銭的なリスクも伴います。
そのため、AI生成物を公開・販売する前には、既存作品との類似性を慎重に確認する必要があります。
権利制限規定の適用範囲
開発・学習段階でも、権利制限の規定が適用されないのは「著作権者の利益を不当に害する場合」です。
具体的には情報解析用に販売されているデータベースの無断利用や、近い将来販売予定と推認される場合が該当します。
具体的な推認要素は、robots.txtによる技術的措置やID・パスワード認証の設定、過去の販売実績などです。
また、海賊版サイトからの学習データ収集は、法的には必ずしも違法とは明記されていないものの、文化庁ガイドラインでは慎むべき行為としています。
このような制限は、権利者の正当な利益を保護するために、必要な歯止めとなっています。
Image to Image入力の著作権処理
生成AIへの入力段階でも、著作権問題が生じる可能性もあります。
たとえば、「Image to Image」で既存の著作物を入力する場合は、原則として著作権者の許可が必要です。
ただし、生成物作成を目的として情報を解析する行為で、著作権法が適用される場合もあります。
もともと類似物を生成するつもりの場合は、享受目的が併存するとして権利制限規定の適用が除外されます。
したがって、既存キャラクターのイラストをAIに入力して、類似した画像を作る場合、入力段階で既に著作権侵害のリスクを含むことになります。
技術的措置による侵害防止
利用段階での著作権侵害を防ぐため、様々な措置がなされています。
たとえば、「プロンプトフィルタリング」では、特定のキャラクター名や作品名が入力された際に、生成を拒否する仕組みが実装されています。
出力段階でのフィルタリングは、学習データに含まれる著作物との類似度をチェックし、一定の値を超えた場合に出力をブロックする仕組みです。
これらの措置は法的義務ではありません。
しかし、事業者の責任軽減や利用者を保護するうえで、重要な取り組みと言えます。
特に商用サービスでは、こうした技術的な配慮の有無によって、事業者責任を判断される可能性があります。
AI生成物は著作物になるのか?

AI生成物の著作権に関する問題は、現代の知的財産法においてもっとも複雑な論点の一つです。
 弁護士
弁護士人間とAIの関与度合いによって著作権の有無が決まるため、個別具体的な判断が必要となります。

具体的にはどのような判断になるのでしょうか?
AIは著作者にはならない
AIは、法的人格を持たないため、著作者になることはできません。
著作権法第2条第1項第2号では著作者を「著作物を創作する者」と定義していますが、AIは「者」に当たらないためです。
完全にランダムな生成や、「生成」ボタンを押すだけで作成したAI画像や、単語を一つ入力しただけで出力された文章などは、著作物性が否定される可能性が高いとされています。
この判断基準は国際的にも共通しており、アメリカの著作権局でも人間の実質的な創作的寄与がない場合は、著作権登録を拒否するという方針を示しています。
著作権が認められるケース
人間が思想・感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用した場合、その利用者が著作者となる可能性があります。
重要となる判断要素は「創作意図」と「創作的寄与」の両方が認められるかどうかです。
創作意図は、AIを使用して自らの個性を反映させた表現を作る意図があれば足りるとされ、それほど厳格な要件ではありません。
一方、創作的寄与は、個々に応じて総合的に判断されるものです。
文化庁での整理によれば、具体的で詳細な指示・入力、生成物を確認しながらの試行を繰り返すことなどが、考慮される要素としています。
ただし、これらの要素が積み重なることで著作物性が認められる余地があり、単一の行為だけで認められる可能性は低いと考えられています。
プロンプトの分量・内容による判断
AI生成物の著作物性判断で最も注目されるのが、プロンプト(指示・入力)の内容です。
創作的表現について具体的かつ詳細な指示がなされている場合は、著作物性が認められる可能性が高くなります。
しかし、長大な指示でも、構想を示すだけであれば、著作物性の判断には影響しません。
たとえば、画像生成において色彩、構図、雰囲気、キャラクターの表情や動作を詳細に指定した場合は、創作的寄与が認められやすくなります。
しかし、単に「美しい風景」「かっこいいキャラクター」といった抽象的な指示では不十分です。
この判断は従来の写真著作物の考え方とも関連しており、撮影者の意図や技術的工夫が反映されているかが主な基準となります。
AI生成の試行回数と選択行為
AI生成における試行回数や選択行為も、著作物性を判断するうえでの重要な要素となります。
ただし、試行を重ねた回数や、生成物の中から選んだ回数そのものだけでは著作物性は認められません。
重要なのは、生成物を確認した上で指示・入力を修正しつつ、試行を繰り返しているかどうかです。
選択行為についても同様で、単に複数の生成物から気に入ったものを選ぶ行為のみでは、創作的寄与とは認められません。
しかし、創作行為の一環として必要な選択である場合は、考慮される可能性があります。
これは、従来の編集著作物や映画著作物における選択・配列の創作性と類似した考え方です。
人による加筆・修正
AIが生成したものに創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められるとされています。
ただし、人の手によって加筆・修正された部分のみが著作物となります。
したがって、どの部分が人間による創作的表現で、どの部分がAI生成なのかを区別することが重要です。
特に商用利用や権利主張を行う場合は、人間による創作的寄与の範囲を明確に記録しておくことが不可欠です。
著作物性の国際比較
AI生成物の著作物性に関する判断は、国によって異なる傾向があります。
たとえば、中国では比較的AI生成物の著作権を認める判例が出ている一方、アメリカでは著作権局が「人間の具体的なコントロール」を重視する姿勢を示しています。
日本では判例がまだ少ないため、明確な基準は確立されていません。
しかし、文化庁の整理によれば「創作的寄与の積み重ね」を重視する方向性が示されています。
国際的なコンテンツ流通を考える場合、各国の判断基準の違いが権利行使の可否や範囲に影響を与える可能性があります。
そのため、もっとも厳格な基準に合わせた対応が安全策と言えるでしょう。
著作権侵害を避けるには

AI活用における著作権リスクを最小限に抑えるには、開発段階から利用段階まで各段階での適切な対策が欠かせません。
事前の確認作業を怠ると、意図しない侵害によって法的責任を問われる可能性があります。

どのようなことに気を付けたらいいでしょうか?
 弁護士
弁護士学習前・公開前など、要所要所でチェック項目を設けることが大事です。
学習用データの収集は「著作権者の利益を害さないか」
AI学習用データの収集における重要な判断基準は「著作権者の利益を不当に害するかどうか」です。
たとえば、情報解析用に販売されているデータベースを無断利用する場合や、近い将来販売予定と推認されるデータを使用した場合は、権利制限規定の適用が除外されます。
なお、海賊版サイトから学習データを収集する行為は、開発されたAIが著作権侵害を引き起こした場合に、AI開発者の責任を重くする要因となります。
収集前には、データの出所やアクセス制限の有無、権利者の意思表示を十分に調査することが重要です。
また、学習データの出所や学習過程についての記録を保存しておき、あとで確認・検証できるようにしておきましょう。
公開・販売前に「類似性・依拠性」の確認
AI生成物を公開・販売する前に、既存作品との「類似性」「依拠性」について確認することが重要です。
まず、画像検索やインターネット検索を用いて、生成物と類似する既存作品が存在しないかを調査します。
類似性の判断基準は「既存著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できるかどうか」です。
したがって、単に似ているだけでなく、創作的表現の核心部分に共通性があるかどうかを検討すべきです。
依拠性については、利用者が既存作品を認識していた場合は明確に認められますが、認識していなくても学習データに含まれていれば推認されることがあります。
特に注意が必要なのは、特定のプロンプトに対して同様の生成物が頻発する場合です。
これは、学習データに特定の作品が含まれている可能性を示しています。
権利者への事前許諾取得
類似性・依拠性が疑われる場合は、既存作品の権利者から事前に許諾を得ることを検討すべきです。
特に商用利用の場合は、後からトラブルとなるリスクを避けるため、確実に権利処理を行っておきましょう。
許諾取得の際は、利用目的、利用範囲、利用期間を明確に示し、適切な使用料を支払うことが重要です。
また、AI生成物の性質上、元の作品との関係を正確に説明し、権利者の理解を得ることも必要です。
許諾が得られない場合は、該当する生成物の利用を控えるか、既存作品とは全く異なる内容となるよう大幅に修正します。
社内ガイドライン策定と従業員教育
企業でAIを活用する場合は、社内ガイドラインの策定と従業員への教育が欠かせません。
ガイドラインでは、以下の内容を明確に定めることが重要です。
- 利用可能なAIサービスの種類
- 禁止事項
- 確認手順
- 責任体制
特に、機密情報の漏洩リスクや著作権侵害のリスクについての具体的な注意事項を示し、違反した場合の対応も明記しておくべきです。
従業員教育では、著作権の基本概念、AI生成物のリスク、実際の確認手順を実例とともに説明することが効果的です。
また、定期的な研修やアップデートを行うことで、最新の法的動向や技術的な変化にも対応できるようになります。
技術的措置による予防策
AI開発者や提供者は、著作権侵害を防ぐための技術的措置を導入すべきです。
たとえば、プロンプトフィルタリングでは、特定のキャラクター名や作品名が入力された際に生成を拒否する仕組みを実装します。
出力フィルタリングでは、学習データに含まれる著作物と類似度の高い生成物をブロックする機能を設けます。
このような措置は、事業者の責任軽減だけでなく、利用者の意図しない著作権侵害を防ぐ効果も期待できるでしょう。
また、利用者に対しては学習データの内容や適切な利用方法について情報提供を行い、著作権侵害のリスクを軽減するためにガイドラインを提供することも、重要な取り組みと言えます。
侵害発生時の対応体制
万が一、著作権侵害が発生した場合の対応方法を事前に整備しておくことも重要です。
権利者からの指摘や削除要請があった場合は、速やかに事実関係を調査し、侵害が認められる場合は迅速に対応すべきです。
対応体制には、法務担当者、技術担当者、経営陣の役割分担を明確にし、エスカレーション手順を定めておきましょう。
また、「海賊版対策情報ポータルサイト」に掲載されている「無料弁護士相談窓口」など、外部の相談窓口も活用できるよう、事前に情報を整理しておくと安心です。
AIと著作権の今後の動向

AIと著作権を巡る法的な環境は急速に変化しており、技術の進歩に対応した新たなルール作りが世界各国で進んでいます。
 弁護士
弁護士今後の動向を把握しておくことが大切です。
文化庁審議会は「AI生成物の扱い」を継続検討
文化庁では2024年3月に「AIと著作権に関する考え方について」を公表しましたが、これは現時点での解釈を整理したものであり、今後も継続的なアップデートが予定されています。
審議会では、AIの開発や利用によって生じた著作権侵害の事例収集に努めており、具体的な事案を通じて考え方の見直しや必要な検討を行っていく方針です。
特に注目されているのは、AI生成物の著作物性に関する「創作的寄与」の判断基準の明確化です。
プロンプト入力や選択する行為がどの程度評価されるかについて、より具体的な指針が示される可能性があります。
また、関係者間の健全なコミュニケーション促進に向けた取り組みも進められており、クリエイターとAI事業者の共存を目指した新たな枠組み作りが検討されています。
海外では裁判例が増加
アメリカでは生成AIとフェアユースを巡る裁判が40件以上起こされており、その判決内容は国際的に大きな影響を与える見込みです。
たとえば、2024年6月のAnthropic事件判決では、訓練のためのコピーがフェアユースに当たるとの判断が示されましたが、これは地裁レベルでの判決であり、今後の上級審での判断が注目されています。
また、ディズニーやNBCユニバーサルがMidjourneyを著作権侵害で提訴するなど、大手企業による訴訟も増加中です。
EUでは2025年中にAI規制法の施行が予定されており、この内容によっては日本企業も影響を受ける可能性があります。
こうした海外の動向は、日本の法解釈や将来の法改正にも影響を与えるでしょう。
国際的な法制度との調和
AI技術が国境を越えて利用される現状を踏まえ、国際的な法制度の調和を図る動きがあります。
各国の情報解析規定には、適法アクセスの要件やオプトアウト制度の有無など様々な違いがあり、これが国際的なAI開発の障壁となっています。
WIPO(世界知的所有権機関)などの国際機関では、AI時代に対応した著作権制度の在り方について議論が進められています。
日本が世界に先駆けて導入した情報解析規定の経験は、こうした国際議論において重要な参考事例となっており、今後の国際的な基準作りに影響を与える可能性があります。
新たな権利保護制度
急速なAI技術の進歩に対応するため、従来の著作権制度を補完するための新たな権利保護制度の検討も始まっています。
特に注目されているのは、AIの学習を拒否する権利(オプトアウト権)の法制化や、AI学習に対する対価還元制度の導入です。
クリエイターの創作インセンティブを保ちながら、AI技術の発展も阻害しない制度設計が求められており、複数のステークホルダーを巻き込んで議論が進められています。
また、AI生成物の来歴を明示するための技術的標準の策定や、人間による創作物とAI生成物を区別するための表示制度の導入なども、検討課題となっています。
企業の自主的な取り組み
法整備に先行して、企業レベルでの自主的な取り組みも広がっています。
大手AI開発企業では、著作権侵害のリスクを軽減するために、学習データの透明性を高めたり、技術的な防止措置を強化したりする取り組みが始まっています。
また、クリエイターと協力関係を結び、正当な対価でライセンス契約を締結する事例も増えてきました。
コンテンツ業界では、AI生成物の利用に関するガイドライン策定や、業界団体を通じた自主規制の検討も進んでいます。
こうした自主的な取り組みは、将来の法制度設計の参考となるだけでなく、業界全体の健全な発展にもつながっていくでしょう。
知的財産戦略の見直し
政府の「知的財産推進計画2025」では、日本でのAI活用が十分に進んでいないという課題が指摘されており、この状況を改善するための施策検討が進んでいます。
AIと著作権の関係だけでなく、クラウドサービスやNFTなどの新技術に対応した著作権制度の在り方についても継続的な検討が行われています。
また、デジタルトランスフォーメーション時代に対応した知的財産制度全体の見直しも視野に入れられており、AI時代に相応しい知的財産のあり方を再検討することが求められています。
このような動きは、企業の知的財産戦略にも大きな影響を与えるでしょう。
AIと著作権についてよくある質問
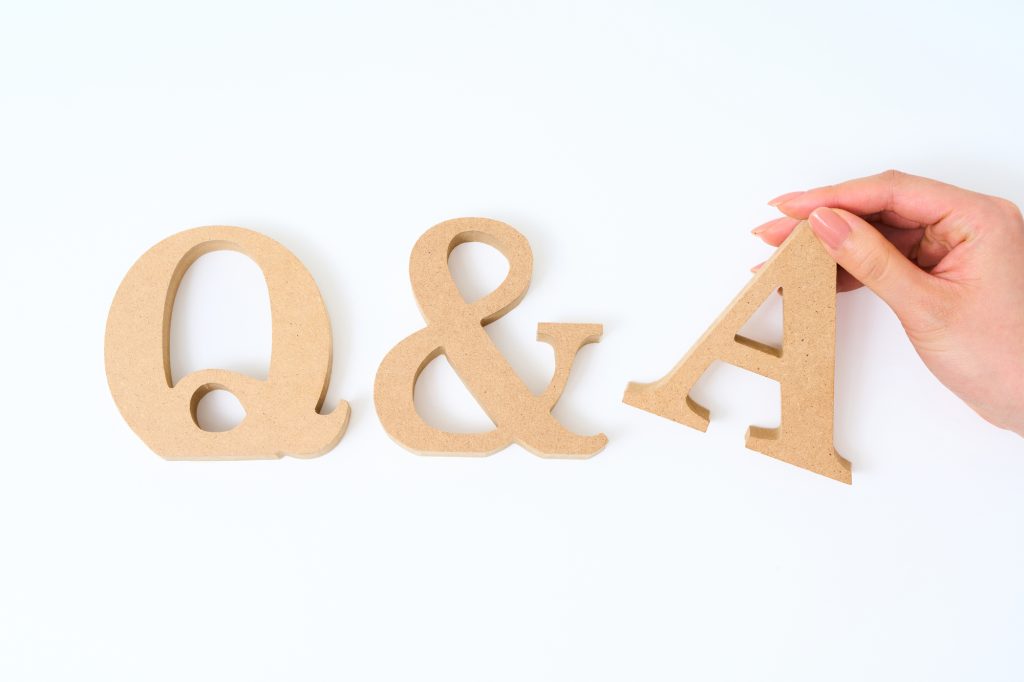
AI活用で頻繁に寄せられる、著作権に関する疑問について回答します。
実際のリスクと対策をふまえ、安全にAIを活用しましょう。
まとめ:安全にAIを活用するには「正しい理解と事前確認」が不可欠
AIと著作権の関係は複雑ですが、基本原則を理解することで正しく活用できます。
開発・学習段階では享受目的の有無、利用段階では類似性・依拠性が判断基準となります。
AI生成物の著作物性は、人間の創作的寄与により決まり、作風模倣は原則問題ないものの、具体的な表現の類似は、侵害リスクがあります。
企業・個人を問わず、利用前の類似性確認と社内ガイドラインの整備が重要です。
法整備の動向を注視しながら、技術的な措置も講じて安全にAIを活用しましょう。

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。
※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










