「従業員から突然、賃金のベースアップについて団体交渉を申し入れられた」
「労働組合から労働条件の改善を求める交渉の要求書が届いた」
「職場環境の改善について、従業員代表との話し合いを求められている」
など、中小企業や個人事業主にとって労働者からの団体交渉の申し入れは珍しくありません。
いざその時、あなたは冷静に対応できるでしょうか? 例えば大企業なら、顧問弁護士に相談ができるでしょうし、このような交渉ごとに長けた百戦錬磨の担当部署に任せて対処するのが定石でしょう。 しかし、中小企業や個人事業主の場合は、そう簡単にはいかないのではないでしょうか?
本記事では、団体交渉の基本的な流れや対応方法、注意すべきルールについて、詳しく解説していきます。
「弁護士に相談なんて大げさな・・・」という時代は終わりました!
経営者・個人事業主の方へ
労働者(従業員)には団体交渉権がある

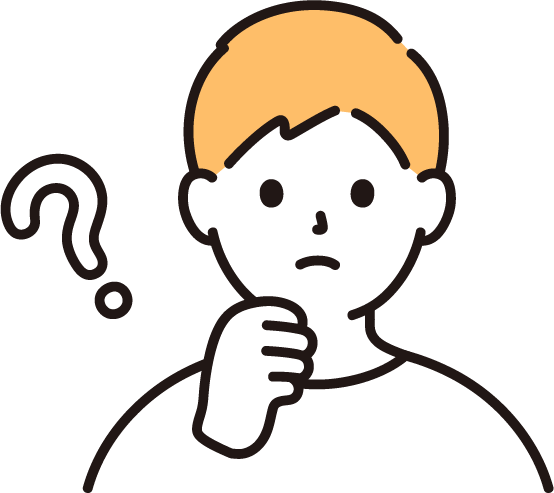
団体交渉権とはどのようなものですか?
 弁護士
弁護士憲法で規定された労働者の権利の一つです。
団体交渉権についての憲法の規定
労働者の権利として、憲法第二十八条で「労働三権」とよばれる、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(ストライキ権)」を認めています。
この条文では、労働者が集団で自身の利益を守るために組織を作り、雇用主と対等の立場で交渉を行うことを保証しています。
これは、労働基準の向上や労働環境の改善を目的としています。
団結権・団体交渉権・団体行動権の違いは?
では、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(ストライキ権)」とはどういった権利なのでしょうか?
団結権
労働者が団結し、労働組合を結成・加入する権利のこと。
- 雇用主と対等の立場で話し合いができるように、労働者が組織を組む、または加入できる権利
- 労働者は集団で自身の利益を守るための組織を作ることができる
団体交渉権
労働者団体が雇用主と労働条件などについて交渉する権利のこと。
- 労働者と雇用主が、労働条件などを交渉し、決定事項を文書で定めることが可能
- 労働組合などの労働者団体が、雇用主と労働条件・賃金・労働時間・安全基準などについて交渉し合意に至る権利
- 雇用主と対等な立場で話し合い、労働者の利益を代表して合意を目指す過程を保障する
団体行動権
要求を通すために、ストライキなどの集団行動を行う権利のこと。
- 交渉や労働条件の改善のために、ストライキやデモなどの集団行動を行うことが可能
- 団体交渉が決裂した場合に、労働者が集団で行動することで、その要求を力強く主張することができる(ビラ配り・SNSでの発信もその活動の1つ)
団体交渉の拒否や無視はできる?

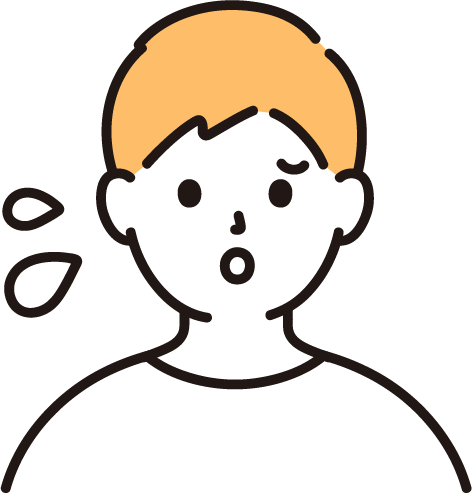
正直なところ、申し入れを拒否したいです…。
 弁護士
弁護士企業が労働組合からの団体交渉を拒否、又は団体交渉の申し入れを無視することは、原則として労働組合法に違反しており、違法行為となります。
ただし、団体交渉の内容が「任意的団交事項」に該当する場合、企業側には団体交渉に応じる義務はありません。
~例~
- 会社の経営戦略や生産方法などに関すること
- 他の労働者のプライバシーに関わること(他の労働者の賃金や退職金の開示要求など)
任意的団交事項は、労働組合と雇用主が自由に協議できる事項です。
そのため、正当な理由の有無とは関係なく、団体交渉権を拒否することができます。
団体交渉の流れ・進め方は?
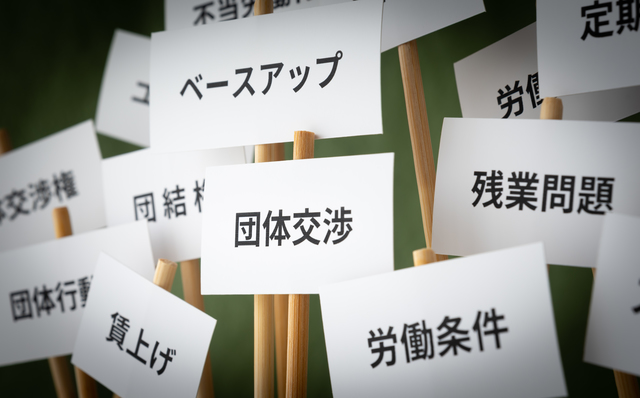
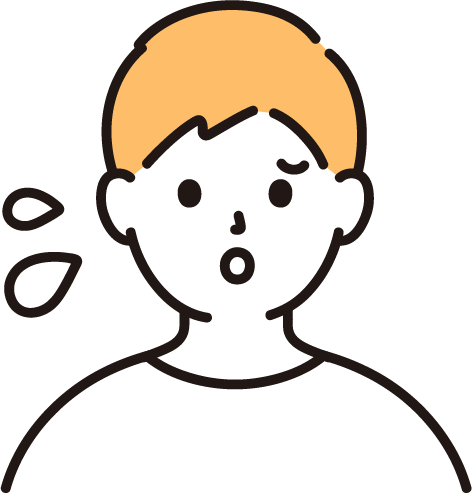
団体交渉の申し入れが突然だったので、準備も心構えもできていない状態です…。
 弁護士
弁護士何の前触れもなく団体交渉の申し入れがあることはままあります。
常日頃から対応について検討しておくことが大事です。
「ある日突然、労働組合から『要求書』など諸々の書類一式が送られてくるかもしれない」
「近々の日程で期日を切られ対応を迫られることがあるかもしれない」
そういったことを、考慮しておく必要があるでしょう。
ましてや、団体交渉についての知識がないまま、対応を迫られその結果、会社にとって不利な条件を飲まされることもあるかもしれません。
交渉の結果「高額の解決金で決着した」という場合、不本意かもしれませんがまだ会社にとってのダメージは、最小限で抑えられたと言ってもいいでしょう。
しかし、上手く交渉がまとまらなかった場合の最悪な結果として、
- 不当な誹謗中傷
- 街宣活動
- ビラ配りやSNSでの発信などを大々的に行われてしまう
こういった行為に発展してしまうと、会社のイメージが悪くなるばかりか、甚大な被害を受ける可能性があります。
そうならない為にも、実際に団体交渉をしていく中での大まかな流れを説明していこうと思います。
団体交渉の日時、場所、出席者は事前に協議が必要
ホームページを持っている組合もありますので、一度組合名で検索をしてみるのもいいでしょう。
ほとんどの場合、活動報告などが掲載されているので組合がこれまでに関わった事件や活動方針を知ることができるのではないでしょうか。
その活動報告のなかに、「自宅まで押し掛けた」「抗議文を直接手渡した」「ビラ配りを行った」等の活動報告の記載がある場合は、今回も同じ行動が予測されるため、事前に弁護士に相談するなどして慎重に対応策を練ることをおすすめいたします。
加入通知書が送られてきますので、該当組合員が在職中なのか?既に会社を退職しているのか?以前に解雇した社員なのか?を確認しましょう。
在職中の社員の場合
→給与・賞与アップや職場環境の改善を求めるなどが争点となることが多い傾向にあるため、一般的に長期化することが予想されます。
既に退職をした元社員の場合
→主に未払い残業代などが争点となる向きが多いため、比較的早く解決できる可能性があります。
最近解雇した元社員の場合
→解雇処分の取り消しを主張してくるケースもありますので、弁護士(専門家)に相談をし、どのように対応をしていくのか慎重に対応をしていくことが重要でしょう。
開催日時について
団体交渉申入書には、大抵の場合直近の日程で初回の候補日が明記されています。
相手側が指定した日の都合がつかなければ、日程の再調整を申し出ましょう。
大切なことは団体交渉を進めていくにあたって、あらかじめ余裕のある日程を申請するということです。
少なくとも2週間程の準備期間を確保しておく必要があります。
準備不足のまま慌てて団体交渉に臨む、ということだけは避けましょう。
団体交渉の開始時間と終了時間について
交渉の開始時間は、就業時間内ではなく、なるべく就業時間以降に設定しておくことをおすすめします。
就業時間内で実施してしまうと、交渉している時間分の給与も従業員に支払わなければならなくなります。
また、終了時間についても、明確に何時までと決めておきましょう。
なかなか交渉を終わらせてくれないこともありますので、「一回の団体交渉は2時間以内で終了する」など条件を明示しましょう。
開催場所について
申し入れをした相手側の希望場所に合わせる必要はありません。
使用時間に制限のある外部の会議室などで実施することをおすすめいたします。
団体交渉でやってはいけない事・注意すべきルール

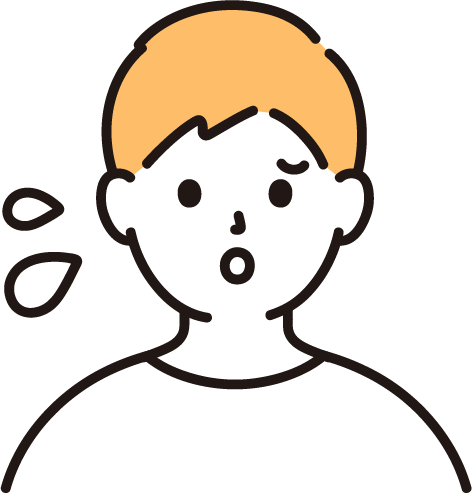
団体交渉時にやってはいけないこと等はありますか?
 弁護士
弁護士主なところでは「理由なく拒否してはならない」「決定権がある者が参加する」「安易にサインしない」という点に注意すべきです。
1:不当労働行為のルール
労働組合法(労働組合法第7条)では、雇用主が労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒否することを、不当労働行為として禁止しています。
団体行動権の実効性を確保するため、雇用主は団体交渉のテーブルに着くことが義務付けられています。
2:誠実交渉義務違反
会社の代表者が団体交渉に出席する必要は必ずしもあるわけではありませんが、交渉する労働条件等についての決定権のない者のみで出席することは「不誠実な団体交渉」となり、「不当労働行為」となる可能性があります。
会社の代表者が出席できない場合は、代表者から団体交渉への対応を一任されている取締役や、人事部など部長職に就いていて労働条件等について会社代表者と同程度の権限を持つ人が出席する必要があります。
事前に決めておくべきこと
- 発言する者をあらかじめ決めておく
- 団体交渉における争点が複数ある場合、争点ごとの発言者を決めておく
3:労働協約について
- 賃金・労働時間・休暇・安全衛生・解雇や雇用に関する規定など、労働条件全般にわたる事項が含まれている
- 雇用主と労働者双方に、法的拘束力を持つ契約である
- 協約の規定に違反した場合は法的責任を負うため、十分精査する必要がある
団体交渉の場で、労働者の代表者が協定書や合意書などを事前に準備し、会社側にサインを求めてくることがあります。
ここで注意しなければならないことは、安易に書類にサインすべきではないということです。
サインを求められた場合は、内容をよく精査した上で行わなければならないということと、サインをするにあたって修正すべき点などがないか確認し、相手側に申し出ましょう。
従業員が団体交渉をするメリットとは?

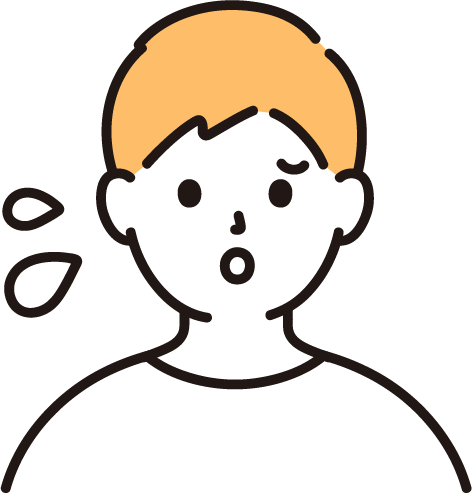
そもそも、従業員は団体交渉を行うことにメリットがあるんですか?
 弁護士
弁護士団体交渉という制度は、労働者が集団で雇用主と交渉することができる点が一つのメリットといえます。
従業員が単独で雇用主と交渉するよりも、はるかに大きな影響力を持つことができると考えられます。
- 労働条件の改善
賃金UPや、より働きやすい労働時間の設定、休暇についての要望などの労働条件について訴えることができる - 職場の安全と健康の確保
労働環境の安全性や健康に関する基準(悪質な労働環境)改善、または向上の交渉
※適切な安全装備の提供・有害な労働条件の改善を含む - 雇用の安定性について
解雇条件・雇用保証・リストラ時の対応など、雇用関連の取り決めを行うことができる(従業員は、より安定した職場環境を手に入れることが可能になる)
従業員が団体交渉をするデメリットはある?

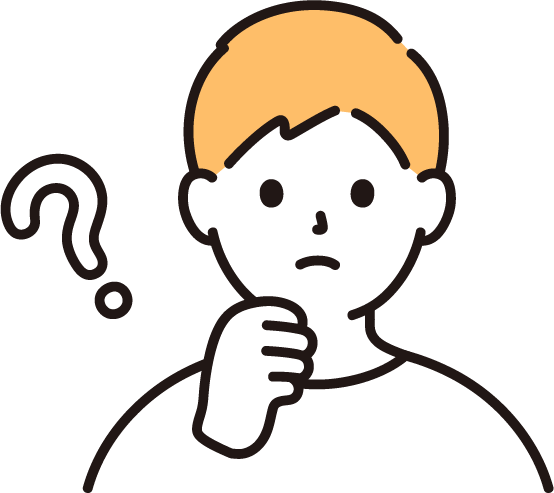
では、団体交渉にはデメリットはないんですか?
 弁護士
弁護士体力面や精神面でデメリットがあるといえます。
就業時間外で活動を行わなければならない
一番は、事前の準備や当日の対応などが大変であるということに尽きるとは思います。
さらに、基本的に団体交渉(労働組合)の活動は労働時間外に行います。
一部例外はありますが、就業時間前や休憩時間・就業後・休日などに資料等の作成準備をする必要があるため、通常の仕事やプライベートとのバランスが取りづらくなる可能性があります。
雇用主側のデメリット
雇用主側が就業時間内での団体交渉を容認してしまうと、その時間分の賃金を会社が保証しなければならない場合があります。
また、「所定労働時間内の労働組合の活動を認めた」と相手側に主張される可能性がありますので、基本的には就業時間外に団体交渉をするように申し出ましょう。
交渉プロセスの長期化
団体交渉は時間がかかります。
具体的には、およそ合意に達するまでに数ヶ月から数年を要することもあります。
この期間中、従業員は何も決まらないままの状態で働く必要があり、ストレスや不安を感じることもあるでしょう。
経済的コスト・職場環境の悪化
ストライキなどが行われた場合は、従業員に直接的な経済的損失をもたらすことになります。
ストライキ中は給与が支払われない場合が多く、これが家計に大きな影響を及ぼすことは容易に想像ができます。
また、対立が激しくなり緊迫した状態は、職場の雰囲気を悪化させ、将来的に信頼関係の再構築が難しくなるでしょう。
団体交渉が決裂した場合の対処法は?
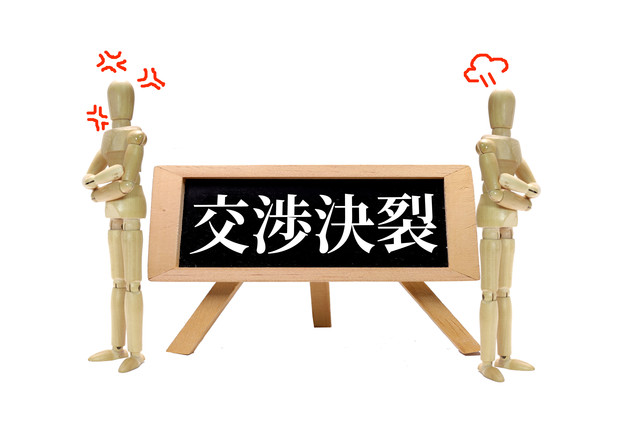
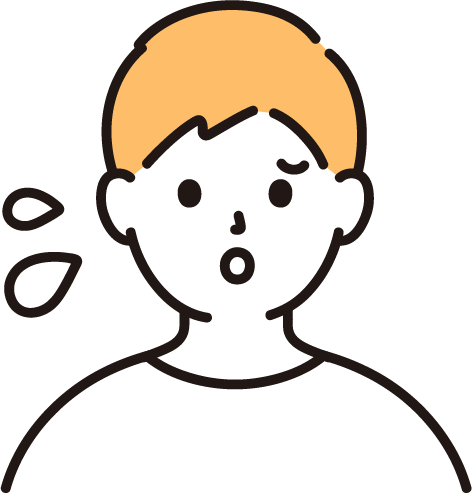
団体交渉の内容に納得ができず、結果的に決裂してしまいました…。
 弁護士
弁護士団体交渉が決裂した場合は、労働委員会への救済申し立てや裁判所での争いに移行する可能性が高いです。
なんとか穏便に双方納得するための対処法を、下記に記載しますので是非参考にしてください。
第三者機関に間に入ってもらい、調停を通じて解決の糸口を探す
交渉の準備を再度見直し、新たな提案や交渉戦略を練る
団体交渉の過程や内容を見直し、法的な問題がある場合は法的措置を検討する
合法的な範囲内で、ロックアウトを検討する
交渉内容や進捗状況を公開し、世論や関係者の支持を集める
双方が受け入れ可能な代替案を提案し、お互いの妥協点を見つける
団体交渉は事前に弁護士へ相談

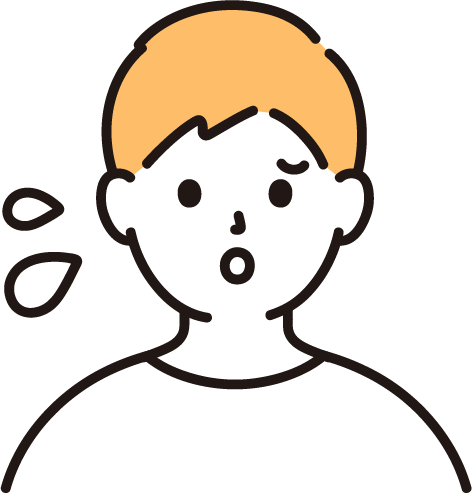
自分は法律に詳しくなく、一人で対応するのは不安です…。
 弁護士
弁護士相手にする組合は、労働問題を数多く扱っていることを念頭に置いておく必要があります。
労働関係の法律に関する知識等がかなり豊富だということを覚悟して、経営者1人(少数)で対抗することは避けましょう。
なぜなら、労働関係法に関する失言の揚げ足を取られ、そのまま不利な条件を飲まされてしまうこともあるからです。
団体交渉に臨むには、労働関係法・団体交渉に関する知識が必須ですので、なるべく早い段階で弁護士(専門家)に相談をすることが大切です。
まとめ
団体交渉とは、簡単に言うと、労働組合や企業などの団体が、労働条件や給与などの労働関係に関する取り決めを行うプロセスです。
労働組合などの労働者団体と雇用主との間で行われる、賃金・労働時間・休暇・安全や衛生条件などの労働条件や雇用条件に関する合意を目指す協議のことです。
長く険しい戦いになるかもしれませんが、この記事が少しでもお役に立てることを心から願っております。
双方にとってより良い結果にたどり着けますように。
また、弁護士保険でトラブルの予防をするのはいかがでしょうか。

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。
※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










