「裁判で相手が平然と嘘をついてくる」
「明らかにデタラメな主張をしているのに、なぜ処罰されないの?」
「こんな虚偽が法廷で通用するなんて許せない」
このように、民事裁判で相手方の虚偽陳述に悩まされていませんか?
結論から言うと、民事裁判で相手が嘘をついても、偽証罪で処罰されることは極めて稀です。
当事者本人には偽証罪は成立せず、証人の偽証も立証が困難なため、実際の処罰例はほぼありません。
しかし、相手の虚偽に対抗する、効果的な対処法はあります。
また、客観的証拠の収集や論理的な反証により、裁判を有利に進めることは十分可能です。
本記事では、偽証罪が成立する要件から実際の処罰事例、相手の嘘の見抜き方など、裁判で立ち向かう具体的な方法について、弁護士監修のもと、わかりやすく解説します。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
裁判で相手が平然と”嘘”をつくことは珍しくない

残念ながら、民事裁判において相手方が事実と異なる主張を展開することは、決して珍しいことではありません。

法廷の場で嘘をつくなんて、不誠実に感じます。
 弁護士
弁護士たいていの場合は、記憶があいまいになっていたり、自分に都合が良いように主張したりするために、「嘘の証言をしている」と感じることがあります。
「こんなデタラメが通用するのか?」と感じたあなたへ
裁判の法廷で相手方が明らかに事実と異なるデタラメな主張をしたり、証人尋問で嘘の証言をしたりする場面に遭遇すると、多くの当事者が強い憤りを覚えるかと思います。
それは当然のことです。
しかし、民事裁判制度では、嘘の主張や証言に対して刑事処罰を科すためのハードルは想像以上に高いです。
偽証罪が成立するのはごく限られた条件の場合のみで、裁判の当事者本人が虚偽を述べても偽証罪は成立しません。
また、陳述書に虚偽の内容を記載しても、宣誓を伴わないため、犯罪にはならないのが現実です。
このような制度の背景には、記憶のあいまいさや主観的認識の違いを考慮するという法的な配慮があります。
これは、民事訴訟が真実の解明よりも、当事者の主張と証拠に基づいて判断することを重視する制度であるためです。
民事裁判では”嘘”が日常的に登場する理由
実際の民事訴訟では、原告と被告の主張が正反対であることも多く、自分に都合の良い事実を主張するのが一般的です。
現実には、「たいていの人が嘘をついている」と考えた方が実態に近いでしょう。
さらに、記憶のあいまいさや事実の混同も大きな要因となっています。
たとえ本人に嘘をついている自覚がなくても、結果的に事実と異なる主張が生まれることは頻繁にあります。
時間の経過とともに記憶が変化したり、希望的観測が入り混じったりするためです。
このような状況下では、原告と被告の間で、感情的な対立が激しくなる傾向にあります。
裁判で嘘をつくと成立する犯罪・偽証罪とは?

 弁護士
弁護士偽証罪は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立します。(刑法169条)

どんな時に偽証罪が成立するのでしょうか?
偽証罪が成立する3つの条件
偽証罪が成立するには、3つの条件がすべて揃う必要があります。
1つ目は、「証人」であることです。
裁判の当事者(原告・被告・被告人)は証人にはなれません。
つまり、裁判で争っている本人たちがいくら嘘をついても、偽証罪にはならないということです。
2つ目は、「宣誓」が必要です。
これは証人尋問の前に「私は嘘をつかないです」と誓うことで、具体的には「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と宣言します。
この儀式的な手続きがあって、初めて偽証罪の対象になります。
3つ目は、「記憶に反する虚偽」です。
ここが重要なポイントで、客観的な事実と違うことを言っても、本人が「そのように覚えている」と言うのなら偽証罪にはなりません。
逆に、客観的には正しいことでも、本人の記憶と違うことを意図的に言ってしまうと偽証罪になります。
つまり、本人の勘違いについては罪にならないけれど、意図的な嘘は罪になりうるのです。
偽証罪の罰則:懲役3か月~10年(罰金刑なし)
偽証罪の刑罰は、3か月以上10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
これは非常に重い刑罰といえるでしょう。
裁判は証人の証言を信用して判断するため、その信頼を裏切る行為には厳罰で臨む必要があります。
ただし、救済措置もあります。
「嘘をついた」ということを判決が確定する前に認めれば、刑を軽くしてもらったり、免除してもらったりできる可能性があります。
この場合、嘘をついたことを認めるだけで十分で、必ずしも真実を話す必要はありません。
実際の運用では、執行猶予がつくケースも多いですが、有罪となれば前科がつきます。
このリスクの大きさが、証人に真実を話すよう促す抑止力として作用しています。
偽証罪が成立しないケースとは?
偽証罪は、多くの方が思っている以上に、限定的な犯罪です。
最も大きなポイントは、裁判の当事者本人には、絶対に偽証罪が成立しないことです。
民事裁判の原告・被告、刑事裁判の被告人がどんなに嘘をついても偽証罪にはなりません。
彼らは「証人」ではなく「当事者」だからです。
また、宣誓していない場合も、偽証罪には問われません。
例えば、裁判所に提出する陳述書に嘘を書いても、宣誓を伴わないため犯罪にはならないのです。
これは第三者が書いた場合も同じく犯罪にはなりません。
また、16歳未満の子どもや、宣誓の意味を理解できない人は宣誓させることができないため、偽証罪の対象外です。
さらには、記憶違いも偽証罪にはなりません。
本人が「そう覚えている」ことを話した場合、それが客観的事実と違っていても罪にはなりません。
偽証罪で問題になるのは「自分の記憶と違うことを意図的に言う」場合だけです。
つまり、善意の間違いは処罰されないということです。
宣誓無能力者と証言拒絶権の特例規定
法律では、宣誓できない人や証言を拒否できる人について、細かく定めています。
16歳未満の子どもは宣誓の意味を理解できないとして、宣誓なしで証言してもらいます。
このため、子どもが嘘をついたとしても偽証罪には当たりません。
そして、「証言拒絶権」というのもあります。
これは「証言すると自分や家族が刑事処罰を受ける可能性がある」「医師や弁護士が職業上知った秘密に関する」といった場合に、証言を拒否できる権利です。
正当な理由で証言を拒否した場合は何の問題もありませんが、理由もなく証言を拒否すると10万円以下の過料を科される可能性があります。
このような規定は、証人の人権を守りながらも、適切な証言を確保するバランスを取ったものです。
無理に証言させて人権侵害を起こすよりも、証言拒絶を認めた方が制度全体の信頼性が高まるという考え方に基づいています。
偽証罪が適用されるハードルは高い
民事裁判で、偽証罪が成立することはほとんどありません。
なぜなら「本人の記憶と違うことを言った」ことを証明するのが極めて困難だからです。
客観的に嘘だとわかっても、証人が「私はそう覚えています」と言えば、それ以上追及できません。
誰も決して人の頭の中をのぞくことはできないからです。
さらに、民事裁判では、刑事事件のような詳細な捜査が行われません。
たとえば、刑事事件なら警察が証人を取り調べて矛盾を追及します。
しかし、民事裁判では当事者が自分で証拠を集めるしかなく、偽証を立証するのは非常に難しいといえるでしょう。
実際に、民事訴訟において、宣誓した第三者証人が虚偽の証言を行い、偽証罪で有罪となった事例は、過去15年を振り返っても公表された確証あるケースはほとんどありません。
捜査機関も民事の偽証には関心が薄く、よほど悪質でない限り起訴されることはないでしょう。
「記憶にない」という証言の法的位置づけは?
証人尋問でよく聞く「記憶にありません」という答えは、法的には微妙な位置づけにあります。
本当に覚えていないなら何の問題もありませんが、実際は覚えているのに「記憶にない」と嘘をつくのは、偽証罪になる可能性があります。
ただし、「記憶がないかどうか」の実際の立証は困難です。
本当に忘れているのか、嘘をついているのかを外部から判断することはできません。
 弁護士
弁護士この証明の難しさが、「記憶にない」という逃げ道を使いやすくしているともいえます。
実務上、不利な質問をされたときの常套句として「記憶にない」が使われることが多いとされています。
しかし、あまりに連発すると裁判官の印象が悪くなり、証言全体の信用性が疑われるリスクもあります。
戦術として使うにしても、使いすぎは逆効果になることがあります。
嘘・勘違い・主観のズレをどう判断する?

 弁護士
弁護士相手の陳述が嘘なのか記憶違いなのか、それとも主観の違いによるものなのかを正確に見極めることは、裁判の方針を立てるうえで、非常に重要と言えます。

実際にはどうやって判断しているのでしょうか?
陳述書や証言の嘘を見破る3つのチェックポイント
虚偽陳述を見抜くには3つのポイントをチェックします。
1つ目は、一貫性の検証です。
同一人物の複数の陳述書を並べて「第一回は午後3時、証人尋問では夕方5時」といった矛盾を探します。
2つ目は、時系列の整合性です。
物理的に不可能なスケジュールや、重要な場面だけ記憶があいまいになっているケースは、矛盾を指摘しやすいと言えます。
3つ目は、客観的証拠との照合です。
メールや契約書、通帳記録など改ざんが困難な証拠と照らし合わせることで事実関係を確認できます。
特に「段外証拠の提示」という手法では、証人尋問当日に反証となる資料を示し、相手の発言との矛盾を明らかにできます。
嘘の種類を分類し、対応戦略を分けるべき理由
虚偽陳述には種類があり、それぞれの特徴に合わせて適宜対応する必要があります。
まず「故意の虚偽」は、事実を知りながら意図的につく嘘であり、この場合は客観的証拠を用いた反証が最も効果的です。
次に「記憶の曖昧さによる誤認」は、悪意のない単純な間違いです。
この場合も相手を責めるのではなく、客観的証拠で正しい事実を示すことが有効となります。
最後に「主観的認識の相違」は同じ出来事に対する異なる解釈です。
例えば、一方が「脅迫」と感じても、もう一方は「説得」と認識している場合などがこれに当たります。
このようなケースは法的基準に照らした論理的主張が求められます。
このように対応を分ける理由は、誤った対応が逆効果を生むからです。
たとえば、単なる記憶違いの相手を「嘘つき」と非難すれば、裁判官から「過度に攻撃的している」と見られるリスクがあります。
虚偽陳述の典型パターンと発見のコツ
虚偽陳述には決まったパターンがあります。
最も多いのは「都合の悪い事実の隠蔽」で、自分に不利な行為を「していない」と否認するケースです。
このタイプは、客観的証拠があれば、比較的立証することは簡単です。
また、「事実の歪曲・誇張」も頻繁に見られます。
これは、基本事実は認めつつ、程度を自分に有利に修正するパターンです。
「大声で怒鳴った」を「やや声を荒げた」と矮小化するなどが該当します。
心理的には、多くの人は完全な嘘をつくことに抵抗があるため「半分は本当」の話を作る傾向があります。
そのため、真実部分と虚偽部分を切り分けて対応することが効果的です。
また、利害関係を分析することで「どの部分で嘘をつく可能性が高いか」を予測できます。
物理的証拠と状況証拠の効果的な組み合わせ
虚偽陳述に対抗するには、物理的証拠と状況証拠をうまく組み合わせることが重要です。
物理的証拠(文書、録音、写真など)は証明力が高いものの、すべての事実において存在するわけではありません。
一方、状況証拠は間接的ですが、事実を推認させる力があります。
たとえば、契約締結後に相手が別業者と同様の契約を結んでいた場合、最初の契約に問題があった可能性を示す手がかりとなります。
効果的な進め方としては、物理的証拠で確実な事実を示し、その周辺を状況証拠で固めていくことです。
証拠の提示順序も重要で、まず動かしがたい物的証拠で相手の主張の一部を崩し、その上で状況証拠を積み重ねていく方法が挙げられます。
こうすることで、相手の陳述全体の信用性を徐々に低下させられるでしょう。
裁判で嘘をついて処罰されたケース

裁判で嘘をついた場合の実際の処罰例は極めて稀ですが、処罰された事例を詳しく分析することで、どのような場合に法的制裁が科されるのかが見えてきます。
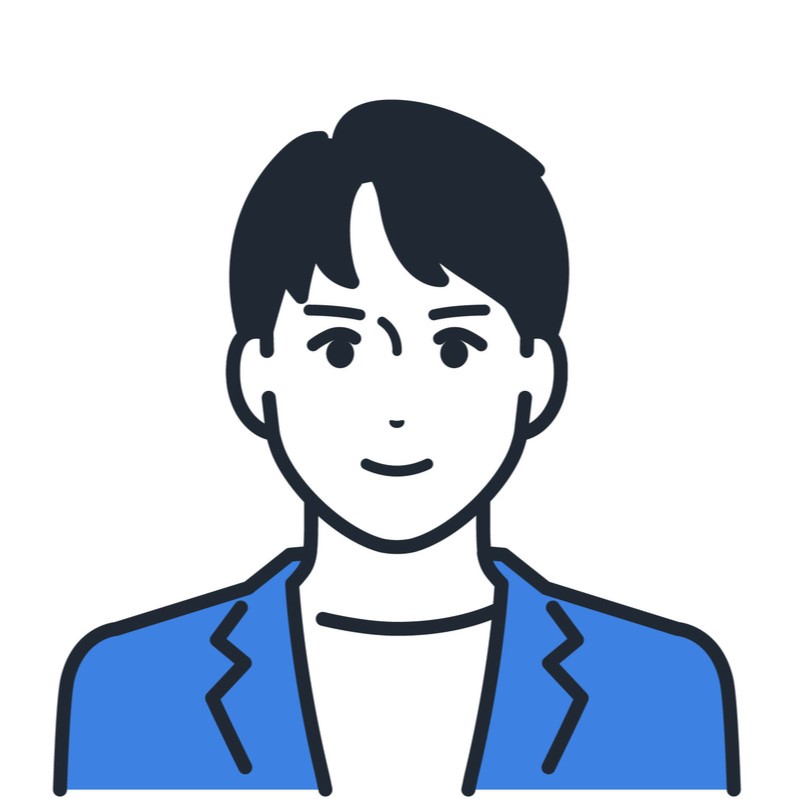
実際に処罰に至った事例があるのですね。
 弁護士
弁護士刑事事件などでは比較的有罪となるケースが見られますが、民事事件ではそうそうありません。
非常勤講師を偽った被告に過料10万円(令和 3 年 10 月 20 日判決 名古屋地裁)
交通事故の損害賠償請求事件で、被告が大学の非常勤講師であると偽って休業損害を請求し、当事者尋問でも「A大学で学生相手に講義をしている」「1ヶ月に3回程度講義を行っている」と虚偽証言した事例があります。
裁判所が民事訴訟法209条1項に基づき被告に10万円の過料を科すという、異例の決定を下しました。
注目すべきは、訴訟の経緯です。
被告は当初「家事従事者」と主張していたにもかかわらず、数ヶ月後に突然「大学の非常勤講師」に変更。原告側の就業先開示要求にもすぐには回答せず、不自然な経過を辿りました。
決定的だったのは、当事者尋問後に裁判官が原告にA大学への調査嘱託を促すという異例の対応です。
この調査で勤務実態がないことが判明し、「重要な争点に関する故意の虚偽陳述は極めて不誠実かつ悪質」として過料が科されました。
偽証罪が実際に成立した事例(刑事・国会証人尋問など)
偽証罪の有罪事例は、主に刑事事件と国会証人喚問で見られます。
刑事では、詐欺・恐喝事件で証人が被告人との関係について虚偽証言した大阪地裁事例(平成22年11月25日)や、交通事故で自分に有利な嘘をついた福岡地裁事例(平成18年7月19日)があり、懲役1年6か月執行猶予3年といった重い処罰が科されています。
国会では鈴木宗男氏の建設会社からの資金提供に関する偽証や、山口敏夫氏の財団への財産流用否定の偽証事件が有名です。
これらが処罰に至った背景には、詳細な捜査と客観的証拠の存在がありました。
一方、民事で偽証罪が成立しにくい理由は明確です。
偽証罪の「主観説」により証人の記憶に反する証言の立証が困難で、民事では供述調書も存在しません。
捜査機関も関心が薄いため、過去15年で確証あるケースはほとんどない状況が続いています。
虚偽鑑定等罪で処罰された専門家の事例
偽証罪に類似した虚偽鑑定等罪の成立要件は、「法律により宣誓した鑑定人・通訳人・翻訳人が虚偽の鑑定・通訳・翻訳を行った場合」です。
偽証罪と同様、3か月以上10年以下の懲役という重い刑罰が科されます。
たとえば、医師が保険金詐欺に加担して虚偽の診断書を作成した事件や、建築士が耐震偽装で虚偽の構造計算書を作成した事件などがあり、専門家としての社会的信頼を裏切った行為として実刑判決が下されるケースも少なくありません。
虚偽鑑定等罪が、偽証罪より処罰されやすい理由は、以下のとおりです。
- 専門家の作成する書面が客観的証拠として残りやすい
- 虚偽の立証が容易である
- 専門家の虚偽は社会への影響が大きい
そのため、捜査機関も積極的に捜査する傾向にあります。
虚偽告訴罪による処罰と事例
虚偽告訴罪は、偽証罪と同じ3か月以上10年以下の懲役が科されます。
近年、痴漢冤罪やDV虚偽告発で注目を集め、処罰事例も増加傾向にあります。
具体的には、離婚調停を有利にするため夫のDVを捏造して虚偽被害届を提出した女性や、金銭トラブルの相手を陥れるため窃盗の虚偽告訴をした事業者が処罰されています。
被害者の人生を破壊する可能性のある悪質行為として、執行猶予なしの実刑判決もあります。
虚偽告訴罪が処罰されやすいのは、告訴内容と客観的事実の矛盾が発見しやすく、被告訴人の無実証明で虚偽が明らかになるためです。
司法制度の根幹を揺るがす行為として検察も積極的に起訴する傾向があります。
国会証人喚問における偽証罪の特殊性
国会証人喚問の偽証罪は、通常の裁判とは異なる特徴があります。
国会証人を偽証罪で起訴するには、証人喚問実施委員会が出席委員の3分の2以上の賛成で議決し、検察に告発するという手続きを経なければなりません。
こうした手順が必要なため、処罰の可否は法的判断だけでなく、政治的な判断にも左右されます。
実際の処罰事例では、政治的背景や社会的注目度が大きく影響し、政治家の証人喚問では政治的思惑が絡みます。
そのため、明らかな偽証があっても告発に至らないケースも少なくありません。
一方で、告発された場合の処罰は重く、政治家としての活動が事実上続けられなくなることも多いです。
国会証人喚問における偽証罪は、法的処罰と政治的制裁の両面を持ち、国民の知る権利や政治の透明性を確保するうえでも、重要な制度と言えます。
しかし、運用には政治判断が大きく影響するという課題も抱えています。
裁判での嘘にどう立ち向かうべきか?

相手の虚偽主張に感情的に反応するのではなく、戦略的かつ冷静なアプローチで対抗することが、裁判で勝利をつかむ鍵となります。

「相手が嘘をついている」と気づいた時、どうすればいいのでしょうか?
 弁護士
弁護士まずは証拠集め、次に矛盾点を探す、というように段階的に動いていくとよいでしょう。
段階的なアプローチ
ステップ1:嘘を立証するための証拠を集める
虚偽陳述に対抗するうえで重要なのは、客観的な証拠の収集です。
相手の嘘を感情的に批判しても裁判官の判断には影響しにくいため、改ざんが困難で第三者が検証できる証拠を揃えることが、結果を大きく左右します。
まず、文書証拠を徹底的に集めましょう。
契約書、領収書などの原本はもちろん、メールやLINEのやり取りも有力な資料となります。
メールは送受信日時が記録されており、相手の主張する時系列との矛盾を示す根拠として有効です。
金銭関係では、通帳の記録が特に重要です。
「支払った」と主張する相手に対し、該当日に入金記録がないことを示せば、虚偽は明らかです。
また、携帯電話の通話履歴、クレジットカード明細、ETCの利用記録なども、相手の行動を示す客観的な証明として活用できます。
ステップ2:矛盾を論理的に崩す・小さな矛盾から嘘を破綻させる
嘘は、必ずどこかで矛盾を生むものです。
相手の陳述書や証言を時系列に沿って整理し、論理的な一貫性をチェックすることで、虚偽の綻びを発見できます。
小さな矛盾を見逃さず、体系的に分析することが重要です。
たとえば、「午前中に会社にいた」と言いながら「同じ時間に別の場所で契約していた」と主張するような場合は、物理的に成り立たないため、虚偽の可能性が高いと言えます。
次に、相手の利害関係と照らし合わせて分析することも重要です。
自分に有利な事実は詳細に記憶しているのに、不利な事実だけ「記憶にない」と答えるような態度は不自然であり、信頼性を疑う根拠となりえます。
また、第三者証言との食い違いも虚偽を見抜くうえで、重要な手がかりとなります。
ステップ3:「段外証拠」で信用性を崩す・尋問中に初出しする戦略の効果
「段外証拠の提示」は、相手の虚偽を明らかにするうえで効果的な手法です。
これは証人尋問の当日に、相手の証言の信用性を揺るがす証拠を提示し、事前に反論の準備をさせないことで動揺を引き起こす方法です。
事前に証拠を提出すると相手が言い訳を準備できますが、証人尋問の最中に反証を突きつけられると、多くの人は冷静さを失い、矛盾した発言を重ねてしまう傾向があります。
具体的には、相手が「4月1日に○○した」と証言した直後に「あなたは4月1日に××していたという証拠があります」と客観的な証拠を示します。
この瞬間の相手の反応は裁判官に強い印象を与え、証言全体の信用性を大きく損なう結果につながります。
ステップ4:重要性の低い嘘には執着しない判断も必要
すべての嘘に同じように対応するのではなく、勝敗に影響する重要な虚偽と些細な食い違いを区別することが重要です。
些細な矛盾に執着しすぎると、本当に重要な争点があいまいにいなり、裁判官に「木を見て森を見ず(細部にこだわりすぎて全体を見ていない)」という印象を与えかねません。
争点の重要度を冷静に評価し、結果を左右する核心部分については徹底的に反証すべきですが、周辺的事実の食い違いはあえて追及しない判断も必要です。
相手の嘘すべてを攻撃すると「悪口の応酬」のような印象を与え、裁判官の心証を損なうリスクもあります。
効果的な対応としては「これが崩れれば主張全体の信頼性が揺らぐ」という核心部分を見極め、そこを集中的に反証することです。
重要でない嘘はあえて踏み込まず、核心的な虚偽に集中することが、効果的な戦い方となります。
感情的対応を避け、冷静な戦略を維持する重要性
感情的な対応は、裁判において逆効果です。
裁判官が評価するのは冷静で論理的、かつ根拠のある主張です。
こちらの主張を論理的に見せるために、落ち着いて事実に基づいた対応を心がけるべきです。
感情的に相手を攻撃すれば「建設的でない」と判断され、裁判官の心証を損なう可能性があります。
さらに、情報の精査ができずに重要な証拠を見落としたり、反論のタイミングを逃したりする可能性も高くなります。
重要なのは「相手が嘘をついているから罰してほしい」ではなく「客観的証拠に基づき、真実はこうです」という姿勢で臨むことです。
裁判官は「誰が誠実か」という点で全体を見ています。
冷静さを保ち、事実に基づいた主張を行うことで、より良い心証を得やすくなります。
裁判官の心証を意識した効果的な反論手法
裁判で相手の嘘に対応する際には、裁判官がどのような心証を形成するかを意識した反論を行うことが重要です。
裁判官は当事者の主張と証拠だけを元に判断するため、どのように真実を伝えるかが結果を大きく左右します。
効果的な反論の方法としては、まず客観的で動かしがたい事実から提示することです。
「客観的にはこのような証拠があります」と冷静に証拠を示すことで「この当事者は信頼できる」という印象を与えられます。
相手の矛盾を指摘する際も攻撃的にならず「時系列を整理すると、このような矛盾が生じています」と論理的に説明することが重要です。
さらに、相手の嘘を明らかにした後には「では真実はこうです」と具体的に示すことで、裁判官にとって理解しやすい形で事実を伝えられます。
裁判で嘘をつくリスクとは

裁判で嘘をつくことの本当の代償は、偽証罪や過料といった直接的な刑事処罰だけではありません。

たとえばどんな代償があるのでしょうか?
 弁護士
弁護士最も深刻な影響は裁判官の心証悪化であり、これが最終的な敗訴につながる可能性があります。
裁判官は「誰が誠実か」で全体を見ている
裁判で嘘をつく最大のリスクは、偽証罪に問われることではありません。
裁判官の心証が悪化し、それが判決に決定的な影響を与えることです。
裁判官は「誰が誠実か」という視点で当事者全体を見ています。
一度でも虚偽が明らかになると、その当事者に対する信頼は大きく損なわれてしまうのです。
民事裁判では、事実認定において裁判官の心証が大きな役割を果たします。
客観的証拠だけでは判断できない部分について、裁判官はどちらの当事者がより信頼できるかを総合的に判断します。
そのため、虚偽陳述が発覚した当事者は、他の主張についても疑念を持たれ、本来であれば認められるはずの正当な主張まで退けられる危険性があるのです。
一旦悪化した心証は回復が困難で、その後の訴訟にも長期間にわたって不利な影響を及ぼします。
結果として、法的には正当な権利を持っていても、敗訴する可能性が高くなります。
虚偽が発覚すると主張全体の信頼性が下がる
一つの嘘が発覚すると、その当事者の主張全体に対する信頼性が連鎖的に低下していきます。
これは「小さな嘘が大きな不利を生む」典型的な状況であり、些細な虚偽であっても訴訟全体に深刻な影響を与える可能性があります。
裁判官の心理として、一度嘘をついた当事者に対しては「他の部分でも嘘をついているのではないか」という疑念を抱くのが自然です。
そのため、虚偽が発覚した当事者の証拠や主張は、より厳しい目で精査されることになります。
逆に、誠実な対応を続けている当事者に対しては、多少の証拠不足があっても好意的に解釈されることもあります。
 弁護士
弁護士この傾向は、特に証拠が不十分な争点で特に顕著です。
客観的な資料だけでは判断できない事実については、裁判官は当事者の信頼性を基準に心証を形成します。
つまり、虚偽陳述をした当事者は、決定的に不利な立場に置かれることになります。
証拠隠滅や偽造行為は別の罪に発展することも
裁判での嘘が問題となるのは、偽証罪だけではありません。
嘘を隠蔽するために証拠を隠滅したり偽造したりする行為は、犯人隠避罪や証拠隠滅罪といった別の重大な犯罪に発展する恐れがあります。
これらの犯罪は偽証罪よりも処罰される可能性が高く、実際に起訴されるケースも少なくありません。
証拠隠滅罪は、自分や他人の刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造した場合に成立し、2年以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。
また、犯人隠避罪は他人の犯罪後にその人が刑事処分を受けることを免れさせる目的で援助した場合に成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
民事裁判での虚偽の陳述がきっかけとなり、こうした犯罪に発展するケースも少なくありません。
民事訴訟法209条による過料制裁の実際の運用
民事裁判の当事者が虚偽陳述を行った場合、民事訴訟法209条により10万円以下の過料が科される可能性があります。
かつてはほとんど適用例がなく形骸化していると考えられていましたが、近年では、悪質な場合は実際に適用されるケースも増えてきました。
過料は刑事罰ではなく行政上の制裁であり、前科にはならないものの、裁判所による公的な制裁として記録に残ります。
また、過料の決定に対しては即時抗告が可能ですが、決定の告知から1週間以内という短期間で対応しなければなりません。
重要なのは、過料制裁の対象となるのは宣誓をした当事者の虚偽陳述に限られることです。
しかし、ほとんどの民事裁判では当事者尋問の際に宣誓が行われるため、ほぼすべての当事者が過料制裁の対象となり得ます。
この制裁は裁判官の裁量ではありますが、虚偽の程度や悪質性が高い場合は適用される可能性が十分にあります。
弁護士費用や訴訟費用の負担増加リスク
虚偽の陳述により訴訟が長期化したり複雑化したりした場合、結果的に弁護士費用や訴訟費用が大幅に増加する恐れがあります。
特に、相手方に損害を与えた場合は、その損害について賠償責任を問われる可能性もあります。
民事訴訟では、敗訴した側が訴訟費用を負担するのが原則です。
ただし、虚偽の陳述により不当に訴訟を長引かせた当事者については、勝訴した場合でも一部の費用負担を命じられる可能性があります。
実際に、名古屋地裁の事例でも、通常であれば認容額に応じて按分される訴訟費用が、虚偽の陳述をした被告に全額負担させる判断が示されました。
また、虚偽の陳述が原因で証拠調べが追加で必要になった場合や、相手方が追加の反証を準備するために要した費用についても、損害賠償の対象となることがあります。
このように、虚偽の陳述をすると、経済的な負担という形でも重い代償を課される可能性があるのです。
【FAQ】裁判における嘘・偽証罪についてよくある質問

裁判で、相手に嘘をつかれた経験を持つ方から寄せられる質問をまとめました。
多くの方が抱く疑問に、法的根拠をもとに回答します。
陳述書の嘘は偽証罪になりますか?
 弁護士
弁護士陳述書に虚偽の内容を記載しても、基本的には偽証罪には該当しません。
なぜなら偽証罪が成立するには「法律による宣誓」が必要だからです。
当事者が提出する場合でも、第三者が提出する場合でも、陳述書の提出時に宣誓はしません。
ただし、民事裁判の当事者が宣誓後に虚偽の陳述を行った場合は、民事訴訟法209条により10万円以下の過料が科される可能性があります。
相手を偽証罪で訴えたいのですが、可能ですか?
 弁護士
弁護士相手方を偽証罪で訴える場合は、警察や検察に告発することになります。
しかしながら、民事裁判の偽証については、過去15年を振り返っても公表された確証あるケースはほとんどない状況です。
捜査機関も民事の偽証には関心が薄く、よほど悪質でない限り起訴されることはありません。
嘘を見破ってくれるのは裁判所?それとも自分で立証すべき?
 弁護士
弁護士民事裁判では、当事者が自分で相手の嘘を立証する必要があります。
裁判官は証拠を自ら収集することが禁じられており、当事者が提出した証拠のみに基づいて判断します。
そのため、相手の虚偽を証明する客観的証拠の収集は当事者の責任です。
ただし、相手の陳述に一貫性がない場合や、客観的証拠との矛盾がある場合は、信用性を疑われることはありえます。
嘘をついた相手が途中で自白したらどうなる?
 弁護士
弁護士偽証罪では、判決確定前に自白した場合、刑法170条により刑の減軽や免除が可能とされています。
この自白は、虚偽陳述をしたことを告白するだけでよく、真実を述べることまでは要求されません。
ただし、民事裁判では偽証罪自体が成立しにくいため、実際にはこの規定が適用される機会は極めて限定的です。
当事者本人の嘘と証人の嘘、どちらが重い?
 弁護士
弁護士法的には、証人の嘘のほうが、重い処罰を受けることになります。
証人が偽証した場合は偽証罪(3か月以上10年以下の懲役)の対象となりますが、当事者本人の嘘は偽証罪にはならず、民事事件では最大10万円の過料にとどまります。
ただし、実際の訴訟への影響は当事者本人の嘘のほうが大きく、裁判官の心証に決定的な悪影響を与える可能性があるので注意が必要です。
記憶違いと嘘の区別はどうやってつけるの?
 弁護士
弁護士法的には「証人の記憶に反する陳述」が偽証となるため、記憶違いは偽証罪にはなりません。
ただし、実際に本人の記憶が真実と一致していないことを証明することは、極めて困難です。
本人に「そのよう思っていた」と言われれば立証は不可能に近く、この証明の困難さが偽証罪の成立を阻む大きな要因となっています。
証人が「記憶にない」ばかり言う場合どうすればよい?
本当に記憶がないなら法的には問題ありませんが、実際は覚えているのに「記憶にない」と嘘をついている場合には偽証罪になる可能性がありますが、立証は困難です。
なお、あまりに頻繁に使うと裁判官の印象が悪くなるリスクがあります。
 弁護士
弁護士対策としては、客観的証拠で記憶を呼び起こすような質問をしたり、矛盾を指摘したりすることが有効です。
民事と刑事で偽証罪の扱いは違うの?
基本的な偽証罪の要件は同じですが、実際の処罰の可能性は大きく異なります。
刑事事件では詳細な捜査が行われ、供述調書なども存在するため偽証の立証が比較的容易です。
一方、民事では捜査が行われることは滅多になく、証人の内心を証明することが困難です。
 弁護士
弁護士なお、国会証人喚問では政治的な背景もあり、また異なる扱いとなります。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
民事裁判で相手が嘘をついたとしても、偽証罪で処罰を求めることは極めて困難です。
当事者本人に偽証罪は成立せず、証人の偽証についても「記憶に反する証言」であることを立証するのが難しく、実際に処罰されるケースはほとんどありません。
重要なのは、相手の嘘に感情的に反応するのではなく、客観的証拠を収集して論理的に反証することです。
裁判官は「誰が誠実か」で当事者全体を評価するため、冷静で事実に基づいた対応を心がけることが、有利な結果につながりやすくなります。
段外証拠の活用や矛盾点の指摘など、計画的にアプローチすることで相手の信用性を下げることが有効です。
嘘の最大の代償は刑事罰ではなく、心証悪化であることを理解し、終始誠実な姿勢で訴訟に臨むことが重要です。

弁護士 黒田悦男
大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981
事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。
また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










