裁判で勝訴したのに相手がお金を支払ってくれない…
判決書を見せても『払えない』の一点張り…
せっかく勝ったのに泣き寝入りするしかないの?
裁判に勝っても、相手が任意に支払いに応じなければ、債権を回収することはできません。
そんなとき、多くの方が不安に思うことそれは
➊強制執行は自分でもできるの?
➋どのような手続きが必要なの?
強制執行は個人でも申し立てることが可能です。
ただし、相手の財産を特定する必要があり、給料差し押さえ、預金差し押さえ、不動産差し押さえなど、財産の種類によって手続きが異なります。また、費用対効果を考慮して慎重に進める必要があります。
本記事では、強制執行を自分で行うための具体的な手順、必要書類、費用、そして成功率を高めるためのポイントについて、詳しく解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
判決後に相手が支払ってくれない場合の対応方法

裁判で勝訴したり、和解や調停が成立したりしても、相手が支払いに応じないケースは少なくありません。
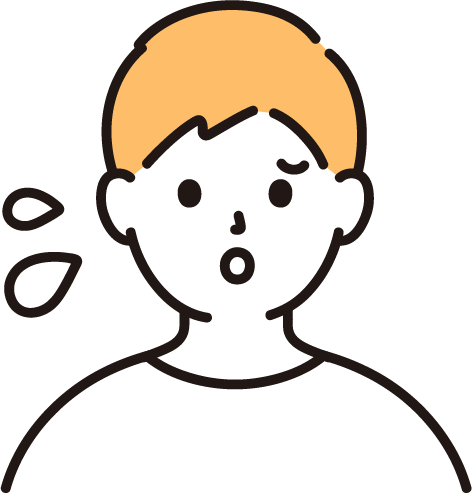
せっかく裁判で勝訴しても支払いに応じないなんて…。
何か手立てはありませんか?
 弁護士
弁護士このような場合、強制執行という手続きを取ることで、債権を回収できることがあります。
強制執行とは?
債務名義とは、以下のような公的文書を指します。
- 確定判決
- 和解調書
- 調停調書
- 執行認諾文言付公正証書
注意しておきたいのは、自力で相手の財産を取り立てることは違法となり、場合によっては刑事罰の対象となる点です。
強制執行は、必ず裁判所を通じて行わなければなりません。
強制執行の対象となる財産は主に以下の3つです。
- 預貯金や給与などの債権
- 土地・建物などの不動産
- 動産(車両、貴金属など)
なお、給与債権の場合、手取り額の4分の1まで(養育費の場合は2分の1まで)しか差し押さえできないため注意しましょう。
強制執行を行うために必要な条件
強制執行を行うためには、以下の5つの条件が必要です。
- 債務名義を保持していること
- 送達証明書を保持していること
- 執行文を保持していること(一部例外あり)
- 相手の住所が特定できていること
- 差し押さえ可能な財産が特定できていること
これらの条件がそろっていない場合、強制執行を申し立てることはできません。
特に、相手の財産状況の事前調査は重要です。
 弁護士
弁護士費用対効果の観点から、強制執行の実効性を見極める必要があります。
相手に財産がない場合、回収は可能?不安を解消するポイント

 弁護士
弁護士債務者が「財産がない」と主張する場合でも、実際には給与収入や預金などの差し押さえ可能な財産を持っているケースは少なくありません。

債権回収を諦める前に、適切な調査をして対策を検討する必要がある、ということですね!
財産がない相手からの回収はどこまで可能か?
一見すると財産がないように見える場合でも、以下のような財産から債権を回収できる可能性があります。
たとえば、給与収入がある場合、手取り額の4分の1までの差し押さえが可能です(養育費債権の場合は2分の1まで)。
例手取り月収20万円の場合、毎月5万円まで回収可能
預金債権についても、残高が少額であっても差し押さえ可能です。
ただし、生活保護費や年金など、法律で差し押さえが禁止されている財産もあるので注意しましょう。
なお、将来的な回収可能性も考慮すべきであるといえます。
判決などの債務名義の時効は10年間あり、この間に債務者の資力が回復する可能性は十分に考えられるからです。
 弁護士
弁護士現時点で資力不足のため回収不可能だという場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。
財産調査で利用できる手続きの種類
財産調査は、強制執行の成否を左右する重要な手続きです。
市区町村や日本年金機構などから債務者の就労情報を得られます。
預金調査については弁護士会照会制度を活用することで、金融機関から口座情報を取得できる可能性があります。
2020年4月からは民事執行法の改正により、第三者からの情報取得制度も整備され、より広範な財産調査ができるようになりました。
また、裁判所を通じた「財産開示手続」も利用可能です。
財産開示手続きの申立てを行った場合、債務者は裁判所に出頭し、決められた期日までに財産目録を提出する必要があります。
 弁護士
弁護士なお、虚偽の申告には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が設けられています。
第三者からの情報取得制度や財産開示手続を利用するには、事前に財産調査を行っていることが条件です。
強制執行で差し押さえられる財産の種類

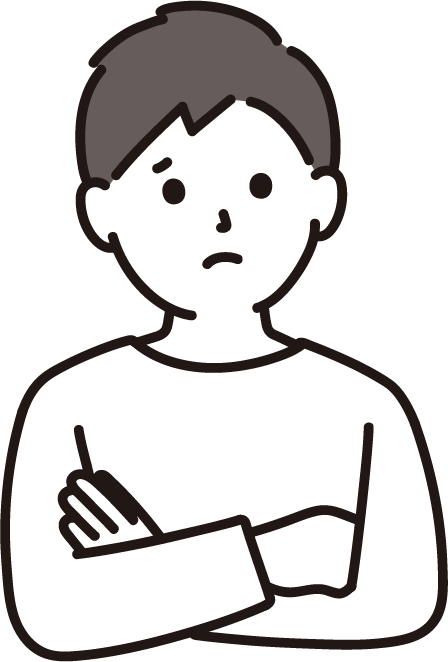
実際に強制執行をしようと思うのですが、どのような財産を差し押さえるのがいいのでしょうか?
 弁護士
弁護士強制執行で差し押さえられる財産は、「債権」「不動産」「動産」の3種類があり、それぞれに特徴があります。
債権の差し押さえ
債権の差押えは、最も一般的で効果的な強制執行の方法です。
給与債権の差押えでは、定期的な収入から継続的な回収が可能です。
給与の手取り額の4分の1(養育費債権の場合は2分の1)までという制限はありますが、債務者が定職についている限り、安定した回収が期待できます。
預金債権の差押えは、口座残高全額を一度に差し押さえられます。
ただし、差押え時点の残高が上限となるため、給与振込日直後などのタイミングを見計らって行うことが重要です。
また、複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれに対して手続きすれば、回収の確実性が高まるでしょう。
退職金債権では、手取り額の4分の1(養育費債権の場合は2分の1)までを差押えられます。
一時金として高額な回収が期待できますが、債務者の退職のタイミングを把握する必要があります。
他の強制執行と比べて迅速な手続きが可能ではありますが、次のような場合には時間を要することがありますので注意しましょう。
- 債務者の居所不明による送達の遅延
- 第三債務者(勤務先など)からの陳述催告に対する回答待ち
- 複数債権者による配当手続きが必要な場合
不動産の差し押さえ
不動産執行は、高額な回収が期待できる反面、手続きが複雑で費用も高額となります。
土地や建物などの差押えでは、まず権利関係を詳細に調査する必要があり、特に以下の点に注意が必要です。
- 抵当権の設定状況
先順位の抵当権がある場合、実質的な回収額が大きく減少する可能性があります。 - 不動産評価額
不動産の実際の価値を把握し、執行費用との見合いを検討する必要があります。 - 占有状況
賃借人がいる場合、明け渡しまでに時間と費用がかかる可能性があります。 - 予納金
裁判所によって異なりますが数十万円(東京地裁の場合は80万円以上)が必要となり、場合によっては回収できない可能性もあります。
また、不動産執行は手続きの複雑さから、執行までに長期間を要することが一般的で、順調に手続きを進めたとしても1年程度かかることがあります。
物件の状況や市場性によっては、さらに長期化することもありますので注意しましょう。
動産の差し押さえ
動産執行は、換価価値の高い特定の動産がある場合に効果的です。
自動車や貴金属、美術品などが主な対象となります。
保管費用は動産の種類により変動し、競売等による換価までに時間がかかる場合があります。
なお、現金については債務者の最低限の生活を保障する規定が民事執行法で定められており、66万円を超える部分のみ、差押え可能です。
強制執行を自分で行う方法

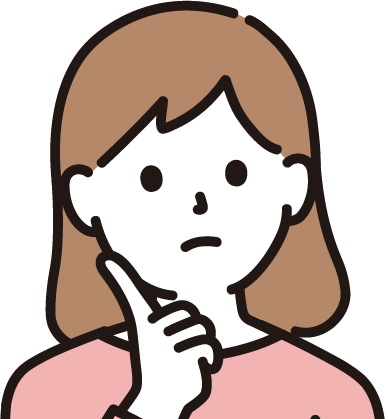
弁護士等に依頼せず、自分のみで強制執行を行うことは可能でしょうか?
 弁護士
弁護士強制執行は法的な専門知識が必要ですが、必要書類と手順を理解すれば自分自身のみでも実行可能です。
ただし、手続きの誤りは回収の遅延や余計な費用負担を招くため、一つずつ確実に進めていくようにしましょう。
強制執行の申立てに必要な書類
強制執行の申立てには最低限以下の書類が必要です。
管轄裁判所のホームページで必要書類を確認することもできます。
| 必要な書類 | 書類の概要 |
| 債務名義の正本 | 公正証書や調停調書など、強制執行の根拠となる文書。 紛失した場合は作成した公証役場や裁判所で再発行が可能。 |
| 送達証明書 | 相手に債務名義が確実に届いたことを証明する書類。 |
| 執行文 | 強制執行が可能な状態であることを証明する文書。 |
| 申立書一式 | 債権差押命令申立書 差押えの対象や範囲を特定する基本書類。 |
| 当事者目録 債権者と債務者について記した記録。給与なら勤務先の正確な情報も記載。 | |
| 請求債権目録 回収したい債権額の詳細を記載。 | |
| 差押債権目録 差し押さえる財産の具体的内容を記載。 | |
| 資格証明書 | 債権者や債務者、第三者債務者が法人の場合、登記事項証明書又は代表者事項証明書が必要。 |
給料差し押さえ・預金差し押さえ・不動産差し押さえの手順
ここでは、主な差し押さえの手順について、詳しく紹介します。
市区町村や年金機構への「第三者からの情報取得手続」で、勤務先情報を入手。
相手に情報開示を求める財産開示手続も利用可。
陳述催告の申立てを忘れずにチェック。
これにより勤務先から給与債権の具体的な情報を得られます。
書類審査を経て、通常1週間程度で発令されます。
送達により、第三債務者である勤務先は、債権者への支払義務を負います。
給与支払日に、手取り額の4分の1まで回収できます。
回収時には「取立届」を提出します。
預金差し押さえの手順は以下のとおりです。
弁護士会照会や情報取得手続を利用し、取引口座を特定します。
過去の取引記録も重要な手がかりとなります。
支店名・所在地を正確に特定し、最新の資格証明書を添付します。
通常1週間程度で発令されます。
送達と同時に口座が凍結され、残高が報告されます。
債務者への送達から1週間後に取立可能となります。
不動産差し押さえの手順は以下のとおりです。
法務局で登記事項証明書を取得し、所有権と抵当権の有無を確認。
市区町村で固定資産評価証明書を取得し、不動産の価値を把握します。
数十万円の予納金と必要書類を提出します。
裁判所から法務局へ嘱託され、債権額の0.4%の登録免許税が必要です。
執行官が現地を調査し、最低売却価格を決定。入札により売却します。
抵当権者などの優先順位に従って、売却代金から配当されます。
強制執行のリスクを減らすための7つのポイント
強制執行はさまざまなリスクを伴います。
必ずしも全額回収できるとは限りませんし、強制執行によって債務者が生活困窮に陥る可能性もあるのです。
このようなリスクを減らすためのポイントを、7つ紹介します。
徹底した事前調査を行う
強制執行する際は、徹底的に事前調査を行いましょう。
財産調査は、強制執行の成否を左右する重要な要素です。
法務局での不動産登記確認に加え、第三者からの情報取得手続を活用することで、より正確な財産状況を把握できます。
 弁護士
弁護士市区町村や年金機構からの情報収集も有効です。
必要に応じて、裁判所での財産開示手続も活用しましょう。
差押対象を戦略的に選択する
給与差押えは、毎月の安定的な回収が期待できます。
一方で、債務者側は、給与が差し押さえられることで生活が苦しくなり、場合によっては転職を余儀なくされる可能性もあるのです。
また、預金差押えは即時回収が可能ですが、残高が不確実という特徴があります。
不動産は換価価値が高い反面、予納金が数十万円必要です。
 弁護士
弁護士これらの特徴を理解した上で、状況に応じた最適な選択をすることが重要です。
書類の完全な準備を心がける
債務名義の正本・送達証明書・執行文といった基本書類の準備は必須です。
書類の不備は手続きの遅延や却下につながるため、チェックリストを作成して漏れがないよう確認しましょう。
費用対効果を冷静に判断する
不動産執行では予納金数十万円、動産執行でも数万円の費用が発生し、それに加えて申立手数料4,000円、郵便切手代3,000~5,000円がかかってきます。
必要な費用と回収見込額を比較し、実行の是非を判断しましょう。
 弁護士
弁護士特に不動産執行では、抵当権の有無や優先順位も考慮に入れ、判断するべきです。
法定制限を正確に理解する
給与は原則として手取り額の4分の1まで、養育費債権は2分の1までという制限があります。
また、生活保護費や年金などの差押禁止財産、生活に必要な最低限度の動産なども差押えができません。
これらの制限を理解せずに手続きを進めると、無駄な費用が発生する可能性があります。
第三債務者との良好な関係を維持する
勤務先や金融機関など第三債務者への対応は、スムーズな強制執行の進行に大きく影響します。
陳述催告を活用して必要な情報を得つつ、手続きの説明は丁寧に行い、過度な負担をかけないよう配慮することが重要です。
 弁護士
弁護士特に給与差押えの場合、勤務先との関係悪化は債務者の退職につながりかねません。
代替手段も視野に入れる
強制執行だけでなく、分割払いの提案や任意売却の検討など、状況に応じた柔軟な対応も検討しましょう。
場合によっては、債務整理などの手続きを視野に入れることで、より確実な債権回収が期待できることもあります。
 弁護士
弁護士特に債務者に支払意思がある場合は、話し合いによる解決も検討してみましょう。
強制執行を自力で行う場合と弁護士に依頼する場合の比較

 弁護士
弁護士強制執行は、専門知識があれば自力でも実行できますが、費用と時間、リスクを考慮すると、弁護士へ依頼した方がよいケースもあります。

自分で手続きするメリットデメリットと、弁護士へ依頼するメリットデメリットを比較するべきですね。
自力で強制執行を行う場合の費用目安
自力で強制執行を行う場合にかかる、費用目安について解説します。
例えば100万円の債権回収を行う場合で見てみましょう。
| 強制執行の種類 | 必要な費用 |
| 債権執行(給与・預金)の場合 | 申立手数料:4,000円(収入印紙) 郵便切手代:3,000~5,000円 裁判所からの通知や送達のための費用 資格証明書取得費用:1通1,000円程度 おおよそ1万円前後の費用 |
| 不動産執行の場合 | 申立手数料:4,000円(収入印紙) 予納金:数十万円 不動産の評価や競売手続きにかかる費用 登録免許税(債権額の0.4%差押登記にかかる税金):4000円 予納金次第ではあるが100万円近くかかることも。 |
| 動産執行の場合 | 申立手数料:4,000円(収入印紙) 予納金:3~5万円 執行官の現地調査等にかかる費用 解錠技術者費用:1~5万円程度 必要に応じて専門家に依頼する費用 おおよそ5~15万円程度 |
弁護士に依頼する場合の費用目安
弁護士費用は、事案の難易度や債権額によって料率が変わります。
以下に具体例を紹介します。
| 【100万円の債権回収の場合】 着手金:4万円~8万円(100万円×4~8%) 報酬金:4万円~16万円(100万円×4~16%) 合計:8万円~24万円程度 |
| 【500万円の債権回収の場合】 着手金:12.5万円~25万円(500万円×2.5~5%) 報酬金:12.5万円~50万円(500万円×2.5~10%) 合計:25万円~75万円程度 |
| 【5,000万円の債権回収の場合】 着手金:75万円~150万円(5,000万円×1.5~3%) 報酬金:75万円~300万円(5,000万円×1.5~6%) 合計:150万円~450万円程度 |
これらの費用に加え、必要に応じて日当や交通費がかかることもあります。
前述の強制執行費用も別途必要です。
強制執行における弁護士費用は決して安くありませんが、もちろんメリットもあります。
専門的な知識と経験に基づいた財産調査を行うことができますし、勤務先などの第三債務者と適切にコミュニケーションをとることも可能です。
また、最適な差押対象の選択や、強制執行以外の代替手段を含めた総合的なアドバイスも受けることができるため、より自分と相手の状況にマッチした選択を行うことができるでしょう。
さらに、手続きの誤りによるリスクを最小限に抑えることができます。
 弁護士
弁護士強制執行は、専門的な知識が必要となるため、相談のみでも弁護士へ依頼する価値はあるといえるでしょう。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
強制執行を成功させるには、事前の準備と財産調査が不可欠です。
自力での手続きと弁護士に依頼する場合の違いを理解し、費用対効果を考慮して最適な方法を選びましょう。
また、相手の状況が変わることもあるため、継続的に財産調査を行い、手続きを見直すことが回収成功の鍵となります。
強制執行の方法で迷った際は、弁護士の無料相談なども活用して、リスクを最小限に抑えながら進めていきましょう。

水島昂 弁護士
東京弁護士会所属
弁護士法人小林綜合法律事務所
東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館2階
電話 03-6212-5201
正確な法律論を提示するだけでなく、柔軟な発想でご相談者の方々の立場・状況に沿った解決策を提案できるよう、心がけております。
事件の大小にかかわらず、どんなことでもお気軽にご相談下さい。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










