
「毎月の給料のほとんどが推し活に消えていく」
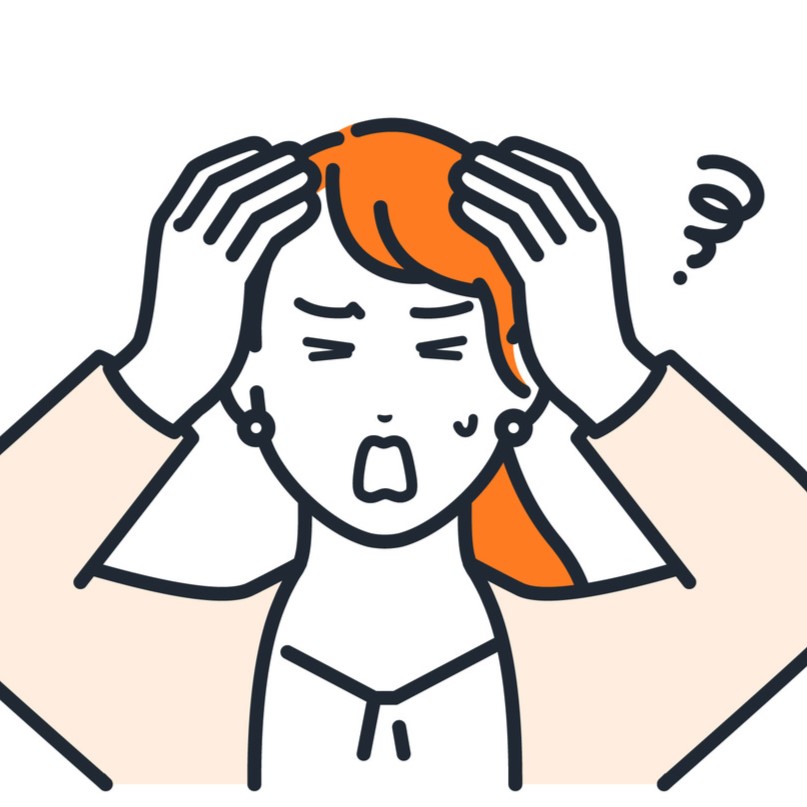
「ライブのために借りたお金がいつの間にか膨れ上がってしまった」
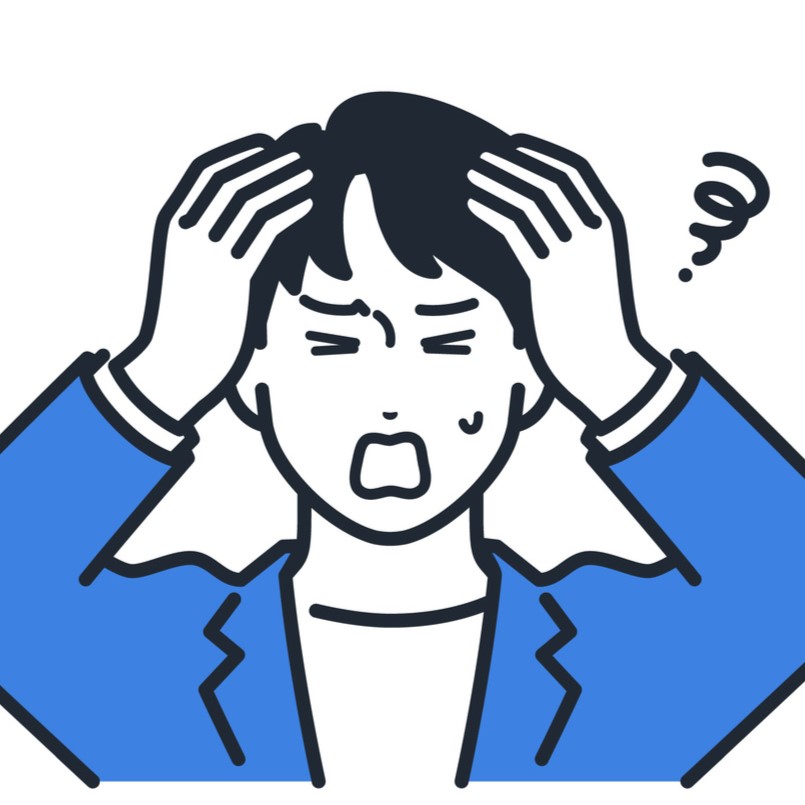
「グッズ代のためにカードを何枚も作ってしまった」
このようなお悩みはありませんか?
推し活による金銭的な悩みを抱える人は、決して珍しくありません。
好きなアイドルやアーティスト、VTuberを応援する気持ちが強いあまり、いつの間にか借金が膨らみ、最悪の場合は自己破産に至るケースも増加しています。
推し活による破産は年々増加傾向にあり、特に若年層を中心に社会問題化しつつあります。
コンサートやグッズなど少額の支出が積み重なり、またSNSでの比較文化や「推せるときに推せ」という価値観も相まって、気づかないうちに破産リスクが高まっているのです。
本記事では、推し活による借金問題の実例から、なぜ「借金の沼」に陥りやすいのか、そして問題を回避する方法についても、弁護士の視点から詳しく解説します。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
推し活で破産することがある

趣味であるはずの推し活が、いつの間にか経済的な破綻へとつながっていく「推し活破産」の現実。
実は、年々増加傾向にあるといいます。
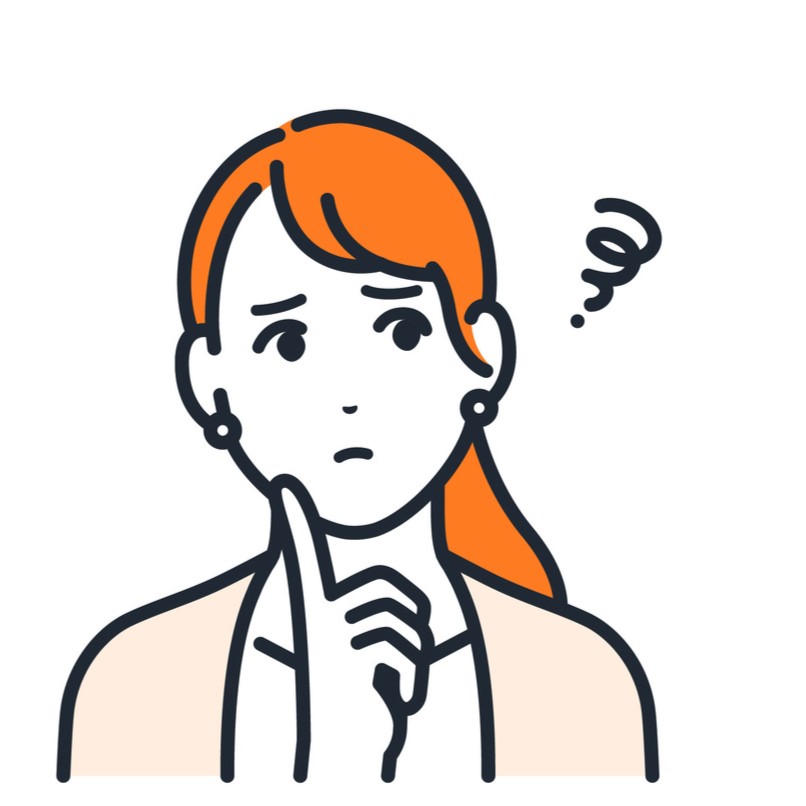
長年推し活をしていると、だんだんお金の使い方が荒くなっていくのを自覚しています…。
 弁護士
弁護士ここでは実際の事例から、推し活が招く金銭トラブルの実態と対策を解説します。
推し活で自己破産した人の事例
推し活による破産は、決して珍しいことではありません。
たとえば、就職して3年目の20代女性が、学生時代から好きになったアイドルグループの推し活にのめり込み、自己破産に至った事例もあります。
彼女は社会人になってからCDやグッズ、雑誌を「観賞用と保存用」として2つずつ購入するようになり、全国のライブにも遠征していました。
遠征費だけで10万円を超えるケースも珍しくなく、足りない部分はカードローンやクレジットカードのキャッシングで補填。
その結果、借金額はボーナスでも返せない規模に膨れ上がり、自己破産するに至りました。
また、推しを追って全国ツアー約20カ所すべてに参加していたファンの事例もあります。
当初は「ちょっとライブに行く程度」だったものが、次第に全通(すべての公演に参加)するほどのめり込み、アルバイト収入のほとんどを推し活に使っていました。
全国ツアーを全通する費用は、約40万円。
推し活の費用を工面するため、地方ライブの際に外食を避けてコンビニの食品で済ませ、徒歩で長時間移動するなど、極端な節約生活を送っていたといいます。
さらに衝撃的なのは、推し活歴20年以上のアイドルファンが、総額3000万円以上を投じたという事例です。
「1回のライブとチェキで最低1万円はかかり、月に20回の現場(ライブ)があれば20万円になる」と語り、自身の収入だけでは足りず借金に頼ることもあったのだそうです。
家計管理は家族に任せ、生活費を差し引いたお金だけが、手元に入ってくる状態でした。
推し活破産が急増している社会背景
近年、推し活による破産事例が増加している背景には、さまざまな社会的・経済的要因が存在します。
たとえば、最近は身近で活動する地下アイドルや、インターネット上のVTuberなど、ファンとの距離が近いジャンルが人気を集めています。
応援しているファンの人数が大手芸能事務所所属のタレントに比べて小規模であることから、「自分が頑張って応援することでこの子を押し上げているのだ」と実感しやすい反面、無理をして応援してしまう傾向があるようです。
また、ファンの間では「今しかない瞬間を大切にする」という考え方が広まっていることも原因とされています。
このような価値観は、今応援しなければ後悔するという強迫観念を生み出し、計画的な貯蓄や予算管理よりも「今」の満足感を優先させる消費行動につながっています。
ライブ・グッズ販売で消費が多様化
推し活の消費パターンは近年多様化しており、ファン心理を巧みに刺激する販売戦略も増えています。
たとえば、アニメグッズでは「ランダム商法」と呼ばれる、中身が見えない状態で販売される方式が普及しています。
これは、目当ての推しグッズを手に入れるために何個も購入してしまうという消費行動です。
また、CD購入特典としての握手券や、限られた枚数しか販売されない限定グッズなど、希少性や特別感を強調した商品展開も増加しています。
こうした販売戦略が、過剰消費を促進する一因になっているのです。
さらに、ライブやイベントが全国展開している場合、可能な限りツアーを追いかけていくファンは、当然推し活金額が増えていきます。
宿泊費・交通費などの遠征費を含めると一回の出費が数万円から10万円を超えることも珍しくなく、複数の公演に参加するファンにとっては大きな経済的負担となっています。
金融サービスの利用ハードルが低下
推し活破産が増加している背景には、金融サービスへのアクセスが容易になったことも大きく影響しています。
ある自己破産事例では、カードローンの返済に加えてクレジットカードのキャッシングも利用していた状況が報告されており、複数の借入先から資金を得て返済を繰り返す、いわゆる「自転車操業」の状態に陥っていました。
特に近年は、スマートフォンアプリからの申し込みや24時間審査など、借入のハードルが大幅に下がっています。
また、クレジットカードのリボ払いは「毎月の支払額が一定」という分かりやすさから利用者が増加していますが、高金利による総返済額の増加というリスクが十分に理解されていないケースも少なくありません。
また、成人年齢の引き下げにより、18歳から自分の意思でカードローンなどを利用できるようになったことも影響しています。
金融リテラシー教育が十分でない若年層が、推し活の熱中から容易に借金を重ねてしまうリスクが高くなっているのです。
簡単に借りられるため、場合によっては返済自体を忘れてしまうケースもままあります。
推し活で破産した際の影響
推し活で自己破産に至った場合、単に借金が帳消しになるだけでは済まず、日常生活においても大きな支障が生じます。
まず、破産すると「ブラックリスト」に掲載されます。
ブラックリストに載ると、新規の借入やクレジットカードの契約ができなくなります。
また、スマートフォン端末の分割払いでの購入もできなくなるなど、日常生活に様々な制約が生じます。
さらに問題となるのは、推し活による過度な浪費が、自己破産における「免責不許可事由」に該当する可能性がある点です。
たとえば、推し活費用の捻出のために副業に手を出したり、チケットを安価に転売したりした場合、不適切な金銭行為とみなされ債務が免責されない可能性があります。
すなわち、自己破産の手続きを行っても借金が残ってしまう恐れがあるのです。
また、差し押さえによって職場に情報が伝わることで、人間関係や信頼関係に影響を及ぼす可能性もあるのです。
推し活が「借金の沼」になりやすい理由

推し活関連の出費は一見すると少額に思えるかもしれません。
しかし、時間の経過とともに積み重なる支出は、気づいたときには手に負えない金額になっていることが少なくありません。
 弁護士
弁護士推し活で短期的な満足感は得られる一方で、長期間にわたる出費は、経済的に困難な状況を招いてしまう恐れがあります。
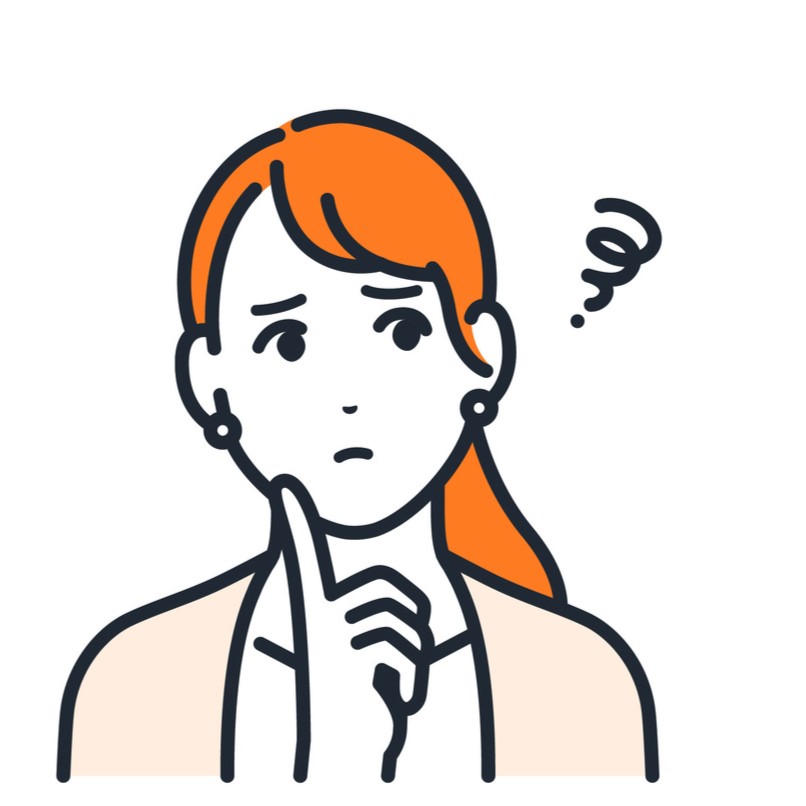
確かに、一回一回はそこまで負担はないですが、回数が増えると出費に苦しむことがあります…。
お金が出ていく仕組みが見えづらいから
推し活で発生する費用は一つひとつが少額に見えるため、その合計に気づきにくい特徴があります。
ファンクラブ加入費、チケット代、遠征費(交通費・宿泊費)、グッズ購入費など、様々な場所でお金が出ていきます。
これらの支出は「推し活」という一つのカテゴリーでまとめられるため、実際にどれだけのお金が出ていっているのか把握しづらいのが現状です。
また、こうした出費は、積み重なると予想以上の総額になります。
また、支出の頻度が不規則であることも問題を複雑にします。
定期的な固定費と違い、イベントの開催時期やグッズの発売タイミングは予測が難しいため、計画的な予算管理がしづらくなります。
結果として、「気づいたら思った以上にお金を使っていた」という状況に陥りやすいのです。
推し活の具体的な出費項目を見ていくと、その多様さと積み重なりが浮き彫りになります。
まず基本的な費用として、CDやDVDの購入費があります。
推しと握手するチケット入手のために同じCDを複数枚購入するという行動が一般化しています。
また、推しグッズを「観賞用と保存用」として2セット購入する習慣もあるようです。
これは出費を単純に2倍にする行動であり、経済的負担を大きくさせます。
限定グッズは「今買わなければ二度と手に入らない」という焦りも生み、計画外の出費につながりやすくなります。
さらには、イベント参加費も見逃せない出費です。
全国ツアーを追いかけるファンの場合、1公演あたりのチケット代は数千円から1万円程度でも、20カ所以上回ると総額は膨大になります。
中には全国ツアーを全通するため、約40万円を支払ったファンも。
さらに遠方でのイベントに参加する際には遠征費(交通費、宿泊費)もかかります。
他のファンと比較してしまうから
推し活における過剰消費の大きな要因の一つが、他のファンとの比較から生まれる心理的圧力です。
特に「同担」(同じ人物を推している仲間)同士の競争意識や、SNS上での「推し活自慢」の文化は、過剰な出費を助長する環境を作り出しています。
特に女性ファンの間では「同担拒否」と呼ばれる現象が存在します。
これは同じ推しを持つファン同士が交流を拒否する行為で、一種の嫉妬や排他的な所有欲から生まれるものです。
この背景には、「自分と推しとの関係は特別であるべき」という感情があり、他のファンよりも「推しとの関係性が深い」ことを証明したいという欲求につながります。
このような競争意識は、ライブの参加回数やグッズの収集量、推しとの交流機会など、目に見える形で「努力」や「貢献度」を示そうとする行動につながります。
「自分は本気のファンだ」という自己認識や周囲からの評価を得るために、経済的に無理をしてでも現場に足を運び、グッズを購入する心理が働くのです。
同担拒否・ファン内マウント文化
ファン文化の研究者や法律専門家が指摘するように、推し活界隈では「マウント文化」が根付いています。
特に「同担拒否」と並行して、「イベントにたくさん行った人や、たくさん課金した人が偉い」という価値観が形成されていることが多くあります。
たとえば、「会場の後ろのほうでポツンと観ていると周囲から不審がられる」と周囲の目を気にして「ファンとしての立場を守るため」に経済的な無理を重ねる心理が働くことも珍しくありません。
SNSでの「課金自慢」
SNSの普及は推し活文化に大きな影響を与え、「課金自慢」という現象を生み出しました。
たとえば、ファンがSNS上で推しグッズのコレクションやライブ参加回数、推しとの2ショット写真など「成果」を投稿し合う文化があります。
これらの投稿を目にした他のファンは、自分だけが取り残されているような焦りや劣等感を抱きやすくなります。
「みんなが行っている」「自分だけグッズを持っていない」という心理的圧力が生まれ、本来なら経済的に無理な出費であっても「この一回だけは特別」と例外を作り出してしまうのです。
特に問題なのは、SNS上では他者の「華やかな部分」だけが切り取られて表示される点です。
実際には無理して参加していたり、借金してまでグッズを購入していたりしても、影となる部分の行動は見えません。
見えるのは「楽しそうな推し活の成果」だけであり、それが新たな参加者を巻き込み、過剰消費のサイクルを拡大していく構造があるのです。
“自転車操業”が常態化しやすいから
推し活に熱中するうちに、単純な収入だけでは賄いきれなくなり、クレジットカードやカードローンに頼るケースが増えています。
これが、借金の沼にはまる最初の一歩です。
自己破産に至った複数の事例では、初めは「今月だけ特別」という意識でクレジットカードを利用しています。
翌月の給料で返済するつもりが、次のイベントやグッズが発表されると、また同じように「特別」として利用してしまうのです。
そして次第に、前月の借金を返済する前に新たな借金を重ね、しまいには借金を借金で返済する「自転車操業」状態に陥ってしまうのが一連のパターンとなっています。
この自転車操業が常態化する背景には、「推し活は特別」という心理があります。
日常生活では節約していても、推し活に関しては「投資」や「必要経費」として例外扱いにしてしまうのです。
推し活費用を通常の家計管理の枠組みから切り離してしまうことで、実際の経済状況と乖離した消費行動が続いてしまうという流れです。
リボ払いの危険性とは
推し活にのめり込んだ人々がお金を工面する際によく利用するのが、クレジットカードのリボルビング払い(リボ払い)です。
毎月の返済額を一定にできる便利さがある一方で、高い金利が課され、結果的に返済総額が膨れ上がるリスクがあります。
カードローンの返済もあるのに、加えてクレジットカードのキャッシングも利用していては、いつまでたっても返せるはずがありません。
また、1社からの借入限度額に達すると、別の会社でカードを作り、さらに借り入れを続けるという悪循環に陥ります。
特にリボ払いの「毎月の支払いが少額で済む」という特徴が借金のワナです。
少額支払いによって「まだ余裕がある」という誤った認識が生まれ、さらなる借入や支出を続けてしまいますが、実際には金利によって返済総額はどんどん膨れ上がり、最終的に返済不能な状態にまで陥ってしまうのです。
借金が膨れ上がるしくみとは
推し活関連の借金が膨れ上がる背景には、構造的な要因があります。
まず、「推し活」という趣味は継続的な出費を伴うものであり、単発の大きな出費ではなく、少額の支出が積み重なるという特徴があります。
さらに、推し活には「緊急性」が伴うことが多いのも問題です。
限定イベントの開催告知、予想外のサプライズ発表など、「今しかない」機会に対応するため、計画的な貯蓄ができないまま出費が発生してしまいます。
こうした予測不能な出費に対応するために借金に頼り、それが繰り返されることで、気づかないうちに返済不可能な規模にまで膨れ上がってしまうのです。
消費感覚が麻痺しやすいから
推し活における過剰消費には、消費者の感覚が麻痺する要素があります。
特に問題なのは、徐々に金額の感覚が麻痺していく「慣れ」の現象です。
最初は1000円のグッズを購入することにためらいを感じていたファンが、次第に5000円、1万円という、より高額な買い物に抵抗を感じなくなっていきます。
これは心理学で言う「アンカリング効果」に類似した現象で、一度高額な出費を経験すると、それが新たな「普通」の基準になってしまうのです。
また、前述の何が当たるかわからない「ランダム商法」も、消費者の合理的判断を鈍らせる効果があります。
商品そのものの価値と購入価格の関係性を曖昧にし、「当たり」を求める心を刺激することで消費感覚を麻痺させ、過剰消費を促進しているのです。
推し活破産を防ぐには弁護士へ相談しよう

借金が膨らみ始めたら、早めの対策が重要です。
特に推し活による借金は「趣味だから問題ない」と放置されがちですが、対応が遅れるほど解決は難しくなります。

「ちょっとヤバいかも」と思う前に、一度立ち止まることが重要ですね…。
 弁護士
弁護士借金の増加に歯止めがかからなくなったとき、法律の専門家に相談することで状況を改善できる可能性があります。
弁護士へ相談するタイミング
推し活による借金問題は、初期段階では気づきにくいことが特徴です。
多くの場合、「まだ返せる」という思い込みから相談が遅れるケースが見られます。
自覚することは難しいかと思いますが、借金の返済が難しくなってきたと感じたら早急に対応することが重要です。
債権者に連絡して状況を説明し、分割払いの相談や支払期限の延長などを交渉できる可能性があります。
早期対応の目安として、以下のような状況になったら専門家への相談を検討すべきでしょう。
まず、毎月の返済額が収入の3分の1を超えるようになったときです。
家賃や食費、光熱費などすべての生活費を、残りの2/3の収入ですべてまかなう必要があり、家計のやりくりは厳しくなります。
次に、返済のために新たな借り入れが必要になった場合です。
これは典型的な自転車操業の始まりであり、早急な対応が必要となります。
また、債権者からの督促が増えた、返済日に寝込むほど精神的に辛くなった、といった状況も専門家に相談すべきサインです。
特に推し活による借金の場合、「この先もっとお金がかかる」という不安を抱えやすいため、早い段階で客観的なアドバイスを求めることが重要です。
そうすれば、推し活を続けながらも返済計画を立て直すことで、破産という最悪の事態を避けられる可能性があります。
弁護士相談で得られるサポート
推し活による借金問題では、早めに弁護士へ相談することが大切です。
弁護士は債務者の状況に応じた最適な債務整理の方法を提案してくれます。
借金の金額、収入状況、資産状況などを総合的にふまえ、任意整理、個人再生、自己破産の中から、状況に合った対応方法を提案してくれるのです。
また、弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から各債権者に「受任通知」という書面を送付します。
通知が債権者に届いた時点で、債権者から債務者への直接の取り立てが一時的に禁止されます。
そのため、債権者は、督促の電話や訪問から解放され、精神的な余裕を取り戻せるというわけです。
さらに、債権者や裁判所とのやり取りもすべて弁護士に任せられます。
借金問題による精神的な負担が大きく、債権者は正常な判断ができなくなっているケースも少なくありません。
弁護士という専門家に代理人として手続きを進めてもらうことで、精神的な負担が軽減され、推し活との向き合い方を冷静に考える余裕も生まれます。
債務整理の方法
債務整理の方法としては、まず任意整理が考えられます。
これは裁判所を利用しない手続きで、債権者と交渉し、返済方法の変更や将来利息のカット、遅延損害金の減免などを認めてもらう方法です。
推し活による借金でも、特定の債権者を除外して債務整理を進められる場合があります。
個人再生は、借金を大幅に減額しつつ原則3年で分割返済していく方法です。
自宅や車などの財産を手放さずに債務整理できますが、安定した収入があることが条件となります。
推し活による借金が高額でも、生活をしながら返済する道を選びたい場合に適しています。
自己破産は、裁判所から免責許可決定を受けることで借金の返済義務を免除してもらう方法ですが、推し活による浪費は免責不許可事由(返済義務が認められない事由)になり得ることに注意が必要です。
また、一定金額以上の財産をすべて手放す必要があり、信用情報にも記録されるため、その後の生活に制約が生じます。
どの方法が最適かは個々の状況によって異なりますので、まずは法律の専門家に相談し、推し活による借金の特徴や自身の経済状況に合わせた最適な解決策を見つけることが重要です。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
推し活は生活に潤いをもたらす大切な趣味である一方で、気づかないうちに借金を抱えるリスクも伴います。
単発の出費は少額でも、CD・グッズ・遠征費など多岐にわたる費用が積み重なり、トータルで見れば予想を超える金額になることも少なくありません。
さらに、ファン同士の比較による心理的プレッシャーや、SNSでのマウント文化が消費をあおり、無理な支出を捻出する原因となることもあります。
クレジットカードやリボ払いによる「自転車操業」に陥ると、借金は雪だるま式に膨らんでしまいます。
このような状況に陥った場合、早めに弁護士等の専門家へ相談することが重要です。
推し活を楽しみながらも、自分の経済状況を冷静に見つめ、持続可能な形で続けていくことこそが、長く推しを応援するための最善の方法と言えるでしょう。

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。
※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










