「犯罪の被害に遭ったけど、どうすればいいかわからない」
「警察に相談したいが、何から始めればいいの?」
「被害届って聞いたことはあるけど、具体的にどうやって出すの?」
このような不安や疑問を抱えている方は少なくありません。
詐欺、窃盗、傷害、ストーカーなど、誰もが犯罪被害に遭う可能性があり、万が一被害に遭ってしまったときのために適切な対処法を知っておくことが大切です。
もしも、犯罪被害に遭った場合は、可能な限り早期に被害届を提出することが重要です。
被害届は、警察が捜査を開始するきっかけとなる書類であり、適切な手続きをふむことで犯人の特定や事件解決につながる可能性が高くなります。
ただし、告訴との違いや提出方法、必要な準備などを正しく理解しておかなければ、受理されない場合もあります。
本記事では、被害届の基本的な意味から具体的な提出方法、警察署での手続きの流れ、受理されやすい書き方のコツまで、被害届に関する全ての情報を弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
被害届とは?どんなときに出すべき?

 弁護士
弁護士被害届は、犯罪の被害を受けたときに警察に提出する重要な書類です。
多くの方が「いざというときにどうすればいいのか」と不安に思われるかもしれませんが、ポイントを押さえておけば、スムーズに手続きを進められます。

「被害届」という単語自体はよく聞きますが、実際どのようなものなのかはよくわかっていません…。
被害届の意味と目的
警察が犯罪の存在を知り、捜査を始めるきっかけとなる重要な文書として位置づけられています。
被害届の主な目的は、捜査機関に対して被害にあった事実を申告することです。
被害があれば、犯人を特定していなくても提出できるもので、警察が犯罪捜査に着手するためのきっかけとなります。
被害届を提出することで、犯人の特定や事件解決につながる可能性が高くなります。
告訴・告発との違いは?
被害届と混同されやすいものに、告訴・告発があります。
これらは犯罪被害を伝える点では被害届と同様ですが、最も大きな違いは、処罰を求める意思表示があるかどうかです。
告訴・告発は被害申告に加えて犯人に対する処罰を求める意思表示を含みますが、被害届は被害があったことを申告するものです。
被害届でも、処罰を求める意思は表示できますが、必須事項ではありません。
被害届・告訴・告発のそれぞれの違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 被害届 | 告訴 | 告発 |
| 意味 | 被害の申告 | 被害の申告+処罰意思がある | 被害の申告+処罰意思がある |
| 捜査開始義務 | なし | あり | あり |
| 主体 | 原則被害者本人 | 被害者など告訴権者 | 第三者 |
| 親告罪の訴追 | できない | できる | できない |
法的な効力にも違いがあります。
告訴・告発をした場合には、警察は捜査を開始する義務が生じます。
一方、被害届を提出した場合、捜査が行われるかどうかは、警察の判断に委ねられます。
また、親告罪への対応も異なります。
名誉毀損罪や器物損壊罪などの親告罪では、起訴するために告訴が不可欠です。
被害届から告訴への切り替えは可能
被害届を出した後でも、告訴状の提出は可能です。
ただし、親告罪については告訴期限(犯人を知った日から6か月以内)があるため、期限内に手続きを行う必要があります。
反対に、告訴から被害届への変更は基本的にできませんが、告訴を取り下げて被害届を新たに提出することは可能です。
状況に応じて適切な手続きを選択し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
被害届提出前の準備

被害届をスムーズに提出するためには、事前の準備が重要です。
 弁護士
弁護士しっかりと準備しておくことで、警察での手続きが円滑に進み、受理される可能性も高くなります。

どのような準備をすればいいのでしょうか?
被害届を提出するタイミング
被害届の提出において、法律上の期限は設けられていません。
ただし、できる限り早急に提出することが重要です。
時間の経過とともに有力な証拠がなくなっていくおそれがあるため、被害直後の提出が理想的です。
時間が経過してから被害届を提出する場合、警察から提出が遅れた理由について説明を求められることがあります。
そこで合理的な説明ができない場合は、取り合ってもらえない可能性があることに留意が必要です。
また、事件が軽微で被害から時間が経っている場合には、基本的に受理されないか、受理されても放置されてしまうケースもあります。
また、公訴時効の観点からも、早期提出は重要です。
犯罪には公訴時効が設定されており、この期間を過ぎると起訴できなくなってしまいます。
確実に被害届を受理してもらい、適切な捜査を受けるためには、被害があったらすぐに提出するよう心がけましょう。
なお、被害届を出すべき判断基準としては、まず「刑事事件としての事件性があるかどうか」です。
民事事件に該当する内容では、「民事不介入の原則」により被害届は受理されません。
どこに出せばいい?警察署の探し方と確認方法
基本的に、被害届は事件があった場所を管轄する警察署に提出します。
管轄の警察署を探す際は、被害者の住所地、加害者の住所地、犯罪発生地のいずれかの管轄警察署が主な提出先となります。
最も一般的なのは、被害者の住所地を管轄する警察署への提出です。
全く関係のない遠方の警察署に提出しても、最終的には管轄の警察署へ送られることになります。
警察署の管轄区域や所在地は、各都道府県警察のホームページで確認できます。
また、警察相談専用電話「#9110」に電話して、どこの警察署に相談すべきか確認することも可能です。
交番でも被害届の受付は可能ですが、事件の規模によっては対応してくれない場合があります。
交番では警察官の人員も限られており、長時間の事情聴取や詳細な被害内容の確認を行う余裕がない場合があるためです。
可能であれば、はじめから警察署に行った方がよいでしょう。
犯罪被害に遭った直後であれば、110番通報も有効です。
警察官が到着すれば、更なる被害を防ぐとともに、その場で被害状況を確認してもらえます。
被害届提出時に必要な物一覧
被害届を提出する際は、手続きを円滑に進めるため、必要な持ち物を事前に準備しておくことが重要です。
必須の持ち物として、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書と印鑑があります。
身分を証明できるものがないと、被害届の提出者が本人であることを確認できないため、必ず持参してください。
印鑑は認印で構いませんが、シヤチハタ(浸透印)は避けた方が無難です。
もしも、被害の証拠があれば持参しましょう。
ただし、保存が急がれる証拠(指紋の付着など)については、下手に持って行かない方が良い場合もあります。
証拠品の取り扱いに不安がある場合は、事前に警察へ相談しておくことがお勧めです。
また、犯罪事実の存在を裏付ける資料もあれば、合わせて持参しましょう。
担当警察官に事件の内容を理解してもらいやすくなり、被害届の受理につながりやすくなります。
写真、録音データ、メッセージのスクリーンショット、契約書類など、事件に関連する資料は可能な限り用意しておきます。
被害届提出に手数料はかからない
被害届の提出に、手数料は一切かかりません。
警察への被害届提出は公的サービスの一環であり、費用を請求されることはありません。
 弁護士
弁護士もし手数料を要求された場合は、詐欺の可能性があるため注意が必要です。
ただし、警察署に行くための交通費や、必要に応じて証拠書類のコピー代などは自己負担となります。
これらは手数料とは別の、被害者が負担すべき実費で、電話での相談にかかる通話料も同様です。
また、捜査過程においても、被害者に費用を請求されることは基本的にありません。
取調べや実況見分への協力、証人としての出廷なども、被害者の義務として行われるものであり、費用負担はありません。
加害者として犯罪を起こした場合の取調べでは、警察車両での送迎や留置場での食事提供など、一定のサービスが提供されます。
これは被害者と被疑者で扱いが異なる点として注目されることがあります。
なお、被害届に関連して弁護士に相談する場合や、民事訴訟を起こす場合には別途費用が発生しますが、これらは被害届提出の手数料ではなく、追加的な法的サービスに対する費用です。
被害届提出前に整理しておくべき事項
被害届を提出する前に、被害の内容を5W1Hの形式で整理しておくことが重要です。
- Who(誰が)
- When(いつ)
- Where(どこで)
- What(何を)
- Why(なぜ)
- How(どのように)
これらを時系列で整理し、被害の詳細や金額、犯人の特徴などを可能な限り詳しくまとめておきましょう。
あいまいな記憶では警察も対応しにくくなるため、記憶が鮮明なうちに要点を書き出しておくことが大切です。
また、刑事事件としての事件性があることを、明確に説明できるよう準備しておくことも重要です。
民事事件と判断されると被害届は受理されないため、どのような犯罪に該当するのかを整理しておく必要があります。
さらに、被害届を提出する目的や、希望する対応についても明確にしておきましょう。
単に被害を申告したいのか、犯人の処罰を求めたいのか、示談を希望するのかなど、自分の意向を整理しておくことで、適切なアドバイスを受けられます。
警察署での流れ

 弁護士
弁護士警察署での被害届提出は、受付~書類作成まで、順を追って行われます。
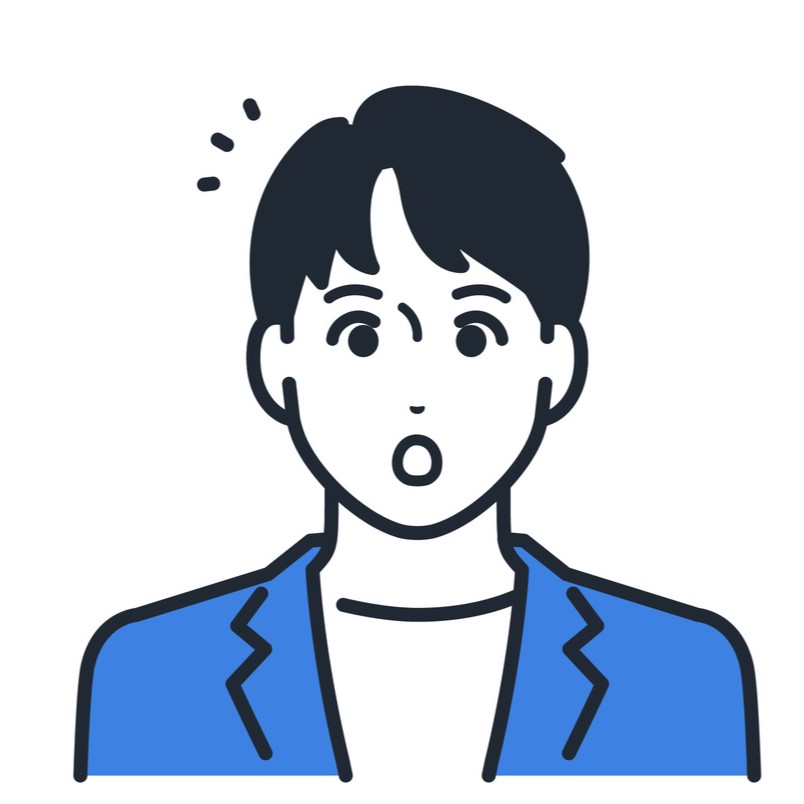 弁護士
弁護士事前に手続きの流れを把握しておくと、スムーズに対応できますね。
受付時に伝えること
警察署に到着したら、まず受付で「被害届を提出したい」と明確に伝えましょう。
受付では、どのような被害を受けたのかを簡潔に説明する必要があります。
この時点で詳細を全て話す必要はありませんが、事件の概要を整理して伝えることが重要です。
また、受付では身分証明書の提示を求められることがあります。
運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認ができる書類を準備しておきましょう。
さらに、被害届提出の理由や緊急性についても、簡単に説明できるようにしておくと、スムーズに担当者に案内してもらえます。
事前に警察署に連絡を入れて、概要を説明し、担当警察官に時間をとってもらうこともおすすめです。
突然訪問するよりも、事前連絡により適切な準備をした状態で対応してもらえる可能性が高くなります。
犯罪事実の存在を裏付ける資料を持って事情を説明しに行くことで、担当警察官に事件の内容を理解してもらいやすくなるでしょう。
受付で案内される場所は、警察署の構造によって異なります。
新しい警察署では市民相談窓口のような開放的なスペースで対応されることもありますが、古い警察署では取調べ室と同じ部屋で手続きすることが一般的です。
これは被害者も被疑者も同じ部屋で調べを受けるという警察の運用によるものです。
書類の書き方を解説(記入例つき)
被害届の書式は警察署に用意されています。
実際には被害者の話を警察官が聞き、警察官が代わりに記載することが多いため、事前に被害届を自分で準備していく必要はありません。
ただし、記載内容を理解しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
被害届には、以下の項目を記載します。
- 被害者の住居
- 被害者の職業
- 被害者の氏名
- 被害者の年齢
- 被害の年月日時
- 被害の場所
- 被害の詳細
- 被害金品
- 犯人の住居
- 犯人の氏名
- 犯人の人相
- 犯人の着衣
- 犯人の特徴
- その他参考となる事柄
これらについて、聞かれたら答えられるよう、わかる範囲で事実を整理しておくことが重要です。
記入例:窃盗被害の場合
- 被害者:住所「東京都○○区○○町1-2-3」職業「会社員」氏名「田中太郎」年齢「35歳」
- 被害年月日時:「令和6年3月15日午後2時頃」
- 被害場所:「東京都○○区○○町1-2-3番地先路上」
- 被害詳細:「自宅前に駐輪していた自転車1台を何者かに盗まれた」
- 被害金品:「電動自転車1台(ブランド名:○○、色:青、購入価格:約8万円)」
- 犯人の特徴:「不明(目撃者なし)」
- その他:「盗難に気づいたのは帰宅時の午後6時頃」
このように具体的かつ正確な情報を整理して提供することで、警察の理解を得やすくなります。
供述調書との違いと注意しておきたい点
被害届と供述調書は、どちらも警察での手続きに関わる書類ですが、目的と内容が大きく異なります。
| 被害届 | 被害事実を申告するための書類 |
| 供述調書 | 詳細な事情聴取の内容を記録した書類 |
供述調書は、被害届よりもはるかに詳細な内容を含みます。
被害の状況、犯人との関係、被害に至る経緯、目撃者の有無、被害後の対応など、事件に関するあらゆる情報が記録されます。
また、法廷での証拠として使用される可能性があるため、より慎重に作成すべきです。
注意すべきは、被害届提出後に供述調書の作成が別途必要になる場合があることです。
被害届は事件の端緒となる書類ですが、本格的な捜査が開始されると、より詳細な事情聴取のために供述調書が作成されます。
犯罪捜査規範では、参考人供述調書を作成したときは被害届の作成を省略できるとされていますが、実際には両方作成されることが一般的です。
なお、供述調書の内容を後に変更することは困難です。
そのため、記憶があいまいな部分については「覚えていない」「はっきりしない」と正直に答えておきましょう。
あいまいな記憶に基づいて不正確に供述してしまうと、後の捜査や裁判で問題となる可能性があります。
また、供述調書には被害者の署名・押印が必要です。
内容をよく確認してから署名するようにし、不明な点があれば遠慮なく担当者に質問しましょう。
被害届受理後の警察での手続き
被害届が受理された後は、警察による事件性の判断と捜査方針の決定が行われます。
警察は被害届の内容を検討し、刑事事件として捜査開始するかどうかを判断します。
被害者に対して追加の事情聴取が行われるのは、この段階です。
被害届受理後の警察の対応は、事件の性質や緊急性によって異なります。
緊急性が高い事件では、即座に捜査が始まることもありますが、そうでない場合は業務の繁閑や事案の内容によって対応が決まります。
 弁護士
弁護士被害届を受理したら必ず捜査しなければならないという法律上の義務はないため、場合によっては放置される可能性もあるのです。
捜査が開始されると、被害者に対して取り調べや証拠品の提出、実況見分などの捜査協力を求められます。
これらは任意で行われるもので、義務ではありません。
しかし、犯人を正しく処分するためには、協力が必要となります。
被害者も被疑者と同様に、取調べ室で事情聴取を受けることになります。
被害届の受理証明書について警察が発行する義務はありません。
ただし、保険金請求などで必要になる場合があり、警察署によっては受理証明書を発行してくれる場合もあるため、必要に応じて相談してみましょう。
被害届の書き方のコツ

 弁護士
弁護士被害届を確実に受理してもらうためには、記載内容の具体性と正確性が重要です。
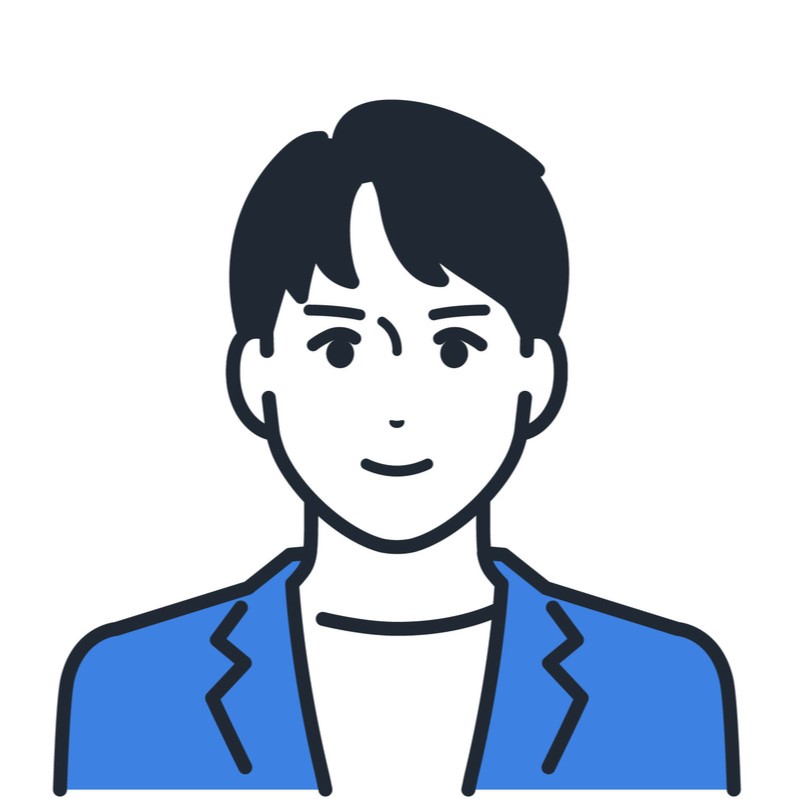
誰が見ても事件性を判断しやすいよう、要点を押さえた書き方を心がけるべきですね。
いつ・どこで・誰が?具体的に書くコツ
前述のとおり、被害届を効果的に作成するためには、5W1Hを意識した具体的な記載が不可欠です。
これによって、警察が事件を理解しやすくなります。
記憶のある限り、警察官に被害事実を正確に申告することが重要です。
あいまいな表現ではなく、できる限り具体的な情報を提供しましょう。
日時については「○月頃」ではなく「○月○日午後○時頃」というように、より詳細に記載することが推奨されます。
場所についても「自宅付近」ではなく「○○市○○町○丁目○番地先の路上」というように、第三者でも特定できる程度の具体性が必要です。
被害の詳細についても、単に「盗まれた」だけではなく、どのような状況でどのような手口により被害を受けたのかを詳しく記載します。
例えば、ストーカー被害の場合、「○○(被疑者)からストーカー被害を受けています」と書くだけでは不十分です。
ストーカーにはつきまとい、メールの送信、無言電話など様々な手口があるため、いつ、どこで、どんな手口で被害を受けたのかを具体的に記載する必要があります。
犯人の特徴についても、分かる範囲で詳細に記載します。
身長、体格、服装、特徴的な言動など、後の捜査に役立つ情報を可能な限り記録しておきましょう。
目撃者がいる場合は、その情報も重要な参考事項となります。
受理されにくいNG例と受理されやすいOK例
被害届の受理可否は記載内容によって大きく左右されます。
以下の表で、受理されにくい例と受理されやすい例を比較して確認しましょう。
| 項目 | 受理されにくいNG例 | 受理されやすいOK例 |
| 日時の記載 | 「先月頃」「最近」 | 「令和6年3月15日午後2時頃」 |
| 場所の記載 | 「自宅付近」「駅前」 | 「○○市○○町1-2-3番地先路上」 |
| 被害内容 | 「お金を騙し取られた」 | 「投資名目で現金50万円を騙し取られた」 |
| 犯人の特徴 | 「怪しい人」「知らない人」 | 「30代男性、身長170cm程度、黒いジャンパー着用」 |
| 事件性の説明 | 「迷惑している」「困っている」 | 「刑法○○条の○○罪に該当すると思われる」 |
被害として届けられた事項が、刑事事件として扱えないと判断された場合には、「民事不介入の原則」によって被害届は受理されません。
例えば、「貸した金が返ってこない」というような相談は、基本的に民事事件となり、この場合には被害届が受理されることはありません。
事件が軽微で時間が経っている場合も、基本的には受理されないでしょう。
警察は日々多数の事件を扱っており、すべての事件を捜査するのは困難です。
被害が非常に軽く、年月が過ぎてしまった事件については、捜査する余裕はないのが現状です。
被害届では、刑事事件にあたることをしっかりと説明することが重要です。
どのような犯罪に該当するのかを明確にし、法的根拠を示すことで、警察の理解を得やすくなります。
また、被害の程度や社会的影響についても、適切に説明できるようにしておきましょう。
被害届作成時の注意点とポイント
事実のみを記載する
被害届の作成にあたっては、推測や憶測に基づく内容は避け、確実に把握している事実のみを記載しましょう。
記憶があいまいな部分については「覚えていない」「はっきりしない」と正直に話すことが重要です。
被害届の記載内容は、後の捜査や裁判において大切な証拠となる可能性があるため、虚偽の記載は避けましょう。
不正確な情報により捜査が混乱したり、後に問題となったりする可能性があります。
被害届は被害者本人が提出する
被害届は基本的に「被害者本人」が提出する必要があります。
ただし、被害者が幼い・病気で動けない・死亡しているなど、自身で被害を伝えられない場合には、代理人によって提出できる場合があります。
なお、代理人にあたる人は法律上の制度として規定されているわけではないため、例えば親族や弁護士が提出することも禁止されていません。
ただし、全く関係のない第三者が提出しても、警察は取り合ってくれない可能性が高いことに注意が必要です。
代理人が被害届を提出する場合は、本人との関係を証明する書類や、代理権限を示す委任状などが必要になることがあります。
また、後から本人による確認や追加の事情聴取が求められる場合もあるでしょう。
弁護士が代理人として被害届を提出する場合は、専門知識を活用した適切な書類作成が期待できます。
特に複雑な事件や法的判断が困難な案件については、弁護士による代理提出が有効な場合があります。
証拠がある場合、適切に保管・提出する
被害の証拠がある場合は、その旨を被害届に記載し、適切に保管・提出することが重要です。
証拠の取り扱いについては警察の指示に従い、独自の判断で処理しないようにしましょう。
被害届を出したあとの流れ

被害届を提出したあとも、被害者側は、やるべきことがいくつかあります。
 弁護士
弁護士捜査への協力や追加の事情聴取、必要な資料の提出などを警察から求められることがあります。
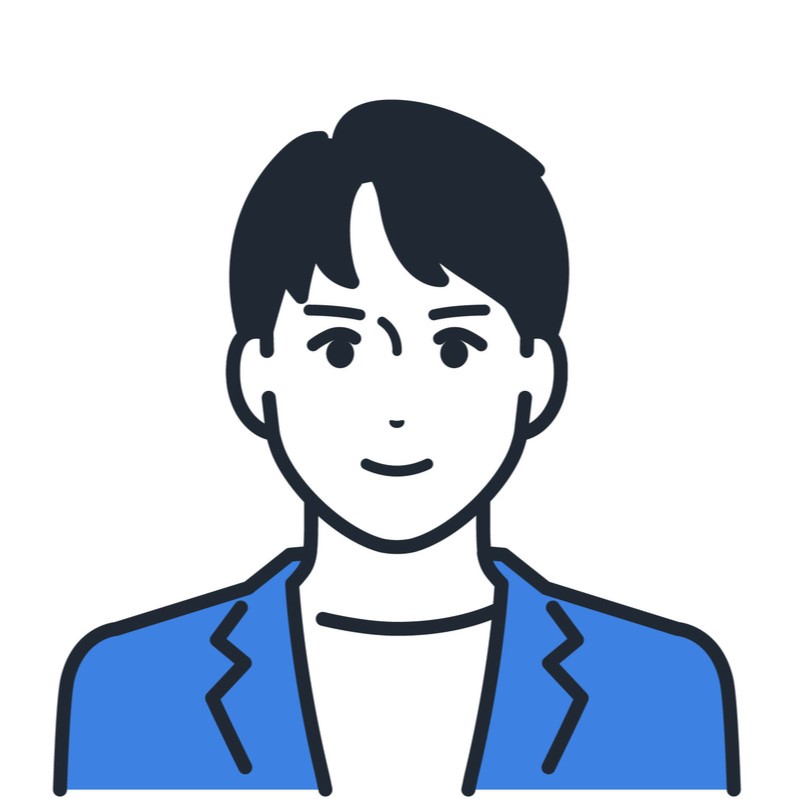
事前に、一連の流れを理解しておくことが大切ですね。
受理された後のスケジュールと対応
被害届が受理されたからといって、すぐに捜査や犯人逮捕に至るわけではありません。
受理後は、まず「事件性の有無」を判断するための内部審査が行われ、その後、必要と認められた場合に捜査が開始されます。
提出者に対して、進捗状況や結果が必ずしも共有されるとは限らず、事件として扱われないまま自然消滅するケースもあります。
警察は原則として事件性がなければ捜査を行わず、また捜査状況を開示する義務はなく、被害届を出しても音沙汰がないケースも少なくありません。
とはいえ、提出後に何の反応もない場合は、担当部署に問い合わせることで、捜査状況の有無を確認できることもあります。
ただし、担当官によって対応にばらつきがあるため、連絡先や窓口の記録は控えておくと良いでしょう。
受理されないときの理由と再提出のコツ
被害届が受理されなかった場合は、まず警察官にその理由を尋ね、改善可能な点があるかを確認することが重要です。
理由が合理的で是正できるものであれば、速やかに改善して再度提出を試みるべきです。
被害届が受理されない主な理由は、主に次の5つです。
- 事件性が認められない
- 民事トラブルにとどまる
- 証拠が不十分
- 被害が軽微
- 被害から時間が経っている
例えば、金銭の貸し借りでトラブルになった場合、「返済の意思がある限りは詐欺とはみなされにくい」とされ、民事不介入の原則により警察が介入しないケースが多く見られます。
金銭トラブルを被害届として提出しようとしても、貸した証拠や返済を求めた証拠がなければ門前払いされることもありえるのです。
このようなケースでは、証拠の整理・補完、経緯の時系列化など、再提出時の資料作成がポイントになります。
また、警察署によっては担当者の対応に差が生じることもあります。
所轄警察署で受理を拒否された場合、県警本部や監察室などの上級機関に相談することも一つの方法として覚えておきましょう。
また、弁護士に依頼して法的観点から被害届の正当性を主張してもらうことも効果的です。
弁護士などの専門家に相談することで、警察との交渉や書類の改善が可能となり、受理されるための適切なアドバイスを得られます。
さらに、告訴という手続きに切り替えることも検討すべき選択肢です。
告訴は法律上の制度であり、警察には捜査開始義務が生じるため、被害届よりも受理されやすいと言えるでしょう。
ただし、告訴には処罰を求める意思表示が必要であり、親告罪以外では必須ではありません。
追加資料の準備や、弁護士に相談すべきタイミング
被害届提出後に新たな証拠が出てきた場合は、速やかに追加資料として警察に提出すべきです。
特に、録音・LINEのやりとり・現場写真などは、客観性が高く、捜査の後押しとなる可能性があります。
提出後に証拠が揃っていくケースも少なくないため、「出して終わり」ではなく、情報更新の準備をしておくことが重要です。
また、対応に不信感がある場合や、被害届が繰り返し受理されない場合は、弁護士に相談することで打開策が見つかることもあります。
被害届が受理されないと精神的負担が増し、結果的に弁護士相談に至ることも少なくないため、被害者側の心理的負担が大きい局面でもあります。
警察対応に限界を感じたら、早い段階で法律の専門家である弁護士に相談し、示談・告訴・民事訴訟など次の選択肢を整理するのが望ましいでしょう。
被害届は郵送・オンライン提出できる?取り下げ方法は?

 弁護士
弁護士被害届の提出では、状況に応じて最適な方法を選択し、適切な手続きを行いましょう。
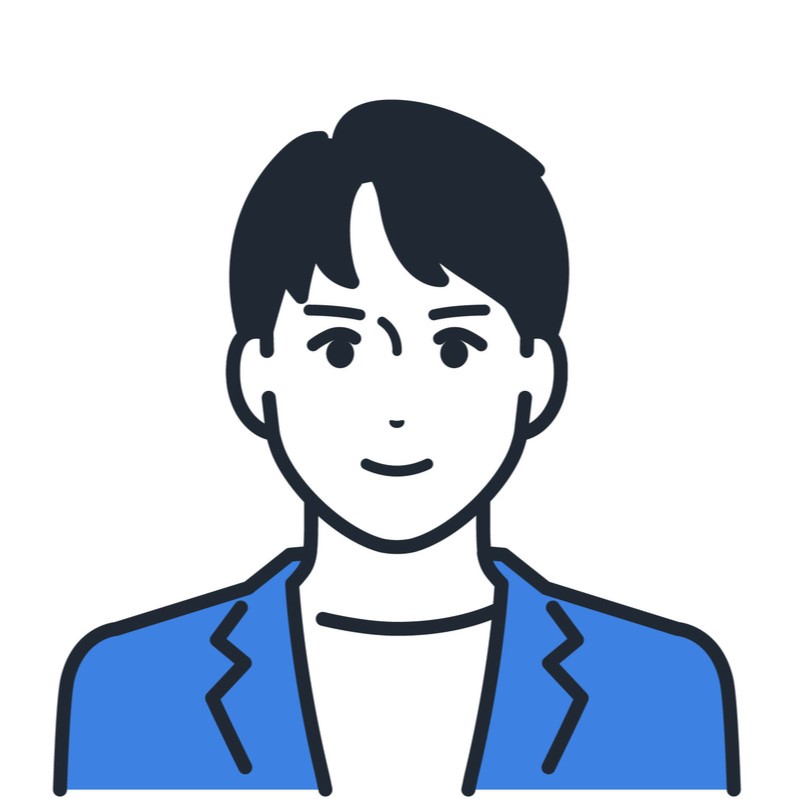
基本的には「警察署に赴いて被害届を記入する」という方法になります。
被害届は郵送でも提出できる
自ら作成した被害届を郵送で提出することは禁止されていません。
但し、郵送したとしても、警察から直接事情を確認したいとして警察署に来るように求められる可能性もありますし、二度手間になる可能性を踏まえれば、当初から警察署に出向いた方がよいと言えます。
なお、例外的に被害届のコピーを事前に郵送して内容確認を依頼したり、被害届受理後に補足資料を郵送したりするケースもあります。
これらの郵送を希望する場合は、事前に警察署に相談し、対応を確認することが重要です。
メール・電話や口頭のみでの提出はできない
2025年7月現在において、メールやオンラインでの被害届提出に対応している警察署はありません。
警察のメールアドレスを把握すること自体が困難であり、また被害届自体をメールで送っても正式な被害届として取り扱ってもらえる可能性は低いと考えられます。
メールでの被害届提出については、おそらく警察はそのような状況を想定していないため、正式な受理は期待できません。
ただし、被害があったことをメールで警察に伝え、それをもとに警察が動いてくれることで、被害届を出すのと同じような効果を得ることは可能性として考えられます。
電話での被害届提出についても同様で、電話のみで被害届を出すことは困難だと考えられます。
ただし、口頭で警察に被害を申告した場合、その内容をもとに警察が対応してくれることはありえますが、最終的には記録として残すため書面化されることが一般的です。
犯罪捜査規範第61条では、「前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届に記入を求め又は警察官が代書するものとする」と規定されています。
つまり、口頭で申告した場合でも、警察官が被害者に代わって被害届を作成できるというわけです。
また、110番通報も、口頭による被害申告の一種と考えられます。
緊急性がある場合は、まず110番通報を行い、警察官が現場に到着した後で正式な被害届の提出について相談することが適切です。
一度出した被害届を取り下げたいときは?
被害届は取り下げが可能です。
被害の弁償がなされて示談が成立した場合には、被害届の取り下げが条件となることが多いため、警察署に行って所定の手続きを済ませる必要があります。
被害届の取り下げ手続きができるのは、原則被害届を提出した本人のみです。
取り下げの際は、身分証明書と印鑑を持参し、警察署で取り下げ書類に記入します。
場合によっては、取り下げの理由についても詳細に説明を求められることがあります。
このように被害届の取り下げは可能ですが、安易に取り下げるのはおすすめしません。
一度取り下げた被害届を、気が変わったとして再度提出しようとしても、受理してもらえない可能性が高いからです。
警察は一度取り下げた事件について、被害者の意思が不安定であると判断し、再受理に慎重になる傾向があります。
また、被害届が取り下げられると、不起訴となる可能性が高くなります。
検察官は被害者の処罰意思を重視するため、被害届の取り下げは加害者にとって有利な材料となってしまいます。
取り下げを検討する際は、この点を十分に理解しておく必要があるでしょう。
被害届取り下げ時の注意点
前述のとおり、被害届の取り下げには、慎重な判断が必要です。
取り下げることで捜査が終了し、加害者が刑事処分を受けない可能性が高くなります。
このことを十分に理解した上で決断する必要があります。
示談による取り下げの場合、示談の内容を詳細に確認することが重要です。
- 示談金の額、支払い方法
- 支払い期限
- 守秘義務の有無
- 今後の接触禁止条項
これら示談書に記載される全ての条項を理解してから取り下げ手続きを行いましょう。
被害届取り下げ後、捜査への影響も考慮する必要があります。
捜査が既に進行している場合、取り下げによって捜査が中止されることが一般的ですが、他の証拠によって捜査が継続される場合もあります。
また、同種事件の被害者が他にもいる場合は、取り下げが他の被害者に与える影響も考慮すべきです。
取り下げ手続きには、時間的な制約が存在する場合があります。
特に、検察段階まで事件が進んでいる場合は、取り下げのタイミングによって効果が異なる可能性があります。
被害届の取り下げは、相手方に対して「接触禁止」や「再犯防止の約束」など、将来のトラブルを未然に防ぐための条件を付すことが有効な場合もあります。
そのため、取り下げを検討する際には、このような条件やタイミングを含め、必要に応じて弁護士に相談することが望ましいでしょう。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
被害届は犯罪被害を警察に申告し、適切な捜査を求めるための重要な手続きです。
被害を受けたら迅速に提出し、5W1Hを明確にした具体的な内容で記載することが受理のポイントとなります。
また、被害届と告訴は目的や法的効果が異なるため、その違いを正しく理解した上で、状況に応じた適切な方法を選択することが大切です。
このように、手続きを正しく行うことで、効果的な被害回復につなげられるでしょう。

足立高志 弁護士
大本総合法律事務所
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-1-1
大手町パークビルディング8階
tel 03-5224-4555
fax 03-5224-4556
mail adachi@omoto.top
【経歴】
中央大学法学部卒
2007年弁護士登録
中小企業から個人の方まで幅広く対応しております。過去は変えられませんが、より良い未来となるよう、手助けができればと思っています。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










