あなたは、保険金詐欺の危険性を知っていますか?
一見、簡単にお金を手にできる方法に思えるかもしれませんが、実は発覚リスクが高く、重大な法的制裁を受ける犯罪行為です。
保険会社の調査技術と情報共有システムの進化により、詐欺の発覚率は年々高まっており、軽い気持ちで行ったとしても、後戻りできないほど深刻な事態に陥ることがあります。
本記事では、保険金詐欺の定義から手口、発覚メカニズム、法的責任まで詳しく解説します。
保険の正しい利用方法と詐欺行為の境界線を明確にし、賢明な選択ができるようサポートします。
最後までお読みいただければ、保険金詐欺は一時的な利益よりも長期的な人生の損失の方が大きいことを理解いただけるでしょう。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
保険金詐欺とは?

保険金詐欺は、保険制度を悪用して不正に金銭を得ようとする犯罪行為です。
被害に遭ったと偽装し、実際の損害を水増しするなど、本来受け取る権利のない保険金を詐取します。
 弁護士
弁護士保険金詐欺は保険会社だけでなく、真面目に保険を利用する契約者全体の保険料にも悪影響を及ぼす社会的問題となっています。

軽い気持ちで保険金詐欺を行ってはいけませんね…。
保険金詐欺の定義
保険金詐欺とは、保険会社を騙してお金を詐取する行為であるため、刑法の定める詐欺罪が成立します。
具体的には、事実と異なる内容を保険会社に申告したり、意図的に事故や災害を引き起こしたりして、本来支払われるべきではない保険金を受け取ることです。
保険金詐欺は刑法246条に規定される「詐欺罪」に該当し、法定刑は「10年以下の懲役」となります(2025年6月1日より「懲役」は「拘禁刑」に改正、施行されます)。
注目すべきは、罰金刑の規定がなく、有罪判決が確定した場合は懲役刑となり、刑務所へ収監される可能性が高いことです。
初犯であっても実刑判決を受ける可能性があるため、軽い気持ちで保険金詐欺を行うと、人生に大きな影響を与えかねません。
保険金詐欺の具体例としては、以下のようなケースがあります。
- 自作自演の交通事故を装い保険金を請求するケース
- 実際には被害を受けていない部分を災害による被害と偽り、保険金を請求するケース
- 意図的に盗難を偽装して保険金を得ようとするケース
2017年5月には愛知県で保険金詐取未遂により男女3人が逮捕された事例や、2016年2月には福島県で少年ら4人が故意に車を衝突させて保険金をだまし取ったとして逮捕された事例があります。
保険金詐欺のよくある手口
保険金詐欺はさまざまな手口が存在しますが、特に損害保険における被害が多く見られます。
一般的なのは、自作自演の交通事故を装った請求です。
たとえば、友人らと共謀して計画的に事故を起こしたように見せかけ、保険金を詐取する方法があります。
友人を被害者として巻き込み、慰謝料や治療費を請求するパターンが多く、自分の友人を利用して慰謝料や治療費を保険会社から詐取する手口が典型的です。
通院日数や治療費を水増しするケースも多くあります。
実際の交通事故などで怪我をした場合でも、治療の回数を実際より多く申請したり、本来必要ない治療を受けたと偽ったりして保険金を不正に受け取ります。
たとえば、通院日数を増やした書類を作成し、本来より多くの保険金を請求するといった手口が一般的です。
また、災害とは無関係な被害での保険金請求も少なくありません。
特に火災保険においては、経年劣化による住宅の破損を自然災害によるものと偽って申請し、保険会社に補修料金を請求する手口が横行しています。
加えて、高級車やスポーツカーなど修理費用が高い車種をわざと傷つけ、外国産部品や塗装費用を水増しして請求するケースも見られます。
さらに、虚偽の診断書提出も保険金詐欺の代表的な手口の一つです。
医師と共謀して診断書を改ざんし、保険金を詐取するケースもあります。
こうした行為は医師法違反や公文書偽造にも該当する可能性があり、より重い罪に問われる恐れがあります。
保険金詐欺の成立要件
保険金詐欺が詐欺罪として成立するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
第一に、欺罔(ぎもう)行為があることです。これは、相手を騙そうとする意思があることを意味します。
保険金を請求する手続きの際に、嘘の報告をすることは、欺罔行為に該当します。
第二に、錯誤の成立が必要です。錯誤には、間違いや誤りといった意味があります。
保険会社が被保険者から受けた虚偽の報告を信じた場合に成立します。
第三に、交付行為が行われることです。
これは保険会社が自ら被保険者や被害者に対して保険金を支払う行為を意味します。
 弁護士
弁護士保険会社が保険金詐欺に気づき、交付行為を行わなかった場合は詐欺罪が成立せず、代わりに詐欺未遂罪という犯罪が成立することになります。
第四に、財産移転が発生することです。これは交付した財産が実際に相手へ渡った状態を指します。
保険会社が保険金を支払い、保険金詐欺を行った人が実際に受け取った時点で詐欺罪が成立します。
決済手続きを行ったものの、実際に振り込まれる前に保険金詐欺に気づいて決済を止めた場合は詐欺罪ではなく、詐欺未遂罪となります。
詐欺罪が成立するためには、上記4つの要件を、すべて満たす必要があります。
特に、交付や財産移転が発生していない場合は詐欺罪ではなく、詐欺未遂罪として刑事罰に処されます。
なお、詐欺未遂罪の法定刑も「10年以下の懲役」ですが、未遂で終わった場合は刑罰が軽減される傾向にあります。
保険金詐欺が発覚する経路
保険金詐欺が発覚する経路はいくつか存在します。
その中でもっとも多いのは、内部告発です。
詐欺を行った人間が知人に話し、それを知った知人が警察や保険会社に連絡するパターンが少なくありません。
詐欺を行う人物は周囲に自分の悪事を自慢するような傾向があり、そのことが発覚の原因となることが多いのです。
詐欺発覚後の事情聴取では「自分だけは罪を軽くしたい」という心理から共犯者が証言を覆すこともあります。
保険会社は通報者の身元を明かさないため、誰が告発したかは分からないままです。
次に多いのが、被害額の見積もりを出した機関からの情報提供です。
自動車事故の場合、整備工場や板金工場の担当者から保険会社に連絡が行き、保険金詐欺が発覚するケースが多く見られます。
整備工場や板金工場が保険金詐欺に加担した場合、罪に問われるリスクがあるため、怪しい依頼があれば保険会社に情報提供されるようになっているのです。
また、保険会社の調査要請によって発覚することもあります。
保険会社は、見積もりなどに問題がなければアジャスター(事故の調査や解決をサポートする職種)に協定依頼して保険金を支払いますが、確定できない要素があれば調査会社を入れることもあります。
事故状況と車の傷が一致しない、報告内容が食い違う、明らかに嘘をついているなどの場合に調査が入り、詐欺行為が発覚することもあります。
また、「歩けない」として保険金を受け取った被保険者が日常生活では普通に歩いていたことが調査で判明し、逮捕に至ったケースもあります。
 弁護士
弁護士保険会社の調査能力は年々向上しており、高額請求や不審な履歴がある場合は特に入念な調査が行われます。
★よく使用される調査方法★
- データベース検索を用いて過去の不正請求情報と照合する
- テキストマイニング(膨大なテキストデータから情報を抽出すること)で調査報告書や請求書類の矛盾を検出する
- SNS分析で事故関係者の不審な関係性を発見する
特に効果的なのはネットワークリンク分析で、一見無関係な請求データを参照して人や場所、アカウント、企業間の関係を明らかにできます。
保険会社は、これらの技術を組み合わせて詐欺を検知し、不正請求を防いでいます。
保険金詐欺はなぜバレるのか?

保険金詐欺は一見完璧な計画に見えても、どこかにほころびがあるものです。
保険会社は豊富な経験や最新技術を駆使して不正請求を検証し、詐欺行為者が見落とした証拠や関係者の証言から真実を明らかにしていきます。
 弁護士
弁護士保険会社の調査技術や不正検知技術は、年々レベルが向上しています。

保険会社はどのようにして詐欺を見破っているんでしょうか?
保険金詐欺を見破る方法
現代では、保険会社間の情報共有システムが整備され、不審な請求パターンを検出しやすくなっています。
日本損害保険協会の保険金不正請求ホットラインや各社間の情報交換制度により、複数の保険会社をまたいだ不正も発見されやすくなりました。
また、SNS投稿が証拠となるケースも増加しています。
重傷を装って保険金を請求した人物がSNSで日常生活を楽しんでいる様子を投稿し、請求内容と実生活の矛盾が生じることもあります。
このような投稿が発覚すると、不正が明るみに出る可能性もあるのです。
さらに、医療診断の矛盾も詐欺発覚の糸口になります。
たとえば、医師の証言と診断書の内容が一致しない場合や、複数医療機関で異なる診断が下された場合などが、調査の端緒となることがあります。
最新の不正検知技術
保険業界の不正検知技術は、急速に進化中です。
米国の調査によると、ネットワークリンク分析や予測モデリング、アノマリー分析などの先進技術の導入が進んでいます。
たとえば、以下のようなデータを活用し、多角的に分析します。
- 外部データベース
- 公共データ
- ソーシャルメディア情報
効果としては検知精度の向上(68%)、検知件数の増加(40%)、損害額の削減(40%)などが報告されています。
日本でも保険金不正請求通報制度が整備され、業界全体での対策が強化されています。
今後も詐欺検知技術は発展し続け、発覚率はさらに高くなると予想されます。
 弁護士
弁護士保険金詐欺は犯罪行為であるだけでなく、発覚リスクが非常に高い行為であることを認識すべきです。
保険金詐欺がバレた事例5選

保険金詐欺は様々な手口で行われますが、多くの場合いずれ発覚します。
以下では実際に発覚した保険金詐欺の事例を5つ紹介します。
 弁護士
弁護士事例を通じて、不正の手口や発覚に至る経緯、そして判決内容を知ることで、保険金詐欺がいかに重大な犯罪であり、どのような結末を迎えるのかを理解できるでしょう。
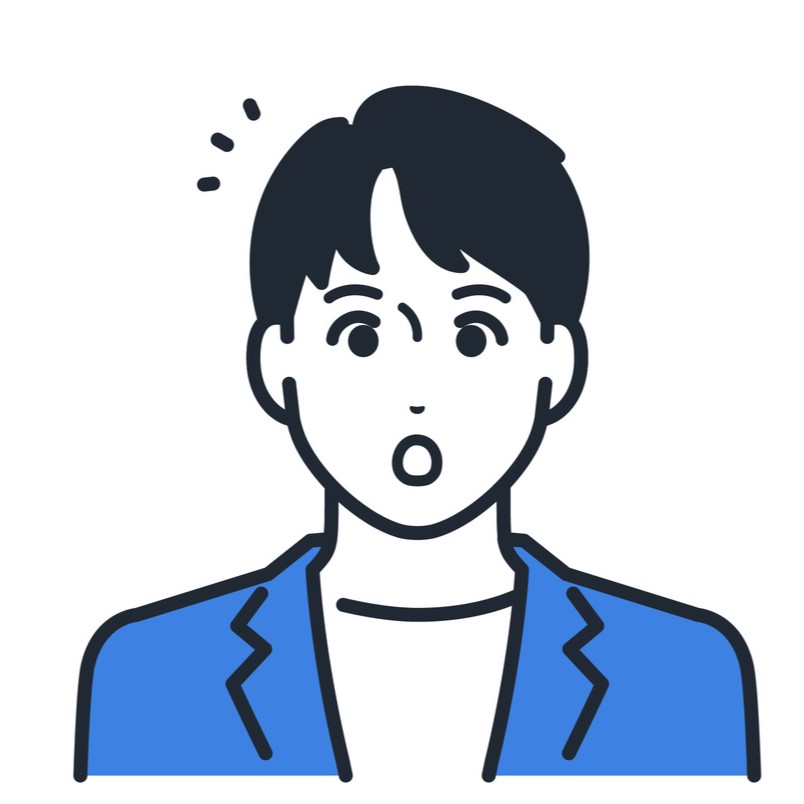
保険金詐欺に加担しないよう、気を付けます。
過剰な通院日数の水増しが調査で露見した事例
2010年代前半に発生した保険金詐欺事件では、交通事故の被害者が実際の必要性を超えて通院したと偽り、通院日数を水増しして保険金を請求しました。
被害者は実際には2週間程度で完治する軽傷であったにもかかわらず、3か月以上通院したと虚偽の申告を行い、約50万円の保険金を不正に受け取りました。
保険会社の定期的な調査で、通院パターンに不自然な点があることが発覚。
医師の診断内容と通院記録に矛盾があることが判明し、詐欺罪として起訴されました。
裁判では被告人が罪を認め、被害額全額を返還したことを考慮され、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が下されました。
この事例では、保険会社による通院記録の精査と医師への確認調査が、詐欺発覚の決め手となりました。
通院日数の水増しは比較的よく見られる手口ですが、保険会社の調査体制が強化され、発覚率が高まっています。
交通事故の状況に矛盾があり、証言の食い違いで発覚した事例
2016年2月、福島県で少年ら4人が故意に車と車を衝突させて保険金をだまし取ったとして逮捕されました。
彼らは「アクセルとブレーキを間違えた」と主張していましたが、保険会社は4人の勤務先が同じであることや請求内容に不審な点があったことから警察に通報。
警察の詳細な調査により、事故現場の状況と証言内容の矛盾、および関係者の証言の食い違いが明らかになりました。
特に車両損傷の状態と主張していた事故状況が物理的に合致しないことが鑑定で判明し、計画的な詐欺であることが立証されたのです。
少年法適用により刑事処分の詳細は非公表となりましたが、このケースは関係者間の証言の不一致と物的証拠の矛盾が発覚の決め手となった典型例です。
計画的な詐欺であっても、複数人が関わると証言の一貫性を維持することは難しく、調査が進むにつれて矛盾点が浮かび上がってきたという事例です。
災害とは関係のない経年劣化を被害として報告した事例
2017年に発覚した火災保険詐欺事件では、商業施設の経営者が経年劣化による建物の損傷を台風被害と偽って火災保険を請求し、約200万円を不正に受け取りました。
保険会社の調査員が現地調査を行った際、損傷パターンが風災によるものではなく長年の劣化によるものであることを指摘。
また気象データからも申告された日時に該当地域で台風や強風の記録はないことが確認されました。
さらに建築の専門家による鑑定で、損傷は少なくとも数年前から進行していたことが証明されたのです。
裁判では被告人が計画性を否認したものの、詐欺の意図があったことは認められ、懲役3年、執行猶予5年の判決が下されました。
また、不正受給した保険金の全額返還も命じられています。
この事例は、保険会社の専門的な調査と気象データの活用、さらに専門家の鑑定が詐欺発覚の鍵となったケースです。
特に自然災害を装った詐欺は、客観的な気象データが残っているため、発覚しやすくなっています。
過去の事故を再利用して二重に請求した事例
2014年に発覚した保険金二重請求事件では、実在した自動車事故の情報を利用して、複数の保険会社に同じ損害について請求を行い、合計で約500万円を不正に受け取りました。
被保険者は複数の保険会社に自動車保険を契約しており、一つの事故について各社に請求。
最初の保険会社からの支払いを受けた後、別の保険会社にも同じ事故について請求したのです。
しかし、2社目の保険会社が精査する過程で不審な点を発見。
日本損害保険協会が運営する情報交換制度を通じて照会したところ、既に別の保険会社から保険金が支払われていたことが判明しました。
裁判では、被告人に懲役3年の実刑判決が下されました。
保険契約時に重複保険の告知義務に違反していた点も量刑に影響しています。
この事例では、保険会社間の情報共有システムが詐欺発覚の決め手となりました。
2018年10月から、日本損害保険協会は保険金請求歴の情報交換対象を全種目に拡大しています。
このような二重請求の発覚率は、今後さらに高くなっていくでしょう。
虚偽の診断書を提出して入院費を水増しした事例
2020年に発覚した大規模な保険金詐欺事件では、医療機関が関与する組織的な詐欺が行われました。
医師と共謀した請求者が実際の治療内容を超える虚偽の診断書を作成し、高額な保険金を詐取していたのです。
この事件では、保険会社のデータ分析システムが通常より高額な請求パターンを検出したことから調査が開始されました。
同じ医療機関からの請求に不自然な共通点があり、詳細な調査の結果、診療記録と請求内容の間に大きな矛盾があることが発覚。
関与した医師とグループメンバーは組織的詐欺として起訴され、主犯格の医師には医師免許の取り消しと共に懲役6年の判決が下されました。
患者役として加担した共犯者にも懲役2~4年の実刑判決が下されています。
この事例では、保険会社のAIを活用した異常検知システムが功を奏し、組織的な詐欺行為が発覚しました。
医療機関が関与する詐欺は悪質性が高いとみなされ、厳しい判決につながっています。
保険金詐欺がバレた場合はどうなる?

 弁護士
弁護士保険金詐欺が発覚した場合、単なる保険契約上のペナルティでは済まされず、刑事罰の対象となります。

有罪となった場合、どのような罰則があるのでしょうか?
詐欺罪として厳しい罰則が科される可能性もあり、金銭や社会的信用の喪失など、人生を大きく左右する事態へと発展することになるでしょう。
「詐欺罪」にあたる
保険金詐欺は刑法246条に規定される「詐欺罪」に該当し、法定刑は「10年以下の懲役」です(2025年6月1日より「懲役」は「拘禁刑」に改正、施行されます)。
詐欺罪には罰金刑の規定がなく、有罪判決が確定した場合は懲役刑となり、刑務所への収監となる可能性が高くなります。
詐欺罪は、未遂でも刑事罰の対象です。
刑法250条では詐欺罪の未遂も罰すると規定されており、保険金詐欺が未遂に終わった場合でも「詐欺未遂罪」として処罰されます。
法定刑は同じく「10年以下の懲役」ですが、未遂で終わった場合は実行した場合と比べて減刑される傾向にあります。
欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪は成立するため、保険会社に嘘の報告をして保険金を騙し取ろうとした時点で、犯罪なのです。
実刑判決を受けた具体的なケースとして、保険金目的で店舗に放火した自営業者が約1千万円の保険金を手にしようとした事件で、懲役5年の実刑判決が下された事件がありました。
また、医療機関の幹部が虚偽の患者情報をもとに約500万円を受け取った健康保険の不正受給事件では、懲役4年の実刑判決を受けています。
 弁護士
弁護士特に、被害額が大きく、計画性・悪質性が高いと判断された場合は、初犯であっても実刑判決となる可能性が高いです。
逮捕され長期間にわたって影響を受ける
保険金詐欺で逮捕された場合、刑事手続きが取られます。
まず逮捕から始まり、その後48時間以内に検察官に事件が送致されます。
送致を受けた検察官は24時間以内に「勾留するかどうか」を判断。
その後、裁判官に勾留請求を行います。
勾留が決定すると、原則10日間の身柄拘束が行われ、必要に応じてさらに10日間延長されることも。
勾留期間中に検察官は「起訴・不起訴」を判断します。
詐欺罪のような悪質性の高い事件では起訴される可能性が高く、起訴された場合は刑事裁判へと進みます。
刑事裁判では証拠調べや証人尋問などを経て有罪か無罪かが判断され、有罪の場合は刑の重さが決定される流れです。
逮捕後に受ける影響は、身柄拘束だけではありません。
最大23日間の勾留が行われるため、社会生活が突然中断します。
学生であれば学校に行けず、社会人であれば会社に出勤できなくなります。
結果として、退学処分や解雇などの深刻な事態に発展することも少なくありません。
さらに、詐欺事件は社会的な注目を集めやすく、年齢によってはニュースなどで実名報道される可能性もあります。
一度報道されると、その情報はインターネット上に残り続け、社会生活において長期間にわたり影響を及ぼすことになります。
保険金詐欺による一時的な利益と引き換えに、社会的信用を失うという重大なリスクを負うことになるのです。
支払われた保険金の全額を返還請求される
保険金詐欺が発覚した場合、不正受給によって得た保険金は全額返還請求されます。
返金方法は保険会社によって異なりますが、基本的には一括払いが一般的です。
経済的に一括返済が難しい場合は分割払いとなることもありますが、返済する意思を示すことが重要です。
誠実な対応をすることで、刑事罰が軽減される可能性もあります。
また、保険金詐欺が発覚すると、保険契約は強制的に解除されます。
つまり、詐欺行為後に実際に保険金支払い事由が発生したとしても、保険金が支払われなくなるというわけです。
保険契約解除後に再契約を検討することも可能ですが、契約における審査は厳格に行われます。
例えば、医療保険に加入中に病気や怪我で保険金を受け取った後、通常は契約期間まで保険契約は継続します。
しかし、詐欺により契約解除となった場合は、新規加入時と同じ審査基準が適用されます。
そのため、過去に発生した怪我や病気が原因で加入を断られることもあるのです。
さらに留意したいのは、保険業界間での情報共有による影響です。
日本損害保険協会は2013年に保険金不正請求対策室を設置し、保険金不正請求ホットラインを開設しました。
現在では全保険種目において契約内容、保険金請求歴や不正請求に関する情報が保険会社間で共有されます。
すなわち、一度詐欺を行うと業界全体からブラックリスト入りする可能性が高いのです。
このように、保険金詐欺がバレた場合のリスクは多岐にわたります。
一時的な金銭を得るため、安易に犯罪行為に手を染めると、取り返しがつかないほど深刻な影響を及ぼすことになります。
保険金詐欺の時効は何年?民事と刑事で異なる時効期間

保険金詐欺の時効は、刑事上の公訴時効と民事上の時効で大きく異なります。
詐欺行為を行った後、一定期間が経過すると法的責任を問われなくなる可能性がありますが、民事と刑事では時効の考え方や期間に違いがあるため、注意が必要です。
 弁護士
弁護士単純に、一定の期間が経過したから時効が成立した、というものではないことに留意が必要です。
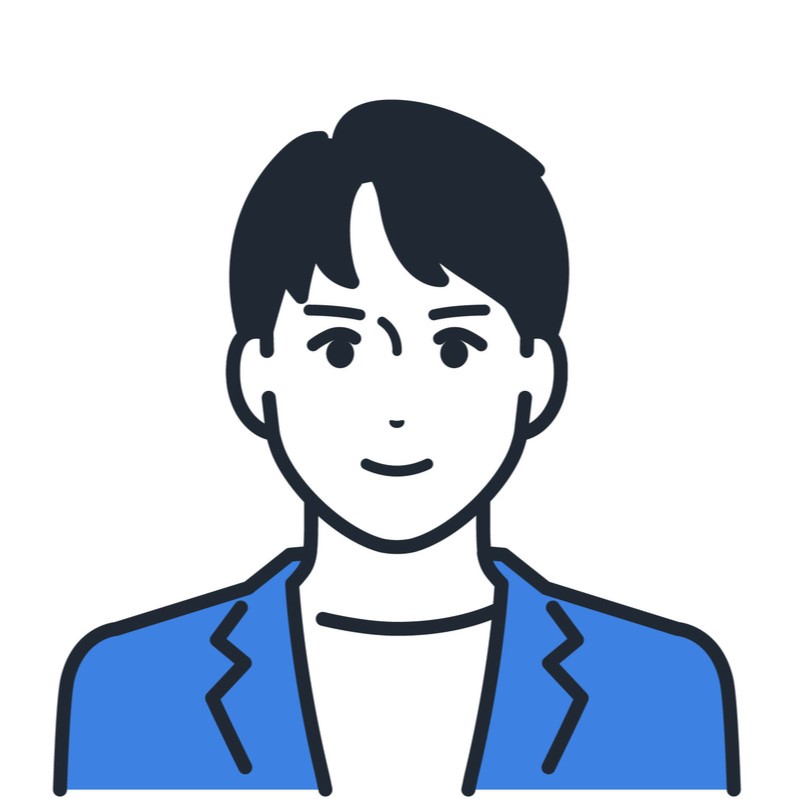
時効の考え方について詳しく知りたいです。
刑事事件の公訴時効
保険金詐欺の刑事事件における公訴時効は7年と定められています。
詐欺罪が成立してから7年が経過すると、時効が成立し、刑事罰を科すことができません。
この公訴時効は、犯罪行為が完了した時点から始まります。
詐欺未遂の場合も同様に7年の公訴時効が適用されます。
詐欺罪の場合、時効を迎えると、たとえ証拠がそろっていたとしても起訴できません。
公訴時効の趣旨は、時間の経過による証拠の散逸や記憶の薄れによる誤判の防止、また犯人の心理的負担の解消などが挙げられます。
過去の保険金詐欺において、行為から7年後に発覚したケースでは、公訴時効が成立したため起訴されませんでした。
しかし、これは刑事責任を問えなくなるだけであり、民事上の返還請求権は別途検討する必要があります。
また、公訴時効は犯人が完全に身をくらませたりした場合や犯人が海外に逃亡していた場合などには、その期間が停止することもあります。
民事事件の時効
保険金詐欺における民事上の時効は、保険会社からの返還請求権に関係します。
 弁護士
弁護士民事の時効には二つの期間が設定されています。
まず、保険会社が被害を認識した時点から3年が経過すると、消滅時効が成立します。
これは、保険会社が詐欺被害に遭ったことを知った時から起算される「主観的」な時効です。
請求可能な状態になった時点から3年間が経過すると、保険会社は保険金の返還を請求できなくなります。
一方、より長期の時効として、行為があった時点から20年が経過しても消滅時効が成立します。
これは「客観的」な時効と呼ばれるもので、保険会社の認識に関わらず、詐欺行為そのものから20年が経過した場合に適用されるものです。
つまり、詐欺行為が発生してから20年間、保険会社が被害に気づかなければ、その時点で時効が完成し、返還請求権は消滅するというわけです。
ただし、民事の時効は当事者が援用(時効による権利消滅を主張すること)しなければ効果が発生しません。
つまり、被告側が時効を主張しなければ、時効が成立していても請求が認められることがあります。
時効成立後でも残る民事上の責任
刑事事件の公訴時効が成立したとしても、民事上の責任は最長20年間残ります。
すなわち、刑事責任と民事責任は、別個の法律関係であることがわかります。
刑事上は時効により罪に問われなくなっても、不正に得た利益の返還義務は依然として存在し続けるのです。
具体的な事例として、ある保険金詐欺では、詐欺行為から8年後に発覚したケースがありました。
刑事訴追はできなかったものの、保険会社は民事訴訟を提起し、詐取された保険金の返還を求めました。
裁判所は公訴時効が成立していても民事上の責任は残るとして、詐欺者に対して全額の返還と遅延損害金の支払いを命じました。
このように、保険金詐欺において「刑事責任を問われなくなったから安全」と考えるのは誤りです。
民事上の責任は長期間残り続け、発覚すれば利息や遅延損害金を含めた返還義務が生じることになります。
保険会社側の時効対策とは
保険会社は保険金詐欺に対して時効が成立しないよう、さまざまな対策を講じています。
保険金請求に疑わしい点がある場合、保険会社は詳細な調査を行う権限を有しています。
この調査過程で時効の中断事由となる行為を行うことで、時効を防ぐのです。
保険契約には通常、保険金請求に関する調査への協力義務が定められています。
被保険者がこの義務に違反した場合、それ自体が契約違反となり、保険金支払いの拒否事由になることもあるのです。
保険会社が行う調査には、以下のような手法があります。
- 事故状況の確認
- 医療記録の精査
- 関係者への聞き取り
- 専門家鑑定など
なお、「日本損害保険協会」という、不正受給に対して警告を鳴らしている機関があります。
保険会社同士で詐欺情報を共有し、複数の保険会社にまたがる詐欺行為を発見しやすくし、時効前に対処できる体制を整えています。
保険金詐欺の時効問題は複雑であり、単に年数だけで判断できるものではありません。
時効の進行開始時期や中断事由、停止事由などの細かい法的判断が必要となることが一般的です。
そのため、時効が成立したかどうかは、最終的に裁判所の判断に委ねられることになります。
よくある質問

保険金詐欺に関してはさまざまな疑問が寄せられます。
保険契約の再加入可能性や詐欺未遂の罰則、不正の疑いをかけられた場合の対応など、実務的な問題について法的観点から回答します。
保険金詐欺がバレた後、再加入は可能か?
保険金詐欺が発覚し、保険契約を解除された後でも、再度保険への申込自体は可能でしょう。
しかしながら、新規加入審査を受ける必要があり、過去の詐欺行為がこの審査に影響する可能性が高いと考えるべきでしょう。
保険会社が行う審査とは、保険加入条件を満たしているかどうかを確認することです。
これは保険金詐欺の有無に関わらず、すべての新規契約において行われます。
しかし過去に詐欺行為を行った人物は、保険会社のブラックリストに載っている可能性があり、審査で不利になることが予想されます。
例えば、過去に健康状態が良好で保険加入条件を満たしていた人が、保険加入後に大病を患い、保険金を正当に受け取ったとします。
その後に別の保険で詐欺行為を行い、契約を解除されたケースを考えてみましょう。
この場合、新たに保険契約を申し込んでも、過去の大病歴や詐欺歴が理由で加入を断られる可能性があります。
さらに再加入で大きな壁となるのは、保険業界内における情報共有システムの存在です。
日本損害保険協会の保険金不正請求通報制度により、保険会社間で不正請求に関する情報が共有されています。
一般的な保険会社だけでなく、共済事業を行う協同組合なども参加しており、一度詐欺行為を行うとほぼすべての保険会社での契約が困難になる可能性があります。
結論として、保険金詐欺がバレた後の再加入は理論上可能でも、実際には非常に難しいと考えるべきでしょう。
保険金詐欺未遂でも逮捕されるのか?
保険金詐欺未遂でも逮捕される可能性は十分にあります。
刑法第250条では「詐欺罪の未遂は罰する」と明確に規定されており、法定刑は詐欺既遂と同じ「10年以下の懲役」です。
ただし、未遂の場合は刑罰が軽減される傾向があります。
詐欺未遂罪が成立するのは、欺罔行為(相手を騙す行為)があった時点からです。
つまり、保険会社に対して嘘の事故報告等をして保険金を詐取しようとした時点で、詐欺未遂罪が成立します。
たとえ保険会社が報告内容を疑って保険金を支払わなかったとしても、詐欺未遂罪として刑事罰の対象となり得るのです。
逮捕のリスクについては、詐欺の金額や悪質性、計画性などが考慮されます。
たとえば、未遂で終わった場合、保険金の支払いが行われていないため被害額はゼロとなります。
しかし、それでも犯罪行為として処罰される可能性もあるのです。
特に計画性が高いケースや、過去に類似の行為を繰り返している場合は、未遂であっても厳しく処罰される傾向にあります。
軽い気持ちで保険金詐欺に手を染めようと思っている人は、未遂であっても刑事責任を問われる可能性があることを認識すべきです。
また、未遂でも保険契約が解除される可能性が高く、将来的な保険加入にも影響することを理解しておきましょう。
保険金詐欺の疑いをかけられたらどうする?
保険金請求をして、詐欺を疑われた場合、落ち着いて対応することが重要です。
まず理解すべきは、保険会社が保険金詐欺を疑うのには何らかの理由があるため、その原因を把握しましょう。
詐欺の事実がないのであれば、焦らずに正当な保険金請求であることを証明すべきです。
具体的な対応方法としては、保険会社が指定する業者で見積もりを取り直したり、自動車安全運転センター等で事故証明を取得したりなど、客観的な事実を証明する書類の準備が効果的です。
また、保険会社からの質問には、誠実に対応し、説明には一貫性をもたせましょう。
疑いが晴れない場合や、保険会社の対応に納得できない場合は、弁護士への相談も検討すべきです。
保険金請求は契約に基づく正当な権利であり、不当に拒否されている場合は法的手段を取ることも可能です。
特に自動車保険の場合、弁護士費用を補償する弁護士特約が付いていることも多く、こうした状況での法的対応をサポートしてくれる場合があります。
保険金詐欺の疑いをかけられた場合に避けるべき行動としては、怒りや焦りから保険会社の担当者に感情的に接することや、事実と異なる説明を追加することなどが挙げられます。
こうした行動は疑いを深める原因となり、保険会社との関係悪化につながりかねません。
結果として、解決を遅らせることにつながります。
大切なのは、保険金詐欺を行っていないのであれば、客観的な証拠と一貫した説明で自分の正当性を主張することです。
正当な証拠があれば、保険会社も保険金の支払いに応じるでしょう。
工事業者が「火災保険を利用できる」と言ってきた場合の対応は?
工事業者から「火災保険を利用できる」と持ちかけられても、相手の話を鵜呑みにしないようにしましょう。
自然災害による被害は火災保険でカバーされても、経年劣化による損傷は補償対象外となることが一般的だからです。
実際に保険適用可能かどうかは自分で確認しましょう。
この状況で注意すべきなのは、一部の業者が経年劣化を自然災害による被害と偽って保険金を請求するよう勧める「保険金詐欺」に誘導するケースがあることです。
このような詐欺に加担してしまうと、業者だけでなく依頼主も詐欺罪に問われる可能性があります。
国民生活センターによると、「保険金が使える」とうたう住宅修理サービスに関するトラブルが増加しており、特に高齢者が被害に遭うケースが多いと報告されています。
こうした業者は「保険金がおりるため自己負担はゼロ」などと勧誘しますが、実際には経年劣化分は補償されず、結果的に自己負担が発生したり、保険金詐欺に加担させられたりするケースが少なくありません。
適切な対応としては、まず自身が加入している保険会社に連絡し、被害状況や補償範囲について確認することをおすすめします。
保険会社の担当者に現状を説明し、必要に応じて調査を依頼しましょう。
また、複数の工事業者から見積もりを取り、不自然に高額な見積もりや「保険金が確実に下りる」と断言する業者には注意が必要です。
家の持ち主であれば、いつ頃からその破損があったかを把握しているはずです。
自然災害と関連付けられない破損について保険金を請求することは詐欺行為となり得るため、正直に状況を報告し、適切な対応を取ることが重要です。
保険金請求の際に気をつけるべきポイントは?
保険金請求を行う際には、いくつかのポイントを押さえておくことで、不正請求と疑われるリスクを減らし、スムーズに手続きを進められます。
まず事故や被害の正確な記録を残すことが重要です。
事故現場の写真、被害状況の詳細な記録、発生日時の記録など、客観的な証拠を可能な限り収集しておきましょう。
特に自動車事故の場合は、事故状況の写真、相手方の情報、目撃者の証言なども記録しておくと役に立ちます。
次に、保険会社への報告は迅速かつ正確に行うことが重要です。
保険契約には事故報告の期限が設けられていることが多く、報告が遅れると保険金の支払いに影響が出る可能性があります。
また、報告内容には事実のみを伝え、嘘や誇張した情報を含めないよう注意しましょう。
ささいな嘘でも後々矛盾が生じ、不正請求と疑われる原因となることがあります。
医療関連の保険金請求では、信頼できる医療機関を選び、医師の指示に従った適切な治療を受けることが大切です。
保険金詐欺を疑われないためにも、保険会社から疑いを持たれている医療機関や、整骨院を利用するのは避けましょう。
特に、整骨院での治療は、事前に医師の同意を得ることが望ましいです。
また、医師の指示通りの通院ペースを守ることで、不正請求を疑われるリスクを減らせます。
見積書や診断書などの書類は、正確な内容であることを確認してから提出しましょう。
水増しされた見積書を提出すると、詐欺行為と見なされる可能性があります。
最後に、保険金請求の過程で不明点があれば、保険会社の担当者に質問することをためらわないでください。
保険の契約内容や請求手続きを正しく理解することで、誤解や不正請求の疑いを避けられます。
これらのポイントに注意して正当な保険金請求を進めれば、不要な調査や疑いを回避できるでしょう。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
保険金詐欺は「保険会社を騙して金銭を詐取する行為」であり、刑法上の詐欺罪として10年以下の懲役に処せられる重大な犯罪です。
未遂でも罪に問われ、発覚すれば逮捕・起訴され、社会的信用を失うリスクがあります。
また、不正受給した保険金の全額返還を求められるだけでなく、保険契約も解除されるため、今後の保険加入に支障が出る可能性があります。
刑事責任での公訴時効は7年ですが、民事上の責任は最長20年間残ります。
一時的な金銭的利益を得るための犯罪行為が、長期にわたる人生の損失につながることを認識し、決して行わないようにしましょう。

足立高志 弁護士
大本総合法律事務所
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-1-1
大手町パークビルディング8階
tel 03-5224-4555
fax 03-5224-4556
mail adachi@omoto.top
【経歴】
中央大学法学部卒
2007年弁護士登録
中小企業から個人の方まで幅広く対応しております。過去は変えられませんが、より良い未来となるよう、手助けができればと思っています。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










