突然警察から連絡が来て事情聴取を求められた…
家族が逮捕されてしまった…
刑事事件の容疑者として呼び出しを受けた…
そんな緊急事態に直面したとき、多くの方が『私選弁護人と国選弁護人、どちらを選ぶべきか?』『弁護士費用が高額で払えるか不安』『すぐに対応しないと取り返しがつかないのでは?』といった疑問や不安を抱くのではないでしょうか?
刑事事件では早期の弁護活動が結果を大きく左右するため、可能な限り私選弁護人を選ぶことをおすすめします。
私選弁護人は逮捕前からでも依頼でき、自分で弁護士を選べるため、経験豊富で信頼できる弁護士による質の高い弁護活動を受けることができます。ただし、費用面で困難な場合は国選弁護人でも基本的な弁護は受けられます。
本記事では、私選弁護人と国選弁護人の違い、それぞれのメリット・デメリット、選択の判断基準について、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブル(一般事件)に遭遇したときの弁護士費用を最大100%補償。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
私選弁護人と国選弁護人の基本的な違い

刑事事件の弁護人(弁護士)には、大きく分けて私選弁護人と国選弁護人の2種類があります。
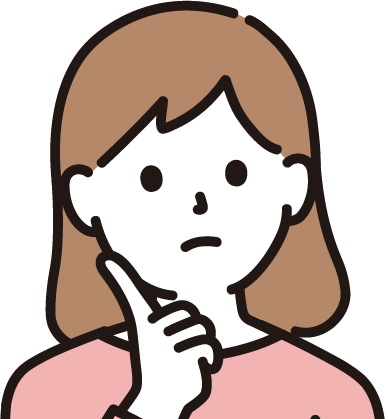
そもそも、私選弁護人と国選弁護人の違いが分からないです…。
 弁護士
弁護士ざっくり解説すると、自分で選んだ弁護人なのか国から選ばれた弁護人なのかの違いです。
選任方法や費用負担、依頼のタイミングなどの違いを理解し、状況に応じた選択をしましょう。
私選弁護人とは?
どのような立場でも弁護士との契約は自由に行えるため、例えば刑事事件の経験が豊富な弁護士を選ぶ、ということも可能です。
また、弁護活動は契約に基づいて行われるため、依頼者への報告や連絡が頻繁に行われ、より手厚いサポートを受けられる傾向にあります。
事件の状況に応じて、示談交渉や早期釈放に向けた活動など、きめ細かな対応が期待できるでしょう。
国選弁護人とは?
国選弁護人を依頼するには、資産要件として現金および預金が50万円未満である必要がありますが、原則として、弁護士費用はかかりません。
国選弁護人は法テラスに登録された弁護人の中から機械的に選ばれるため、被疑者・被告人が希望する弁護人を指名することはできません。
また、原則として一度選任された国選弁護人を変更することもできませんが、私選弁護人への切り替えは可能です。
なお、弁護活動の内容は私選弁護人とほぼ同じですが、家族への報告義務がないため事件の進行状況が当事者・家族ともに把握しづらい場合があります。
弁護人選任のタイミングにおける違い

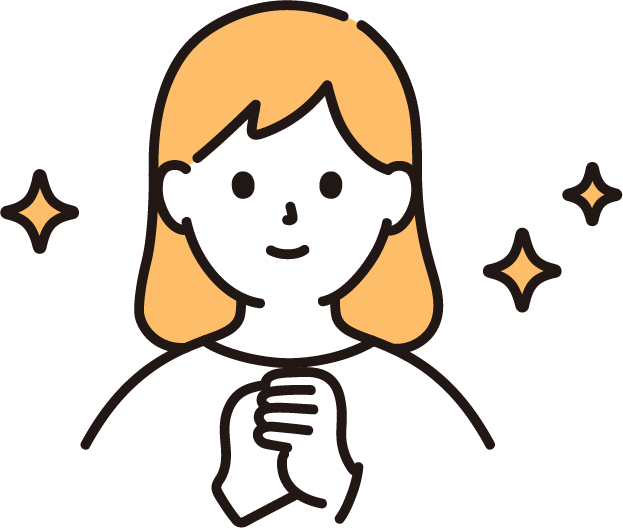
私選弁護人でも国選弁護人でも、裁判が始まる前に依頼すればいいのですね!
 弁護士
弁護士お待ちください。私選弁護人と国選弁護人では、選任できるタイミングが大きく異なります。
それぞれのタイミングや、逮捕前に依頼するメリットなどについて以下で解説します。
私選弁護人はいつでも依頼できる
私選弁護人に依頼できる時期は、特に決められていません。
例えば逮捕前に依頼した場合は、相手と和解を成立させることで逮捕を回避できる場合もありますし、逮捕直後に依頼した場合は、早期釈放の実現も期待できるでしょう。
また、任意の事情聴取を受けている段階や、在宅事件の場合でも私選弁護人に依頼できます。
すでに国選弁護人が付いている場合でも、私選弁護人への切り替えは可能です。
国選弁護人は勾留後に選任される
国選弁護人の選任には、時期的な制限があります。
原則として、国選弁護人は、勾留されてからでないと選任できません。
ただし、当番弁護士制度なら、勾留前から利用できます。
なお、在宅事件や示談による事件化防止が必要な場合など、身体拘束を受けていない事案では、国選弁護制度を利用できません。
このため、早期の法的対応が必要な場合は、私選弁護人を選任する必要があります。
「当番弁護士」と「国選弁護人」の違いについて
当番弁護士は、逮捕期間中(72時間以内)に、原則費用負担なしで利用でき、一度の接見だけを行う制度です。
国選弁護人は、逮捕期間(72時間)後、勾留された時等に、弁護活動をおこなってくれる制度です。
逮捕前に弁護人を依頼するメリットとは?
逮捕前から弁護人に依頼することは、さまざまな利点があります。
特に、刑事弁護はスピードが命です。
早期の弁護活動により、逮捕を回避しやすくなるでしょう。
さらに、弁護人から取調べに関する法的アドバイスを受けることで、不用意な供述を避けられます。
また、示談交渉を早期に開始することで、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
弁護人を選ぶ自由と制限

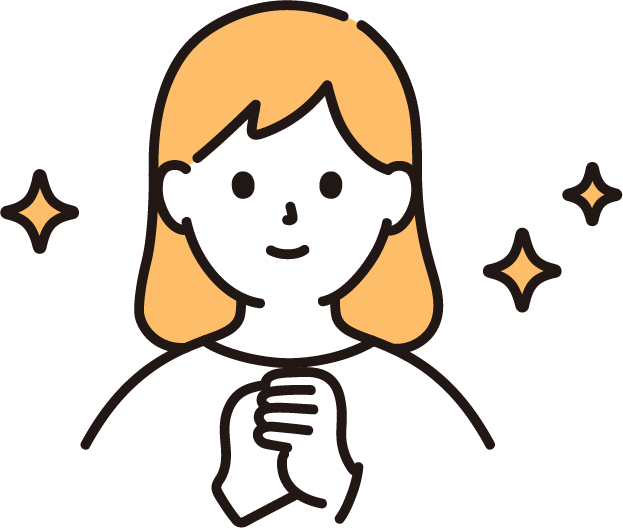
できれば、弁護人は自分と同性で、年が近い方にお願いしたいです!
 弁護士
弁護士弁護人の選任方法によって、依頼できる弁護人の選択範囲が大きく異なりますので注意してください。
私選弁護人の場合は自由な選択が可能である一方、国選弁護人は選択の余地がありません。
私選弁護人は自分で選べる
私選弁護人の場合、依頼者自身が依頼する弁護人を選べます。
具体的には、インターネットで探したり、自宅から近い弁護士事務所を選んだりと、自由な条件で選択可能です。
また、一度依頼した私選弁護人との相性が合わない場合や、思うような活動をしてくれない場合は、契約を解除して別の弁護人に依頼できます。
複数の弁護人に相談してから検討できるため、より信頼できる弁護人を選べるメリットがあります。
国選弁護人は選ぶことができない
国選弁護人は、国(裁判所)によって選任されるため、希望の弁護人は指定できません。
どのような弁護人が選任されるかは完全な運任せです。
また原則として、一度選任された後に変更することもできません。
なお、国選弁護人から私選弁護人への変更すること自体は認められています。
一方で、私選弁護人の選任以外で、国選弁護人の解任はほぼ認められないのが実情です。
弁護人の経験や専門性の違い
刑事事件では、弁護人の経験値が裁判の結果に影響するといっても過言ではありません。
国選弁護人の場合、必ずしも刑事弁護の経験が豊富とは限らず、時には専門分野外の弁護人が担当することもあるのです。
一方、私選弁護人の場合は、刑事事件に特化した弁護人や豊富な経験を持つ弁護人を選んで依頼できます。
そのため、示談交渉の進め方や検察との交渉など、経験に基づいた効果的な弁護活動が期待できるでしょう。
弁護士費用の違い


弁護人の選任は、費用面においても重要な検討要素ですね。あまり予算がないので弁護人を付ける余裕がないかもしれません…。
 弁護士
弁護士安心してください。私選弁護人は依頼者が費用を負担する必要がある一方、国選弁護人は原則として費用負担がありません。
私選弁護人の費用構造(着手金・報酬金)
私選弁護人の費用は、60万円から200万円が相場です。
この費用の内訳は、以下の通りです。
| 着手金 | 30~50万円 |
| 報酬金 | 30~80万円 |
| 日当 | 3~5万円 |
| その他実費 | ~数千円 |
着手金は、事件の結果にかかわらず、弁護活動を開始する際に必要となるものです。
一部の事務所では分割払いにも対応していますが、多くの事務所では、契約時に一括払いを求めています。
報酬金は事件の結果に応じて変動する可能性があり、示談成立や不起訴処分獲得などの成果に連動します。
また、弁護士費用とは別に、保釈金や示談金などまとまった金額が必要となるケースもあるため、事前に費用の見通しを立てておくことが重要です。

国選弁護人の費用負担について
国選弁護人は、原則として費用負担が不要です。
しかし、「現金と預金が50万円未満」という資力要件を満たす必要があります。
弁護士費用が弁護人の選択に与える影響
弁護士費用の違いは、依頼者の選択において大きな影響を与えます。
特に、逮捕直後は仕事ができず収入が途絶える中で、弁護士費用を捻出することは容易ではありません。
万が一、事件の被害者がいる場合は、弁護士費用だけでなく、賠償金や示談金がかかるケースもありえます。
そのため、弁護人を選ぶ際は、依頼費用だけでなく、総合的な費用を考慮した上で選択するべきです。
私選弁護人の弁護士費用が高く感じても、早期解決や不起訴獲得によって長期的には有利な結果につながる可能性もあります。
弁護活動の質と対応の違い

私選弁護人と国選弁護人では、基本的な弁護活動の内容は同じですが、実際の対応や活動の質に、違いが生じることもあります。
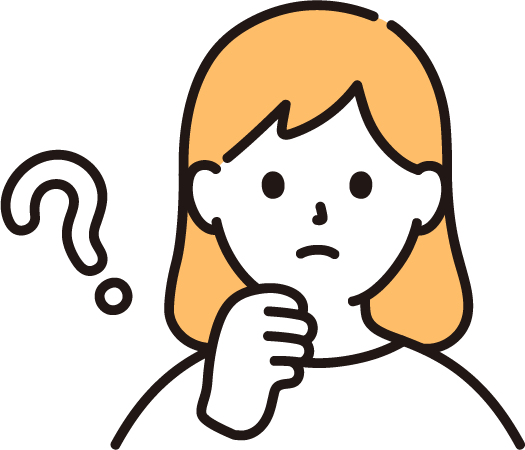
案件としては一緒なのに、そこまで違いが出るものなんですか?
 弁護士
弁護士対応や活動の違いについては、依頼者との契約関係の有無、弁護人の経験、専門性などから生まれます。
私選弁護人による個別対応と頻繁な連絡
私選弁護人は、依頼人から弁護費用をもらって委任を受けています。
そのため、当事者や家族へ頻繁に状況を報告してくれるでしょう。
特に、家族が逮捕勾留され、弁護人しか面会できないケースでは、弁護人からの定期的な連絡が家族の大きな支えとなるはずです。
また、私選弁護人は依頼者との契約に基づいて活動するため、接見の回数や示談交渉の進め方など、具体的な内容の説明を受けたうえで契約できます。
また、検察官の鋭い質問を想定した裁判のシミュレーションや、依頼者の気持ちを丁寧にくみとるなど、状況に合わせたベストな法廷弁護活動が期待できるでしょう。
国選弁護人の対応における限界
国選弁護人は活動内容を報告する義務がないため、進行状況の把握が難しい場合もあります。
「別の案件で多忙である」ということを理由に、連絡をこまめにしないケースも少なくありません。
そのため、状況を理解できず、家族や当事者でさえ不安を抱えることもあります。
また、国選弁護人の弁護士報酬は、私選弁護人と比べて安いといわれており、当事者やその家族との契約に基づいて決められるわけではありません。
そのため、私選弁護人と比較して、弁護活動の積極性や熱意に差が出る可能性があります。
不起訴や早期釈放の実現可能性の違い
日本の刑事司法では、起訴後の有罪率は99.9%といわれています。
不起訴処分を獲得するためには、まず、起訴前に弁護人が相手方と示談する必要があります。
そのうえで、本人を更生させるためのサポート体制を整えたり、社会復帰に向けた具体的なプランを検察官へ提示したりすることが不可欠です。
早期からの弁護活動が可能な私選弁護人は、意見書を提出して勾留を防ぐことで、社会的影響を可能な限り抑えます。
一方、国選弁護人は選任のタイミングが遅くなるため、このような早期対応が難しい場合があります。
刑事事件における私選弁護人のメリット

刑事事件では、早期から適切な法的対応を取る必要があります。

私選弁護人の方が、早い段階から動いてもらうことが可能なんですね。
 弁護士
弁護士起訴前から依頼できる私選弁護人を選任することで、逮捕前からの法的支援や示談交渉、さらには不起訴処分の獲得など、有利に進められる可能性が広がります。
示談交渉や早期釈放に向けた活動ができる
示談は当事者間でも可能ですが、刑事事件の示談は刑事弁護の経験豊富な弁護人を間に入れて行うべきです。
なぜなら、示談交渉が不適切な方法で行われると新たな法的問題を引き起こす可能性があるためです。
私選弁護人は、示談書の作成から検察官への示談結果の報告まで、一貫して対応できます。
示談の効果を得るためには示談書に適切な内容を盛り込むこと、示談の結果を検察官へ十分に伝えることが必要です。
経験豊富な弁護人を選ぶことができる
刑事事件の場合、これまでの経験値が弁護活動に反映されます。
加害者弁護の経験が豊富な弁護人であれば、釈放を請求するタイミングや示談の進め方、検察や裁判官との交渉などを進めてくれるでしょう。
また、長年の経験があれば、専門知識が深く、複雑な法律問題にも対応できます。
過去の経験から、予期せぬ事態が発生した場合でも、柔軟に対応してもらえる可能性も期待できるでしょう。
早期の弁護活動が重要な理由について
刑事事件の早い段階から弁護活動を進めてもらえることは、私選弁護人を選ぶうえでの大きなメリットです。
特に、一度作られた調書を覆すことは優秀な弁護人でも困難だといわれています。
そのため、取調べの初期段階からの法的アドバイスは被疑者の権利を守り、不利な状況に陥ることを防ぐうえで、非常に重要といえるでしょう。
初期段階で適切に対応すれば、事件の相手方と示談を締結して逮捕を防げる可能性が高くなります。
また逮捕されてからすぐに依頼することができれば、早期釈放が実現しやすくなるでしょう。
早期の弁護活動は、被疑者の社会生活や雇用関係を維持する上で、精神的な負担を軽減する効果も期待できます。
刑事事件に巻き込まれることは大きなストレスとなりますが、弁護人のサポートがあれば、一人で抱え込むことなく冷静に対処できるでしょう。
私選弁護人を選ぶ際のポイント

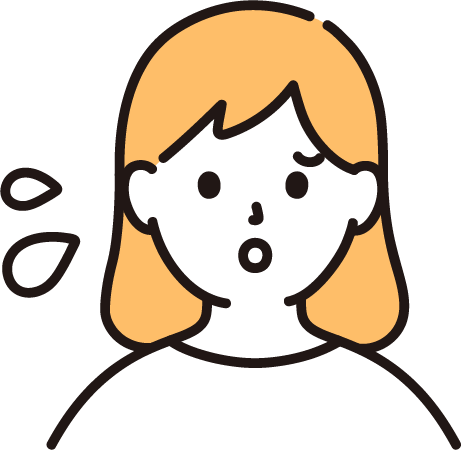
私選弁護人のメリットは分かりましたが、どのように選んだらいいのか…。
 弁護士
弁護士いくつかのポイントをお伝えするので、参考にしてみてください。
私選弁護人の選任は、刑事事件の結果を大きく左右しますが、同時に多額の依頼費用がかかります。
経験と専門性、費用の透明性や相性など、複数の観点から慎重に検討し、最適な弁護人を選びましょう。
専門分野と実績を確認する
大半の弁護士事務所がホームページを持っています。
まずは、ネット検索してできるだけ早く法律相談を受け、説明が分かりやすく信頼できる弁護人へ依頼するのがおすすめです。
また、「(居住地の都道府県) 弁護士会」と検索すると、各地域の弁護士会のサイトが出てきます。
ここから弁護人の検索や相談窓口の案内・予約が可能なので、一度見てみるとよいでしょう。
刑事事件の実績や専門性は、弁護人を選択するうえで重要な判断材料となります。
法律相談では、弁護人の説明の分かりやすさや、これまでの刑事弁護の経験、具体的な解決実績などを確認しましょう。
弁護士費用を確認する
相談時の説明やホームページの記載では費用が安くても、曖昧な契約では結果的に高額となる場合もあるため、費用体系を必ず確認しましょう。
具体的なチェックポイントは以下のとおりです。
- 着手金
- 報酬金
- 実費
- 日当など
契約後に追加費用がないか、ある場合はいくらかかるのかを明確な金額を提示してもらいましょう。
また、分割払いが可能な場合でも、保釈金の納付や示談金の支払いなど、急に大金が必要になるケースもあるため、総額の見通しを立てる必要があります。
予期せぬ出費を避けるためにも、契約前に詳細な費用を確認しましょう。
弁護人との相性を重視する理由
弁護人との相性は、私選弁護人を選ぶうえで非常に重要です。
長期にわたる刑事事件は、人生を大きく左右する深刻な問題です。
心から信頼できる弁護人でないと、依頼者は事実や思いを正直に伝えられず、最適なアドバイスやサポートが受けられない可能性があります。
初回相談の段階から、親身になって依頼者や家族の話を聞いてくれる弁護人は、事件解決まで責任を持って最善の結果となるよう努めてくれるはずです。
また、親身になってサポートしてくれる弁護人に依頼していると、家族の不安も軽減できます。
刑事事件では、被疑者・被告人やその家族が大きな不安を抱えているため、信頼関係を築ける弁護人を選ぶことが重要です。
私選弁護人と国選弁護人、どちらにすべきか?

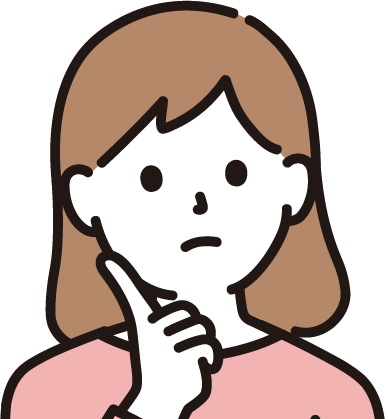
費用が掛かるけど親身になってくれる私選弁護人か、対応に不安があるけど費用が掛からない国選弁護人か…。
 弁護士
弁護士刑事事件において、弁護人選びは事件の結果を大きく左右する重要な決断です。
ここでは弁護人の選び方について見てみましょう。
どちらを選ぶべきか?ケース別の選び方
以下のような考えの場合、私選弁護人を選んだほうがよいでしょう。
- 自分で直接、信頼できる弁護人を選びたい
- 会社に逮捕された事実を知られたくない
- 絶対に不起訴処分を獲得して前科をつけたくない
- 都度、弁護人から活動の報告を受けて、状況を把握したい
一方で、どうしても弁護士費用の負担ができない場合は、国選弁護人を選びましょう。
この場合、弁護人と積極的にコミュニケーションをとり、必要に応じて家族からも連絡を取ることで、より依頼者に寄り添った弁護活動を期待できます。
国選弁護人から私選弁護人への切り替え方法
国選弁護人から私選弁護人に切り替えたい場合は、私選弁護人を選任するだけで手続きは完了します。
私選弁護人を選任すると、その弁護人が検察庁や裁判所に弁護人選任届を提出し、これによって、国選弁護人は自動的に解任されます。
 弁護士
弁護士起訴前に私選弁護人を選任した場合は、裁判官が国選弁護人を解任します。
また、起訴後の場合、解任するのは裁判所です。依頼者側で、特別な手続きを取る必要はありません。
切り替えの理由として多いのは、「国選弁護人から連絡がないことに不安を感じたこと」です。
当事者や家族が状況を把握しないまま進んでいくよりも、適切な情報共有ができる私選弁護人に切り替えることで、より安心して諸手続きを進められるでしょう。
よくある質問

 弁護士
弁護士刑事事件における弁護人選任について、疑問や不安を抱えている方は多くいます。
ここでは、特に多い質問について回答するとともに、選任の際の重要なポイントをまとめます。
国選弁護人の選任基準は?
国選弁護人を選任する条件には、明確な基準があります。
現金と預金が50万円未満という資力要件を満たさなければなりません。
また、勾留状が発せられていることも条件となります。
国選弁護人は、国選弁護人として登録された名簿の中から機械的に選ばれます。
国選弁護人は弁護士会の国選名簿に登録されれば、誰でもなれます。
経験年数や取り扱った事件の数などで登録の制限を受けることはありません。
 弁護士
弁護士そのため、国選弁護人になる人は、刑事弁護の経験が豊富な人から全く経験のない人まで、さまざまです。
私選弁護人の依頼が難しいケース
私選弁護人への依頼が難しいのは、主に経済的な理由が挙げられます。
弁護士費用以外にも、賠償金や示談金がかかる場合もあり、事件終了までの総合的な費用となると、予算を大幅にオーバーしてしまうケースも少なくありません。
また、刑事事件に巻き込まれたら気が動転してしまい弁護人を探すほどの余裕がない、選び方がわからないというケースも多く見られます。
このような場合は、逮捕された人が無料で弁護人の助けを受けられる「当番弁護士制度」を利用し、その後の対応を検討することも一つの選択肢です。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブル(一般事件)に遭遇したときの弁護士費用を最大100%補償。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
刑事事件における弁護人の選択は、事件の結果を大きく左右します。
私選弁護人は早期からの対応や弁護人選択の自由がある一方で、費用負担が必要です。
一方、国選弁護人は費用負担が原則不要ですが、選任時期や選択要件において、制限があります。
刑事事件において結果の命運を分けるのは、初動の早さです。
弁護人への依頼が早ければ早いほど、対応できる内容は多くなります。
ただし、経済的な理由で私選弁護人の選任が難しい場合は、国選弁護人の選任が賢明な選択となります。
また、国選弁護人から私選弁護人への切り替えは随時可能ですので、状況に応じて柔軟に対応できます。
重要なのは、できるだけ早い段階で弁護人に相談し、適切な法的サポートを受けることです。
「もしも」に備えて、この記事が一助になれば幸いです。

水島昂 弁護士
東京弁護士会所属
弁護士法人小林綜合法律事務所
東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館2階
電話 03-6212-5201
正確な法律論を提示するだけでなく、柔軟な発想でご相談者の方々の立場・状況に沿った解決策を提案できるよう、心がけております。
事件の大小にかかわらず、どんなことでもお気軽にご相談下さい。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










