「仕事中にケガをしたのに、会社から『労災は使わないでほしい』と言われた」「通勤中の事故について、会社が労災の手続きをしてくれない」「職場でのケガを『自己責任』として処理された」など、労働者が本来受けられるはずの労災保険の適用を拒否された場合、『これは労災かくしなのか?』『どう対処すればいいのか?』と悩む方も多いでしょう。
労災かくしとは、労働者に多大な不利益を与える違法行為です。
労働者は本来、労働中や通勤中に発生した事故や病気について労災保険の補償を受ける権利があり、会社がこれを隠蔽したり妨害したりすることは許されません。
本記事では、労災の基本的な知識から労災かくしの実態、その対処法や予防策について、詳しく解説していきます。
「弁護士に相談なんて大げさな・・・」という時代は終わりました!
経営者・個人事業主の方へ
そもそも労災とは?


そもそも「労災」についてあまり詳しくないです…。
 弁護士
弁護士労災とは「労働災害」の略称です。
労働者が業務中に負った怪我や病気、通勤中に起きた事故などを補償する制度が「労災保険制度」で、正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。
労災は以下の2種類に分類されます。
- 業務労災
- 通勤災害
労災保険制度は、事業主が負担する保険料によって賄われる公的な労働保険制度の一つです。
業務災害とは
業務災害とは、業務が原因でケガや病気、障害や死亡が発生することです。
通勤災害とは異なり、「業務遂行性」を満たしたうえで、「業務起因性」も認められなければなりません。
 弁護士
弁護士精神疾患の場合、過労の蓄積や過酷な労働環境など業務が一因となっていると認められれば、業務起因性として認定されます。
しかし、個人的な要因が主たる原因の場合は、認められにくくなります。
通勤災害とは
通勤災害とは、通勤によって起こるケガ・病気・障害・死亡のことを指します。
厚生労働省では、「通勤」について以下のように定めています。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、(1)住居と就業場所との間の往復、(2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動、(3)就業場所から他の就業場所への移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。
厚生労働省 青森労働局「業務災害・通勤災害について」
つまり、自宅と事業所との間の最短経路を通常に往復している間に発生した災害が通勤災害と認められるというわけです。
たとえば、会社から業務を遂行する作業場まで行く途中で事故にあった場合は、通勤災害と認められる可能性が高いです。
一方で、会社へ行く前に子どもを保育園へ預けようとした場合は「通勤」ではないため、送迎中に起きた事故は、通勤災害と認められないでしょう。

労災保険とは


では、労災保険というのは、業務上または通勤途中で発生したケガ・病気・障害・死亡に対し、保険金を給付する制度のことですね。
 弁護士
弁護士この保険金は労働者本人だけでなく、場合によっては遺族へ支払われることもあります。
労災保険の主な給付内容
労災保険の給付内容は、主に以下の8種類です。
療養(補償)給付
療養補償給付では、治療に必要な「治療」や「費用」を支給します。
「治療」が支給された場合は、労災病院や労災指定病院等にかかった際、無料で療養できます。
一方、「費用」は労災病院や労災指定病院以外で療養した場合に、費用を受け取れるものです。
休業(補償)給付
休業補償給付では、労働者が休業した場合の収入減を補償する給付金です。
原則として、賃金の支払いが止まった日の第4日目から支給されます。
休業1日につき、日額の60%が給付金として支給されます。
また、給付基礎日額(災害が発生した日の以前3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額)の20%も、特別支給金として支払われます。
障害(補償)等年金
労災によるケガや病気が原因で、身体に一定の障害が残った場合に支払われる給付金です。
障害(補償)等年金には2種類あります。
傷病(補償)給付
傷病補償給付は、療養開始後から1年6ヶ月経過しても治癒せず、障害が残った場合、等級に応じて給付されます。
等級と支給金は以下のとおりです。
| 傷病等級 | 傷病(補償等)年金 | 傷病特別支給金(一時金) | 傷病特別年金 |
| 第1級 | 給付金基礎日額の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 給付金基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 給付金基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |
遺族(補償)等給付
遺族補償給付は、業務中または通勤途中に労働者が死亡した場合、遺族へ給付されます。
給付には2種類があり、一つ目は遺族(補償)年金です。
| 遺族数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金 (一時金) | 遺族特別年金 |
| 1人 | 給付基礎日額の153日分 (55歳以上又は障害がある妻の場合は175日分) | 300万円 | 算定基礎日額の153日分 (55歳以上又は障害がある妻の場合は175日分) |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
二つ目は、遺族(補償)一時金です。
| 条件 | 遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 (一時金) | 遺族特別一時金 |
| 受給資格者がいない場合 | 給付基礎日額の1,000日分 | 300万円 | 算定基礎日額の1000日分 |
| 受給権者全員失権後、合計額が1,000日分に達していない場合 | 給付基礎日額の1,000日分と合計額との差額 | 算定日額の1,000日分と合計額との差額 |
葬祭料等給付
葬祭料等給付は、労働者が死亡した場合に葬儀費用を支給するものです。
葬祭給付の金額は、31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額となります。
なお、上記の額が給付起訴日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が給付額となります。
介護(補償)給付
労災によって、労働者が介護の必要な状態になった場合、介護(補償)給付が支払われます。
給付金の内容は以下のとおりです。
- 最高限度額:常時介護を要する者:17万7,950円
- 最高限度額:随時介護を要する者:8万8,980円
- 最低保障額:常時介護を要する者:8万1290円
- 最低保障額:随時介護を要する者:4万600円
二次健康診断等給付
二次健康診断等給付とは、職場の定期健康診断等にて異常が認められた場合、脳血管・心臓の状態の検査や特定指導を無料で1年度内に一度受けられるものです。
給付の要件は以下のとおりです。
- 一時健康診断の結果、以下4つすべての異常が認められる
- 血圧検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
- 脳・心臓疾患の症状がない
- 労災保険の特別加入者でない
労災保険の加入義務
労働者1人以上を使用する事業主は、労災保険への加入が義務付けられています。
雇用保険は、労働者の労働時間や雇用形態によって対象にならない場合もありますが、労災保険の場合、労働時間は関係ありません。
 弁護士
弁護士常勤・パート・アルバイトにかかわらず、必ず加入しなければならないと法律で定められています。
労災保険料を支払うのは誰?
労災保険料は、事業主が全額負担します。
雇用保険のように、労働者が半額負担することはありません。
労災かくしとは?


労災かくしとは、どのような状態のことを指すのですか?
 弁護士
弁護士労働災害が発生したにもかかわらず、労働基準監督署へ報告しなかったり、労災に関する虚偽の報告書を提出したりすることが、労災かくしです。
労災かくしは、被災した労働者にとって、大きなデメリットとなります。
必要な補償を受けられず、治療費や休業中の収入の補償を受けられない可能性があります。
また、後遺症が残った場合も適切な補償を受けることができません。
労災かくしがおこなわれる主な理由
労災かくしはさまざまな理由によっておこなわれます。
経済的な負担がかかるから
前述のとおり、労災保険は事業主が全額負担しており、労災事故の発生状況によっては保険料が上がる可能性があるため、労災かくしが行われることがあります。
中小企業などでは保険料負担の増加により経営を圧迫する恐れがあるため、労災かくしに繋がってしまうケースも。
また、治療費や休業補償費の負担も挙げられます。
労災認定を受けると、事業主は治療費や休業補償費を負担しなければなりません。
特に、休業期間が長期間に及ぶ場合や、後遺症が残った場合の補償負担は大きくなります。
面倒な手続きを避けたいから
労災保険の請求には、労働災害発生届、診断書、休業証明書など、さまざまな書類が必要となります。
これらの書類の作成には、専門知識が必要となる場合もあります。
また、労災が起きれば検証作業も必要となってくるため、事業主としては面倒な手続きを避けたいと考えてしまうのです。
書類作成や提出には、時間と労力がかかります。
特に、人手不足の事業所では、手続きを負担に感じるケースがあります。
会社の評判を落としたくないから
労災事故が発生すると、会社の評判が落ち、顧客や取引先を失う可能性があります。
特にサービス業や接客業では、会社のイメージが重視されるため、労災かくしに繋がるケースもあるのです。
また、労災事故は会社の安全衛生管理に問題があると受け取られかねず、それが労災かくしの要因にもなっています。
万が一、顧客や取引先が、安全性を重視する傾向にある場合、労災事故を理由に契約を解除される可能性もあります。
労災保険法では、労働災害発生時の報告義務が定められています。
しかし、中には事業主が法令を理解していないために、意図的ではなく労災かくしをしてしまうケースもあるのです。
また、労災保険に未加入の事業者も存在します。
事業者は法令を理解し、適切な対応をすることが求められます。
労災かくしの事例紹介
過去に、労災かくしをおこなった企業について紹介します。
事例1建設業における労災かくし
長野県飯田市のリニア中央新幹線トンネル工事現場で、作業員がトンネル内で左手首を骨折する事故が発生。
ところが、建設会社側は労災かくしを図り、労働基準監督署へ災害報告書を提出しませんでした。
作業員は41日間休業しました。
下請け建設会社が労災かくしを行った理由は、以下の2つと考えられます。
- 元請企業からの納期や予算の圧力か
- 労災保険料の負担増加への懸念か
事例2建設業における労災かくし
2022年1月、滋賀県東近江市の下水管設置工事現場で、労働者が作業中に足を骨折する事故が発生。
作業員は全治2ヶ月の大怪我を負ったものの、労働基準監督署への報告はありませんでした。
会社と社長は、労働基準監督署により、書類送検されました。
事業主が労災かくしを行った理由は、以下の2つと考えられます。
- 労災保険料の負担増加への懸念か
- 企業イメージの悪化への懸念か
事例3食品製造業における労災かくし
平成21年9月、東京都内の食品製造業者が労災かくしを行っていたことが発覚。
労災の内容は、労働者が製品を搬送中に転倒、打撲の傷害を負う事故が発生し、76日間休業した、というものです。
それにもかかわらず、業者は労災かくしを行い、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しませんでした。
食料品製造会社及び同社の総務部長は、書類送検されています。
食品製造業者が労災かくしを行った理由は、以下の2つと考えられます。
- 荷物の運搬を優先させたことか
- 労災保険料の負担増加への懸念か
実はそれも労災かくしかも?


自分で気づいていないだけで、「あれは労災だったかも」という案件があるかもしれません…。
 弁護士
弁護士確かに、企業が労災についての知識が不足しており、労災と認定しなかったというケースも少なくありません。
事例で解説したとおり、通勤中の事故や業務中の怪我や病気など、仕事が原因でケガや病気をした場合、労災保険の対象となる可能性があります。
一方で、労働者が適切に報告したにもかかわらず、会社側が労災と認識しておらず労災事故をなかったことにしたり、労災だと気づいていても虚偽の報告をしたりする「労災かくし」が行われることもあります。
たとえば、以下のようなケースは労災かくしに該当する可能性があります。
- 労働者が休憩中に転倒して怪我をしたが、「業務上の事故ではない」と判断してしまい、労災申請を怠った。
- 労働者がストレスを原因とするうつ病になってしまったが、「仕事だけがストレスの原因ではない」「仕事との因果関係がない」と判断してしまい、労災申請を怠った。
- 労働者から軽微な事故について労災の申し出を受けたが、「軽微な事故だから労災申請は不要」と判断し、労災申請をしなかった。
- 会社の経営状態などを鑑みて、「労災申請すると会社経営に影響が出る」と労働者に通告した結果、労災が発生しても報告されなくなり、会社も積極的に労災申請しなかった。
これらに当てはまる出来事があった場合は要注意です。
「労災かくし」にならないように、不安な場合には専門家に早期相談するようにしましょう。
労災かくしをされた労働者について


労災かくしは、労働者にもデメリットがありますよね?
 弁護士
弁護士さまざまなデメリットが考えられますが、適切な治療や補償が受けられなくなることが大きなデメリットと言えます。
労働者にとってのデメリット
治療費や休業補償費などの補償を受けられない
労災保険が適用されれば、治療費や休業補償費、障害補償給付などのさまざまな補償を受けられます。
しかし、労災かくしによって労災と認められなければ、これらの補償を受けられず、経済的・心理的な負担が大きくなります。
後遺症が残るリスクが高まる
労災保険が適用されれば、適切な治療を受けられます。
しかし、労災かくしによって治療が遅れたり、適切な治療を受けられなかったりすると、後遺症が残るリスクは高くなります。
会社からの不利益な扱いを招く
労働基準法では、労災による休業期間+30日間は、解雇してはならないと定められています。
しかし、労災かくしが行われた場合、そのルールが適用されません。
さらに、会社から解雇や降格、減給などの不利益な扱いを受ける可能性があります。
労災かくしにあった場合の対処法
労災かくしにあった場合、労働者ができる対処方法を紹介します。
労災かくしがあったことを証明するために、証拠を集めておくことが重要です。
- 事故発生時の状況を写真で撮影する
- 目撃者の証言を録音する
- 医師の診断書や、領収書などの医療関係書類を保管する
- 会社からの回答書を保管する
小さな証拠でも、残しておくようにしましょう。
労働基準監督署は、労働者の安全と健康を守るための行政機関です。
労災かくしの相談に対応しており、企業への行政指導も行っています。
相談者の氏名や相談内容を会社側にバレないよう、配慮してくれます。
労災かくしは法的に複雑な問題となるため、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、労災かくしに関する法律や手続きについて深い知識があり、状況に応じた適切なアドバイスが可能です。
労働組合は、労働者の権利を守るための組織です。
労災かくしにあった場合は、労働組合に相談できます。
労働者の権利を守るため、会社に対して交渉してくれます。
厚生労働省や独立行政法人労働安全衛生総合研究所など、労働問題に対応する相談窓口もあります。
法テラスは、法律問題に関する相談を受けられる、国が設立した総合案内所です。
経済的に余裕のない人は、無料で利用できます。
(利用に当たっては収入や資産が一定額以下であるなどの要件を満たす必要があります。)

労災かくしは違法・犯罪《罰則対象です》
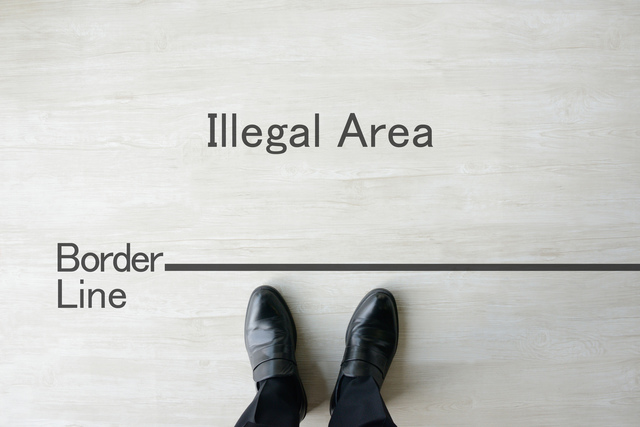

労災かくしをしたら、どんな罰則があるのでしょうか?
 弁護士
弁護士労働災害発生の隠蔽や、虚偽の内容を報告する「労災かくし」は、労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金が科せられる犯罪行為です。
会社だけでなく、労災かくしに関与した個人も罰せられる可能性があり、故意に隠蔽した場合は懲役刑の対象となることもあります。
労災かくしの影響
労災かくしは、労働者にとって大きな不利益となることを紹介しましたが、会社にとっても、以下のようなリスクが発生します。
- 法令違反で罰せられる
- 企業イメージが損なわれる
- 損害賠償請求を受ける可能性がある
このように、労災かくしは、労働者と会社双方にとって深刻な問題となるため、絶対に避けるべきです。
労災かくしの時効
労災かくしには、時効が存在します。
刑事事件としての労災かくしの時効は3年(犯罪行為を知った日から起算)、民事上の損害賠償請求では、5年(被害者が損害を知った日から起算)の時効が適用されます。
この時効までに、労災かくしが行われていることに気づいた労働者が訴えを起こす可能性は十分にあり、これは会社にとって重大なリスクとなり得ます。
「時効まで隠し通せばいい」と甘く考えずに、労災かくしの疑いがある場合には、速やかに各種機関や専門家へ相談することが重要です。
まとめ
労災保険は、労働中や通勤中に発生した事故や病気による被害を、補償する重要な制度です。
しかし、残念ながら「労災かくし」という違法行為が未だに発生しています。
労災かくしは、被災労働者に対して適切な補償を受ける権利を奪うだけでなく、治療遅延による後遺症のリスクを高め、経済的負担を大きくするなど、多くのデメリットをもたらします。
また、労災かくしは企業の負のイメージを招き、社会的な信頼を失うことにもつながり、企業側にとっても大きな不利益となることは避けられません。
労災かくしに遭遇した場合は、労働基準監督署や弁護士といった専門家に相談し、証拠を集めて適切な手続きを踏むことが重要です。
弁護士保険などで、今後の様々なリスクに備えておくこともおすすめします。
また、事業主は、労働災害を正しく報告し、労災保険制度を適切に利用する責務が求められます。

弁護士 黒田悦男
大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981
事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。
また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










