裁判所から呼び出しを受けたものの、やむを得ない事情で欠席せざるを得ない状況に直面してしまう、ということは少なくありません。
一般的に、突然裁判を欠席すると不利な判決につながりやすいものですが、適切な対応を取ることで影響を最小限に抑えられます。
この記事では、欠席による具体的な影響から、答弁書の提出や裁判所への連絡といった対処法をわかりやすく紹介しています。
また、判決確定後の救済措置についても、法律実務の観点から解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
そもそも裁判を欠席してもいいのか?

 弁護士
弁護士裁判所からの呼び出しを受けた場合、原則として出廷する義務があります。
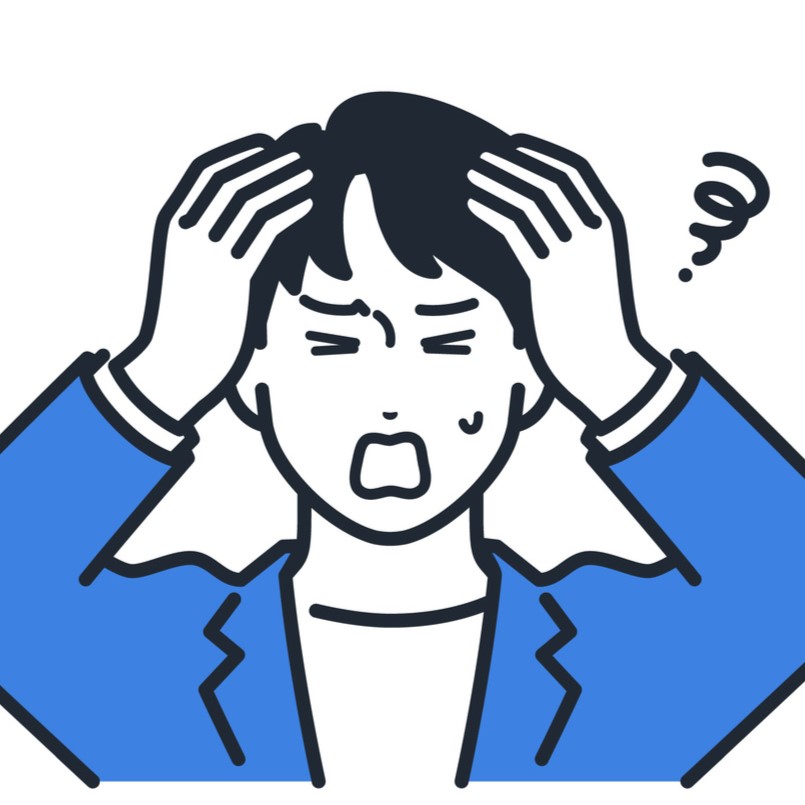
どうしても出廷できない場合には、どうしたらいいのでしょうか?
状況によっては欠席が認められるケースもあり、その判断基準と対応方法を理解しておくことが重要です。
民事裁判と刑事裁判における裁判欠席の扱いの違い
民事裁判と刑事裁判では、欠席に関する取り扱いが大きく異なります。
民事裁判は個人間の権利関係を解決する場であり、一定の条件下で欠席が認められます。
一方、刑事裁判は被告人の刑事責任を問う場であり、原則として欠席は認められません。
また、民事裁判では答弁書を提出すれば、出廷せずに手続きを進行できる場合もありますが、刑事裁判ではそのような対応は認められていません。
民事裁判で欠席しても許されるケース
民事裁判における欠席は、以下の条件を満たす場合に認められます。
- 答弁書を期限内に提出している※
- 病気や事故など、やむを得ない事情がある
- 裁判所に事前連絡をしている
なお、これらの条件を満たしていなくても、相手方が同意すれば期日の変更が認められる場合があります。
※第一回期日に限ります。
答弁書の提出だけをして欠席しても確実に許されるのは、代理人として弁護士などに依頼している場合だけです。
当事者本人で裁判する場合には、答弁書を提出しても、答弁書が裁判を争うだけの中身として乏しいと裁判所が判断すれば、欠席したまま不利益な評価をされてしまう可能性はありますから十分注意して下さい。
欠席が許される具体的なケース
民事裁判では、特定の状況下で欠席が認められています。
たとえば、弁護人を立てていて、答弁書を提出済みの場合、実質的な審理に支障がないと判断されれば欠席が許容されます。
特に、簡易裁判所での手続きではより柔軟に対応してもらえることが多いでしょう。
第1回期日の欠席
第1回期日は、主に今後の裁判の進め方について協議する機会です。
答弁書が提出されており、争点が明確になっている場合は、欠席しても手続きの進行に重大な支障が生じないと判断されることがあります。
ただし、争点整理のために本人の出席が必要と判断される場合もありますので、裁判所の指示に従うようにしましょう。
簡易裁判所での欠席(条件を満たした場合)
簡易裁判所では、少額訴訟や簡易な事案を扱うという特性から、状況に応じた柔軟な手続きが認められています。
たとえば、電話会議システムの利用や、書面のみでの審理も可能となる場合があります。
ただし、これらの特例も、事前に裁判所との調整が必要です。
刑事裁判で欠席が許されない理由
刑事裁判では、被告人の権利を守るため、本人の出廷が必要不可欠とされています。
被告人に認められている「黙秘権」や「防御権」といった権利を適切に行使するためには、公判に出席して直接手続きに参加する必要があるからです。
また、量刑判断(裁判官が刑の種類や程度を決定する判断)においても、被告人の態度や反省の程度を直接確認することが重要視されています。
欠席裁判の仕組みや主なリスク
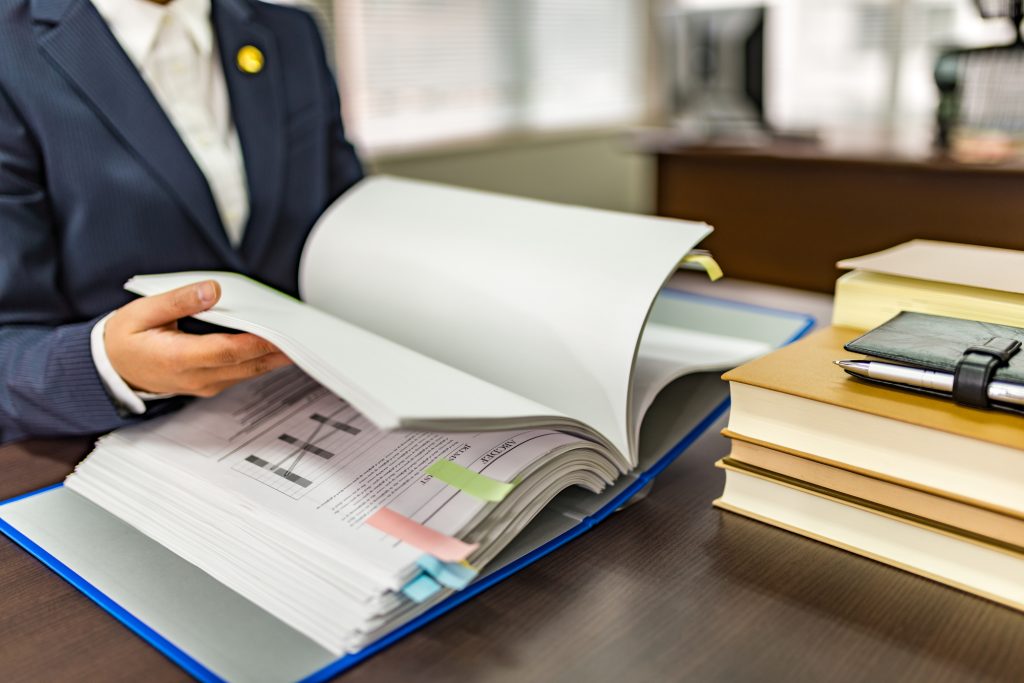
裁判を欠席することは、訴訟の結果や当事者の権利に大きな影響を及ぼすことがあります。
 弁護士
弁護士特に被告側の欠席は、原告の主張をすべて認めたとみなされる「擬制自白(ぎせいじはく)」につながるリスクがあります。

理由もなく「行きたくないから欠席する」というのは避けた方がいいですね。
欠席裁判が成立する仕組み
欠席裁判は、正当な理由なく、当事者の一方が出廷しない場合に成立します。
手続きの公平性を確保するためにも、裁判所は欠席者に対して呼び出し手続きを行わなければなりません。
そのためにも、訴状や期日呼出状は、特別送達で届けられます。
特別送達は書留で送られる法的に重要な書類の送達方法であり、受け取り拒否はできません。
これらの書類が確実に送達されていることを前提として、欠席裁判の手続きが進められるのです。
なお、裁判所からの「特別送達」を無視すると、訴状や判決書が有効に送達されたとみなされ、不利な判決が確定するリスクがあります。
無視してもメリットはないので、必ず受け取るようにしましょう。
擬制自白とは?原告の主張を認めた扱いになる理由
擬制自白によって、原告にとって有利な結果につながりやすくなります。
また、当事者が積極的に争わなくなるため、裁判の遅延を防ぐ効果もあります。
欠席が判決に与える具体的な影響
欠席による擬制自白が成立すると、原告の主張する事実関係がそのまま認定されます。
被告は自己に有利な証拠を提出する機会を失うため、原告の請求が認められやすくなります。
被告として欠席した場合のリスク
被告の欠席は、訴訟の結果に大きな影響を与えます。
出廷して自己の主張を行う機会を失うだけでなく、さまざまなリスクがあります。
答弁書を出さない場合
答弁書を提出しないと、「原告の主張を全面的に認めた」と裁判所からみなされる可能性があります。
この結果、被告は反論の機会を失い、訴訟内容によっては請求額全額の支払いを命じられる等の恐れがあります。
欠席が続いた場合
継続的に欠席した場合も、裁判所は被告が権利を放棄したとみなし、原告の請求をほぼ全面的に認める判決を下す可能性があります。
また、欠席ばかりで裁判の対応を怠っていると判決通知が届いても気づかず、控訴の機会を逃す恐れもあります。
原告として欠席した場合の影響
原告の欠席は、訴訟の取り下げとみなされ、提起した訴訟が無効となる可能性があります。
また、何度も欠席した場合、「訴訟遂行の意思がない」と裁判所から判断され、訴訟が取り下げられることもあります。
すると、新たな訴訟費用の負担や、二重起訴の禁止などの制限により、大きな不利益が生じます。
裁判を欠席せざるを得ない場合の対応策

やむを得ない事情で裁判を欠席する場合でも、正しい対応を取ることで不利益を最小限に抑えられます。
 弁護士
弁護士特に答弁書の提出と裁判所への事前連絡は、重要なポイントと言えるでしょう。
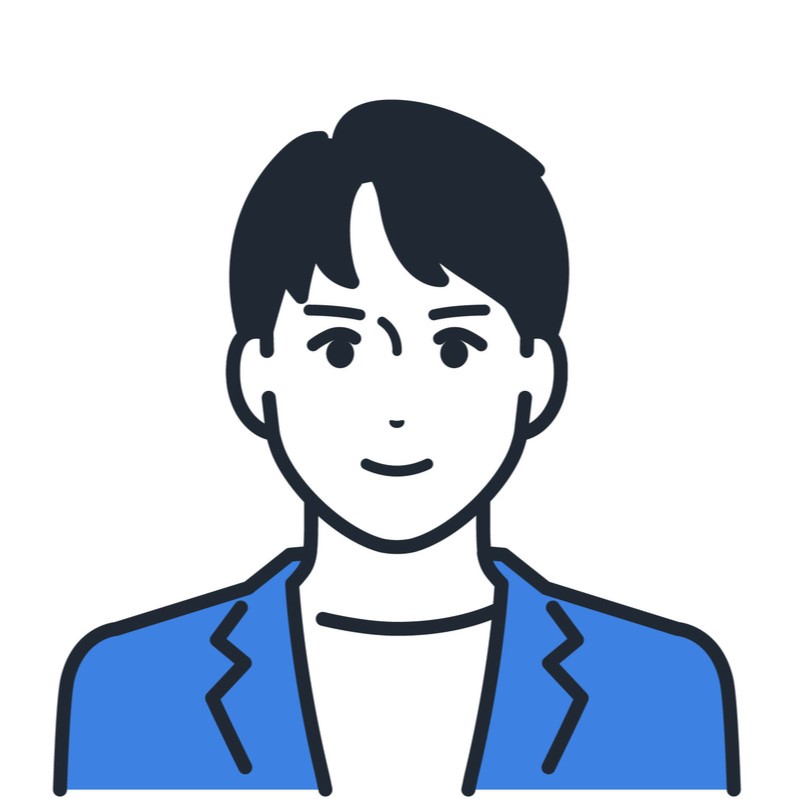
欠席の際は、出来る限り早めの連絡が大事ですね!
答弁書を提出する
答弁書の提出は、被告の主張を書面で裁判所に示す重要な手続きです。
期日に出席できない場合でも、答弁書を提出することで擬制自白を避け、自己の主張を裁判所に伝えられます。
提出期限は厳格に定められており、訴状の送達から2週間以内とされています。
答弁書には、請求の認否と抗弁事由を明確に記載する必要があります。
請求の認否とは、原告が被告に対して請求した内容を認めるか否認するかを明確にすることです。
また、抗弁事由とは、被告が原告の請求に反論する理由や根拠のことです。
形式要件として、提出日、当事者の表示、事件番号などの記載が必須となります。
答弁書は自分での作成も可能ですが、法的な専門知識が必要な部分もあるため、弁護士への相談も検討しましょう。
裁判所に事前連絡する
裁判を欠席する場合は、不利な判決を避けるためにも、裁判所へ事前に連絡しておきましょう。
連絡なく裁判を欠席すると、「裁判に関心がない」「権利を放棄した」と見なされ、不利な判決に持ち込まれる恐れがあります。
やむを得ず欠席する場合は、裁判所へ可能な限り早く伝えましょう。
欠席理由を伝える際の具体的な手順
欠席理由は書面または電話で裁判所に連絡します。
病気や事故の場合は、診断書などの証明書類の提出が求められることがあります。
連絡は、必ず期日前に行いましょう。
電話会議や期日変更を申請する方法
電話会議の利用や期日変更の申請は、書面で行うのが原則です。
相手方の同意があれば、変更が認められやすくなります。
特に簡易裁判所では、柔軟な対応をしてもらえるケースが多いでしょう。
弁護士に依頼する
弁護士に依頼することで、専門的な法的対応が可能になり、訴訟リスクを大幅に軽減できます。
特に出席できない場合の弁護士による代理出頭は、有効な手段です。
弁護士は期日への出頭、答弁書の作成、証拠の提出など、ほぼすべての訴訟行為を代理できます。
たとえ本人が出頭できない場合でも、適切な訴訟対応が可能になります。
裁判欠席後に取れる対策と救済措置

裁判欠席により不利な判決を受けても、法律で定められた救済手段を受けられる場合があります。
 弁護士
弁護士控訴や請求異議の訴えなど、状況に応じて適切な対応策を検討しましょう。
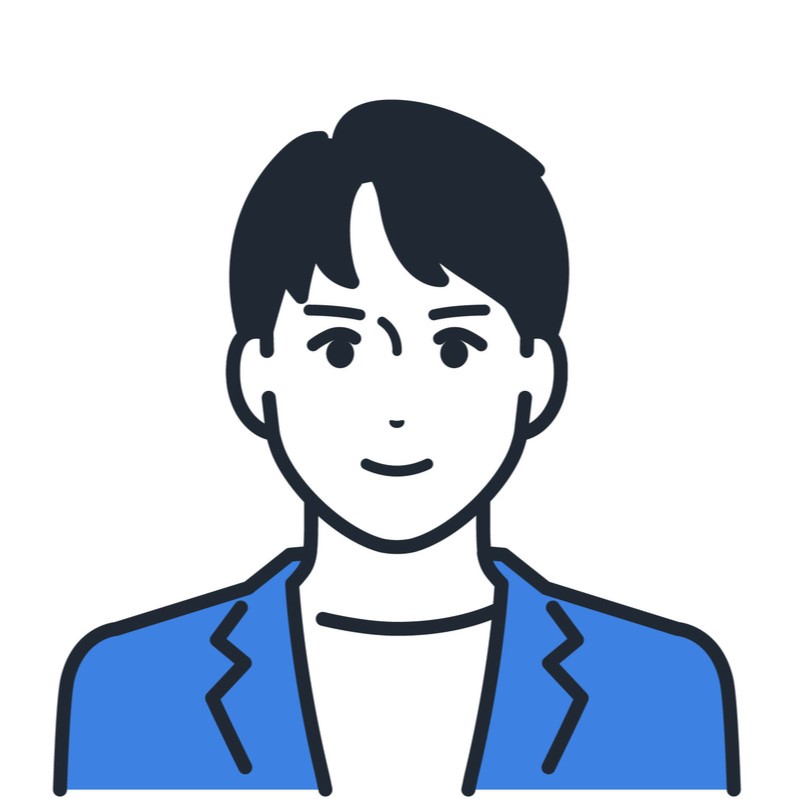
具体的な内容について知りたいです!
控訴を検討する場合のポイント
控訴状には不服の理由を具体的に記載する必要があり、新たな証拠の提出も認められます。
控訴期間は、第一審判決正本(判決書)を送達した日の翌日から2週間以内です。
この期間を過ぎてから控訴を提起することは原則として認められず、判決は確定してしまいます。
控訴期限を守るための具体的な手順
控訴状は第一審裁判所に提出します。
控訴期間の起算点は判決書の送達日であり、送達証明書で確認可能です。
期限内に控訴状を提出できない場合は、書面で期間延長を申し立てられます。
控訴が認められる条件と注意点
控訴審では、第一審判決の法令違反や事実誤認を主張する必要があります。
欠席によって擬制自白が成立した場合でも、やむを得ない事由があれば新たな主張や証拠の提出が認められるケースもあります。
判決確定後の救済措置
判決確定した後でも、特定の要件を満たせば、救済を受けられる可能性があります。
救済には、請求異議や再審の訴え、和解の交渉などがあり、状況に合わせた法的手段を検討できます。
請求異議の訴えで判決を覆す方法
判決確定後に債務の消滅や判決後の事情変更があった場合、判決に重大な瑕疵などが生じた場合に提起できます。
たとえば、支払いや和解が成立したにもかかわらず、執行が行われる場合などが該当します。
その他の法的手段による救済策
再審の訴えは、判決の基礎となった証拠が偽造であった場合に認められます。
また、支払督促に対する異議申立てや、少額訴訟における異議申立ても救済手段となります。
執行停止の申立てによる一時的救済
控訴と同時に執行停止の申立てを行うことで、判決の強制執行を一時的に止められる場合があります。
これにより、控訴審の結論が出るまでの間、財産の差押えなどを回避できます。
本人訴訟と弁護士を利用する場合の違い
本人訴訟では法的な専門知識が不足していると、不利な立場に置かれる可能性があります。
そのような場合は、弁護士を利用することで、専門的な法的主張や証拠収集が可能になり、より有利な訴訟活動を進められます。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
裁判への欠席は、適切な対応を取ることで不利益を抑えられる場合があります。
民事裁判では答弁書の提出が最も重要な防御手段となり、期日への出席が困難な場合は裁判所への事前連絡が必須です。
欠席で不利な判決を受けた場合でも、控訴や請求異議の訴えなど、法的な救済手段も用意されています。
ただし、手続きには期限があり、専門的な法的知識も必要となるため、弁護士への相談がおすすめです。
木下慎也 弁護士
大阪弁護士会所属
弁護士法人ONE 代表弁護士
大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階
06-4797-0905
弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










