「SNSで個人情報を晒された」
「元恋人がプライベートな写真を勝手に公開した」
「職場の同僚に前科のことを言いふらされた」
このようなお悩みはありませんか?
他人に知られたくない情報を無断で公開される「プライバシー侵害」は、デジタル時代において深刻な問題となっています。
一度インターネット上に拡散された情報は、完全に削除することが困難です。
こうした被害に遭った際、「相手を訴えることはできるのか?」「慰謝料はいくらもらえるのか?」「情報を削除させることは可能なのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。
プライバシー侵害は私事性・秘匿性・非公知性の3つの要件を満たす場合に成立します。
被害者は加害者に対し、10万円から100万円超の損害賠償を請求できる可能性があります。
また、SNSや掲示板の運営会社に削除依頼を行うことで、被害の拡大を防ぐことも可能です。
ただし、デジタル時代特有の情報拡散の速さやいつまでも残り続ける特性により、より迅速な対応が求められます。
本記事では、プライバシー侵害の成立要件から具体的な対処法、予防策について、弁護士監修のもと、わかりやすく解説していきます。
実際の判例や事例を交えていますので、プライバシー侵害でお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
プライバシー侵害とは

現代のデジタル社会では、SNSや掲示板を通じた個人情報の拡散が深刻化しており、被害者の社会復帰や精神的健康に長期的な影響を与える重要な人権問題となっています。

正直、どこからがプライバシー侵害に当たるのかよくわかっていません。
 弁護士
弁護士では、改めてプライバシー侵害について詳しく解説します。
【定義】個人の私生活情報を無断で公表すること
情報が本人の同意なく不正に取得されたり、利用、開示、改ざんされたりすることも含まれ、現代では特にインターネットを通じた情報拡散が問題となっています。
従来は、週刊誌や新聞の報道期間によるプライバシー侵害が中心でしたが、現在では一般の個人が簡単に情報発信できるようになったため、被害の広がりや影響の深刻度合いが増しています。
ポイントとなるのは、公開される情報が真実であるか虚偽であるか、ではありません。
それが、私生活上の事実として受け取られる可能性があればプライバシー侵害として見なされる可能性があります。
プライバシー権の法的根拠
プライバシー権は憲法や個別の法に明文規定はありませんが、憲法13条の「個人の尊重および幸福追求権」を根拠として、判例によって確立された「人格権」の一つです。
民法709条の不法行為の規定により、プライバシー侵害を受けた被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。
1964年の「宴のあと事件」では、東京地裁が初めてプライバシー権を「私生活をみだりに公開されない権利」として法的に認定しています。
「宴のあと事件」とは・・・ 小説に登場する人物が実在の政治家に酷似しているとして、出版社と著者を提訴した事件のこと。
この判決では、プライバシー侵害の成立要件として
- 私事性
- 秘匿性
- 非公知性
の3要素が示されました。
現在でも、この基準が基本的な判断枠組みとして使用されています。
また、「京都市前科照会事件」においても、最高裁が前科等は「みだりに公開されないという法律上の保護に値する利益」であると判示し、プライバシー権の保護を明確に認めています。
「京都市前科照会事件」とは・・・地方自治体が住民の前科を無断で照会・取得した行為がプライバシー権の侵害とされ、違法と判断された事件のこと。
個人情報保護法・肖像権との違い
プライバシー権と個人情報保護法は、保護対象や救済手段が異なる点に注意が必要です。
個人情報保護法は、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものを対象としており、主に企業や行政機関などの事業者が個人情報を適正に取扱うことを目的とした法律です。
一方、プライバシー権はより広い概念であり、個人が他人に知られたくないと考える私生活上の情報全般を保護対象とした権利となります。
企業間だけでなく、個人間でのプライバシー侵害行為も責任を問われることがあります。
肖像権はプライバシー権の一種であり、自分の顔や姿などを、本人の許可なくみだりに撮影・公表されない権利です。
たとえば、無断で他人の顔写真を公開する行為などが該当します。
また、こうした権利侵害に対する救済方法にも違いがあります。
個人情報保護法に基づく場合では開示・訂正・利用停止請求が中心ですが、プライバシー侵害や肖像権侵害については、主に損害賠償請求の訴訟や情報公開を差し止める請求等が行われます。
| 項目 | プライバシー権 | 個人情報保護法 | 肖像権 |
| 保護対象 | 個人の秘密にしたい情報全般 ・恋愛関係 ・病歴 ・前科 など | 特定の個人を識別できる情報 ・氏名 ・住所 ・電話番号 など | 容貌・姿態に関する情報 ・顔写真 ・体型 ・服装 など |
| 法的根拠 | 憲法13条・民法709条・判例 | 個人情報保護法 | 憲法13条・判例 |
| 適用範囲 | 個人間・事業者問わず(誰が相手でも適用される) | 主に個人情報取扱事業者(会社や店舗が対象) | 個人間・事業者問わず(誰が相手でも適用される) |
| 救済手段 | 損害賠償・差止請求 | 開示・訂正・利用停止請求 | 損害賠償・差止請求 |
| 成立要件 | 私事性・秘匿性・非公知性 | 個人情報の不適正取扱い | 撮影・公表の無断性 |
プライバシー侵害は刑事事件(犯罪)になるのか
プライバシー侵害が発生した場合、刑法で罰する規定はありません。
ただし、民事上の責任を問うことは可能です。
民事責任として、被害者は民法709条の不法行為を根拠に損害賠償を請求できます。
また、人格権に基づく差止請求によって、現在続いている侵害行為の停止や将来的な侵害の予防を求めることも可能です。
ただし、プライバシー侵害の内容や方法によっては、刑事事件として扱われる場合もあります。
- 名誉毀損罪(刑法230条)
相手の名誉を傷つける発言があった場合 - 信用毀損罪(刑法233条)
企業や個人の信用を損なった場合 - 脅迫罪(刑法222条)
「家に行ってやる」などの脅迫的文言がある場合 - 不正アクセス禁止法違反
他人のアカウントに無断でアクセスして情報を取得した場合
このように、プライバシー侵害には刑事責任が問われる場合もあるため、「身の危険を感じる場合はまず警察への相談を」とされているように、状況に応じて刑事手続きも視野に入れた対応が求められます。
プライバシー侵害が成立する要件【3つの条件】

プライバシー侵害が法的に認められるためには、1964年の「宴のあと事件」で確立された3つの要件を満たす必要があります。
 弁護士
弁護士これらのすべてが揃った場合に、初めて違法なプライバシー侵害として損害賠償や差止請求が可能となります。

改めて、3つの条件についてどのようなものなのか聞きたいです。
私事性(私生活の事実であること)
私事性とは、公開された情報が、私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれのある事柄であることを意味します。
なお、客観的な真実性は問われません。
重要なのは、政治家や公務員の公的活動に関する情報は、私事性が認められないことです。
例えば、政治家の政策判断や公務員の職務上の行為は、公的な性質を持つため、プライバシー侵害の対象外です。
一方で、これらの人物であっても家族関係や健康状態、個人的な趣味嗜好などは私事性が認められる可能性があります。
また、事実が虚偽であっても、一般人がそれを私生活上の事実として受け取る可能性があれば、この要件を満たすとされています。
秘匿性(公開を望まない情報であること)
秘匿性とは、一般的な感覚からして、人に知られたくない内容であることを指します。
この判断は本人の主観ではなく、あくまで平均的な一般人の感受性を基準にして、客観的に行われます。
例えば「ユリよりも桜が好き」といった程度の個人的嗜好は、通常他人に知られても心理的な負担は少ないと考えられるため、秘匿性が認められることはほぼありません。
しかし、病歴や前科、借金状況、不倫関係などは、一般的に他人に知られたくない情報とされるため、秘匿性が認められやすくなります。
特に性風俗業への従事は「社会通念上、社会的偏見の強い職業」として高度に私的な情報と認定された判例もあります。
非公知性(公に知られていない情報であること)
非公知性とは一般の人々にまだ知られていない事柄であることを要件とする概念です。
公開されることによって、本人が実際に不快感や不安を覚えるような情報であることが一般的な条件です。
ただし、一度公開された情報であっても、永久にプライバシー保護の対象から外れるわけではありません。
すでに新聞やインターネット上のブログで公開された内容でも、読者層の違い等を理由に非公知性の要件を認める判例も多くあります。
また、時間の経過により社会的な関心が薄れた場合にも、改めて非公知性が認められることもあり、これが「忘れられる権利(過去の情報を一定の条件下で社会から消去・制限されることを求める権利)」の議論に繋がっています。
名誉毀損・肖像権侵害との違い
プライバシー侵害と名誉毀損の最大の違いは、「真実性の扱い」です。
プライバシー侵害では、判例上、その内容が事実であるかどうかにかかわらず、本人の私生活上の事実が無断で公開されれば成立するのが原則です。
一方、名誉毀損については内容にかかわらず、真実であり、かつ公共の利害に関わる事実で公益目的があれば、違法性が否定される場合があります。
すなわち、名誉毀損では、真実性の立証により違法性が否定される可能性がありますが、プライバシー侵害では、内容が真実であるからこそ、より被害は深刻になると言えるでしょう。
また、公益性についても違いがあります。
名誉毀損では、公共の利害に関する事実で公益目的がある場合には違法とならないケースもありますが、プライバシー侵害ではたとえ政治家や著名人であっても、私生活に関する情報の公開は原則として違法とされます。
なお、肖像権の侵害については、「プライバシー侵害の一種」とされており、容貌の無断撮影や公開行為が、プライバシー侵害として扱われることがあります。
3要件の具体的判断基準
3要件の判断は総合的に行われ、すべてを満たさなければプライバシー侵害は成立しません。
たとえば、ある判例では「性風俗業は社会通念上、社会的偏見の強い職業」とされ、高度な秘匿性が認められました。
また、防犯カメラ設置に関する事例では、撮影の場所・範囲・態様・目的・必要性や映像の管理方法等が総合的に考慮され、被撮影者の受ける不利益が社会生活上、受けいれられ範囲を越えるかが判断の基準とされています。
重要なのは、情報の公開時期と社会を取り巻く状況の変化です。
過去に問題がなかった公開行為でも、時間の経過によって違法となるケースも少なくありません。
特にインターネット上では一度公開された情報が半永久的に残る傾向にあるため、「情報の残存性や粘着性」によって、被害が長期化・深刻化しやすいという特徴があります。
また、SNS等を通じた情報拡散も大きな問題です。
発信が手軽なうえ、情報が一気に拡散される特性があるため、被害は急速に拡大します。
そのため、近年では、プライバシー保護に対して、従来の基準よりも厳格な保護が必要とされる傾向にあります。
デジタル時代のプライバシー侵害

現代のプライバシー侵害は従来とは質的に異なる深刻さを持ちます。
発信の容易性や情報の拡散性、情報の残存性や情報の粘着性という4つの特徴により、被害の回復が困難で長期的な影響を与える問題となっています。
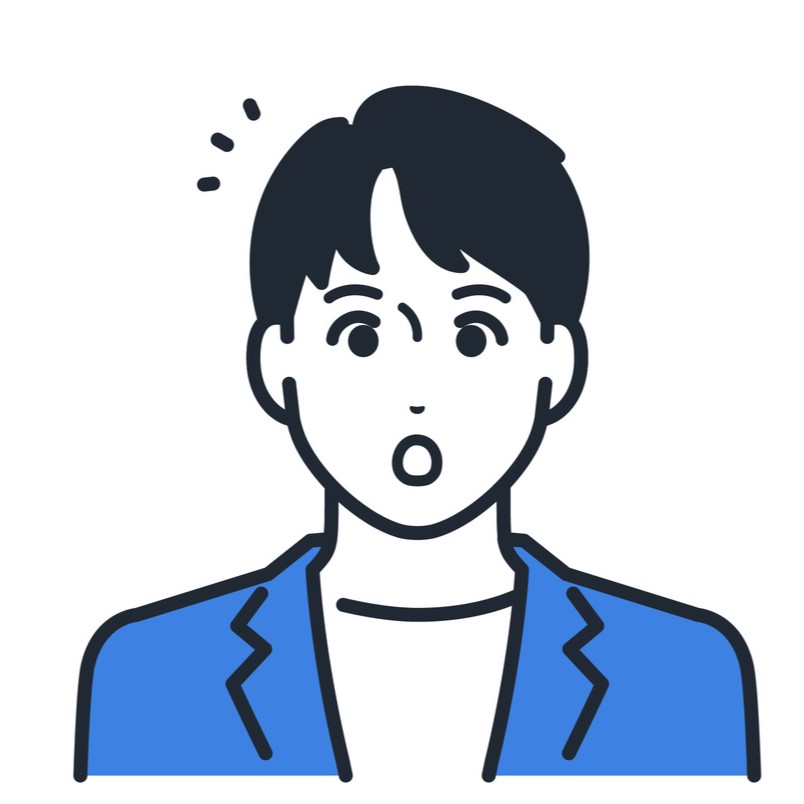
「デジタル」という性質をよく理解する必要がありますね。
 弁護士
弁護士安易な気持ちで情報公開してはならない、という意識を持つことが大切です。
SNS・掲示板での個人情報暴露
SNSや匿名掲示板での個人情報の暴露は、現代において最も深刻なプライバシー侵害の形態です。
誰でも簡単に情報発信ができる環境が整っており、一度公開された情報があっという間に拡散されてしまうからです。
免許証画像の無断公開や犯罪歴・破産情報の掲示板投稿などは、典型的な被害例と言えます。
特に深刻なのは、これらの情報がインターネット上に永続的に残り続け、検索によって個人に紐づけられることで、被害者の社会復帰や就職活動に長期的な悪影響を与えることです。
テレビや新聞等のオールドメディアによる報道と異なり、時間が経っても情報が消えず、簡単にアクセスできる状態が続きます。
ECサイトでの誤送信・情報漏洩
ECサイトにおける個人情報の誤送信や情報漏洩は、企業の管理体制の不備から発生する深刻なプライバシー侵害です。
具体的には、以下のような事例が挙げられます。
- 商品発送時の宛先間違いによる住所・氏名の漏洩
- メール配信での宛先誤設定によるメールアドレスの大量流出
- データベース管理の不備による顧客情報の外部流出
これらの事故は企業側に過失があるケースが多く、被害者は民法709条に基づく損害賠償請求が可能です。
特に問題となるのは、購買履歴から個人の嗜好や生活状況が推測される場合です。
単なる連絡先情報の漏洩を超え、深刻なプライバシー侵害となります。
また、クレジットカード情報や決済情報の漏洩は、経済的被害につながる可能性が高く、慰謝料以外の財産的損害の賠償も問題となります。
企業は個人情報保護法に基づく安全管理措置義務を負っており、この義務違反は行政処分の対象にもなります。
不正アクセス・ハッキング・マルウェアによる情報窃取
不正アクセスやハッキング、マルウェアを使用した情報窃取は、技術的手段により個人のプライバシーを侵害する犯罪行為です。
代表的な手口には、以下のようなものがあります。
- オンラインアカウントへの不正侵入
- スパイウェアによる個人情報の盗取
- フィッシング詐欺による認証情報の騙取
これらの行為は不正アクセス禁止法に違反するものであり、刑事処罰の対象となるほか、被害者に対する不法行為として民事責任も生じる場合があります。
特に深刻なのは、盗取された個人情報が犯罪組織により売買され、ID盗難やオンライン詐欺に悪用されることです。
また、マルウェアに感染した場合、知らないうちに個人情報が監視・収集、長期間にわたりプライバシーが侵害される可能性があります。
こうした被害は発見が遅れる傾向にあり、気づいたときには被害が広範囲に及んでいることも少なくありません。
近年では、ランサムウェアによりデータを暗号化して、復旧と引き換えに身代金を要求する手法も増加しています。
このような攻撃は、個人だけでなく企業や医療機関なども標的となっています。
リベンジポルノ・ネットストーキング・デマの拡散
リベンジポルノやネットストーキング、デマの拡散は、悪意を持った個人による意図的なプライバシー侵害行為です。
具体的には、以下のような事例があります。
- 元交際相手による私的な画像・動画の無断公開
- SNSを通じた執拗な嫌がらせや監視行為
- 虚偽情報を流して社会的信用を失墜させる行為
これらの行為は、被害者の精神的健康に大きなダメージを与え、社会復帰を困難にするケースも少なくありません。
たとえば、リベンジポルノに関しては、専用の処罰法が制定されています。
また、SNSやメッセージアプリを通じて執拗に接触を繰り返すネットストーキングについてもストーカー規制法の取り締まり対象となっています。
デマの拡散については、内容により名誉毀損罪や信用毀損罪が成立する可能性があります。
特に問題なのは、これらの行為が「実際に不快、不安の念を覚える」状態を継続的に作り出し、被害者を精神的に追い詰めることです。
なお、SNSの匿名性によって加害者の特定が困難となる場合も少なくありません。
そこで、「プロバイダ責任制限法」に基づいた発信者情報開示請求は、被害者にとって重要な救済手段となります。

検索結果表示による過去情報の永続化問題
検索エンジンで過去の情報が表示され続けることは、時間経過とともに社会的関心が薄れていくはずの事実を、半永久的に公開し続けるという、新たなプライバシー侵害と言えます。
特に、犯罪報道や破産情報、不祥事に関する記事が検索結果に表示され続けることで、当事者の更生や社会復帰が阻害される問題が深刻化しています。
たとえば、最高裁平成29年の決定では、児童買春事件の検索結果削除請求について「事実を公表されない法的利益が、表現の自由などに優越することが明らかな場合」に限り、削除を認めるという厳格な基準が示されました。
一方で、令和4年のTwitter投稿削除事件では、過去の逮捕記事の転載について削除を認める判断が下されており、媒体の特性に応じた柔軟な判断が行われる傾向も見られます。
検索エンジンによる情報の表示は「情報の粘着性」の典型例であり、個人の氏名検索により過去の負の情報に容易にアクセスできる状況は、現代特有のプライバシー侵害問題を生み出しています。
プライバシー侵害における実際の判例・具体例

プライバシー侵害の法的リスクは、実際の判例や具体的事例から学ぶことが効果的です。
過去の重要判例に加え、近年増加しているSNS関連事件などを振り返ることで、被害者がどのような損害を受け、加害者がどのような責任を負ったのかが具体的に見えてきます。
 弁護士
弁護士以下で、具体事例を見てみましょう。
宴のあと事件(初のプライバシー侵害認定)
1964年の宴のあと事件(東京地判昭和39年9月28日)は、日本で初めてプライバシー権が法的に認められた、画期的な判例です。
三島由紀夫の小説「宴のあと」に登場する人物が、元外務大臣をモデルにして私生活を詳細に描写したものだとして、モデルとなった政治家がプライバシー侵害を理由に損害賠償と謝罪広告を求めて提訴しました。
東京地裁は、この訴えに対し「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利(プライバシー権)」が存在すると判断。
そして、その成立要件として私事性・秘匿性・非公知性の3要素を示しました。
この判決では、仮名を使用していても実在の人物と特定可能な表現で私生活を公開することは違法であると認めました。
結果として、裁判所は慰謝料の支払いを命じる一方で、謝罪広告請求は棄却し、表現の自由とのバランスにも配慮しています。
この事件は、日本におけるプライバシー侵害訴訟の原点ともいえる判決であり、現在でも同様の基準が適用されています。
京都市前科照会事件(前科情報の違法開示)
京都市前科照会事件(最判小昭和56年4月14日)は、行政機関による前科情報の不適切な開示がプライバシー侵害に該当するとして、最高裁が初めて判断を示した重要な事例です。
弁護士からの照会に対し、京都市の区長が前科および犯罪経歴を回答したことを受け、当事者がプライバシー侵害を理由に損害賠償と謝罪文の交付を求めて提訴しました。
最高裁は「前科等は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科等のある者も、これをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」として、プライバシー権の保護対象として前科情報を明確に位置づけました。
そのうえで、市区町村長が「漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等の全てを報告することは、公権力の違法な行使にあたる」と判断し、損害賠償請求を認めました。
この判例により、前科情報の取扱いにおいて、特に慎重な判断が求められることが明確になり、行政機関における個人情報管理体制にも大きな影響を与えています。
SNS免許証晒し・LINE晒し事例
SNSに免許証画像を公開したりLINEのやり取りを晒したりする行為は、現代特有のプライバシー侵害として深刻な問題となっています。
免許証には氏名・住所・生年月日・顔写真など個人を特定する情報が集約されており、本人の同意なく公開することで、重大なプライバシー侵害が発生することになります。
また、LINEやダイレクトメッセージの内容についても、一般に公開を前提としていない私人間のやり取りであるため、私事性・秘匿性・非公知性を満たす場合にはプライバシー侵害が成立します。
特に問題となるのは、元交際相手との私的なやり取りを「おもしろいから」「嫌いだから」という理由で晒す行為です。
これらの内容によっては、名誉毀損に該当する可能性があります。
一度拡散された情報は、完全な回収が難しく、長期間にわたって被害が継続しやすいという特性があります。
そのため、被害者の社会生活に深刻な影響を与えることも少なくありません。
場合によっては、削除依頼や損害賠償請求の対象となるだけでなく、脅迫罪などの刑事責任も問われる可能性があります。
一般人・著名人のプライバシー侵害
近年の判例では、一般人と著名人のプライバシー保護において異なる基準が適用される傾向が見られます。
一般人については、風俗店勤務者の実名暴露事件(東京地裁平成27年6月18日判決)が代表的です。
東京地裁が性風俗業を「社会的偏見の強い職業」として位置付け、業務内容を高度に私的な情報と認定。
被害者の実名を公開した相手に対し、損害賠償を命じました。
また、防犯カメラ設置事件(東京地裁平成27年11月5日判決)では、私生活領域に設置されたカメラによる常時の撮影が、受忍限度を超えると判断され、プライバシー侵害として1人当たり10万円の慰謝料が認められています。
一方、著名人については、従来「公人だから仕方ない」という議論がありました。
しかし、最近の判例では私生活領域と公的活動領域を明確に区別する傾向にあります。
たとえば、政治家であっても交際関係などの私的領域は、プライバシー保護の対象とされることがあります。
検索結果削除事件やSNS投稿削除事件でも、個人の社会的地位は考慮要素の一つですが、決定的な要因にはなりません。
むしろ、公開情報の内容による精神的苦痛の大きさや、社会的な公益性の有無を総合的に比較して、個別具体的に判断される傾向が高くなっています。
石に泳ぐ魚事件(出版差止の先例)
石に泳ぐ魚事件(最高裁平成14年9月24日判決)は、プライバシー侵害によって出版差止請求が認められた判例です。
柳美里の小説「石に泳ぐ魚」のモデルとなった女性が、プライバシー権および名誉権侵害を理由として、作者と出版社に対し損害賠償と出版差止を求めて提訴しました。
最高裁は、人格権に基づく差止請求の可否を判断するにあたり「侵害行為が明らかに予想され、その侵害行為によって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり、かつ、その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難になると認められるときは侵害行為の差止めを肯認すべきである」との基準を示しました。
この判例により、プライバシー侵害では事後的な損害賠償だけでなく、予防的な差止請求も可能であることが確立され、表現の自由との調整における重要な指針となっています。
特に出版物やインターネット上の情報公開といった、事前規制の可能性を示した点で、現代のプライバシー保護に大きな影響を与えています。
Google検索結果削除請求事件
Google検索結果削除をめぐる一連の事件は、デジタル時代のプライバシー保護のあり方を問い直す重要な展開を示しています。
さいたま地裁(平成27年12月22日決定)は過去の逮捕歴に関する検索結果の削除を認め、「一定の期間が経過した後は、社会から忘れられる権利がある」として、日本初の忘れられる権利を認めました。
しかし、これに対して最高裁(平成29年1月31日決定)では検索結果の削除請求を棄却し、「事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」に限って削除が認められるという、という厳格な基準を示して削除請求を棄却しました。
一方、Twitter投稿削除事件(最高裁令和4年6月24日判決)では、過去の逮捕記事転載について、投稿の削除を認めています。
判決では「上告人の本件事実を公表されない法的利益が、本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する」とし判断されました。
これらの判例から、検索結果とSNS投稿では、適用される判断基準に差があることが伺えます。
媒体の特性に応じた柔軟な判断が行われる傾向にあることが、現代のプライバシー保護において明確になりました。
プライバシー侵害が引き起こすリスク

プライバシー侵害は単なる精神的苦痛にとどまらず、経済的損失、社会的信用の失墜、さらに刑事責任まで幅広いリスクを生じさせます。
 弁護士
弁護士特にデジタル時代では被害が拡散・永続化しやすく、加害者・被害者双方にとって深刻な影響をもたらす問題となっています。

具体的にはどのような影響が考えられますか?
損害賠償・慰謝料の金額相場は10万円~100万円超
プライバシー侵害による損害賠償の中心は、精神的苦痛に対する慰謝料です。
金額相場は、10~50万円程度となるのが一般的とされていますが、侵害の態様が悪質な場合には100万円以上の慰謝料が認められることもあります。
慰謝料額の決定要因として、以下の内容が考慮されます。
- 侵害の程度・期間・範囲
- 被害者の社会的地位
- 加害者の故意・過失の程度
- 侵害行為の悪質性
特に継続的な侵害や意図的な嫌がらせ、営利目的での情報悪用などがある場合は高額な慰謝料が認められる傾向にあります。
また、プライバシー侵害により具体的な経済的損失が生じた場合(就職内定取消し、取引停止など)は、慰謝料に加えて財産的損害の賠償も請求できる場合があります。
ただし、現実問題として、因果関係の立証が困難な場合も多く、実際の回収には時間と費用がかかることも考慮すべきです。
信用失墜・炎上・取引停止
プライバシー侵害による信用失墜は、被害者にとって深刻な影響の一つです。
特に現代では「あっという間に拡散する」情報の特性により、一度失った信用の回復は極めて困難です。
個人の場合、就職活動や結婚、社会復帰に長期的な支障をきたし、企業の場合は顧客離れや取引先との関係悪化により経営に直接的な打撃を与えます。
炎上現象では、最初は小さな問題でも短時間で大規模な批判に発展し、無関係な第三者まで巻き込んだ攻撃的な状況が生まれます。
この状況は「常に個人に紐づいて検索される」という情報の粘着性により長期化し、問題が沈静化した後も検索結果として残り続けるので、非常にやっかいです。
企業においては、従業員のプライバシー侵害行為が会社の信用問題に発展し、取引停止や契約解除、株価下落などの経済的損失を招く可能性があります。
そのため、個人だけでなく組織全体でのプライバシー保護意識の徹底が必要です。
刑事罰(名誉毀損罪・脅迫罪・不正アクセス禁止法違反)
前述のとおり、プライバシー侵害行為は、その態様により刑事処罰の対象となる場合があります。
プライバシー侵害単体では刑事処罰の規定はありませんが、関連する犯罪として名誉棄損罪(刑法230条)、信用毀損罪(刑法233条)、脅迫罪(刑法222条)、不正アクセス禁止法違反などが成立する可能性があります。
名誉毀損罪は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科され、また、信用毀損罪も同様の刑罰が適用されます。
住所の公開とともに「家に行ってやる」などの脅迫的文言がある場合は脅迫罪も成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
また、不正アクセス禁止法違反では、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。
これらの刑事責任は民事責任とは別個に追及され、前科として記録に残ることになります。
企業におけるコンプライアンスリスクと責任範囲
企業がプライバシー侵害に関与した場合、個人情報保護法違反による行政処分や刑事処罰を受けるリスクが生じます。
個人情報取扱事業者は、個人情報の適正な取扱いが義務付けられており、違反により個人情報保護委員会からの勧告・命令、さらに従わない場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
企業の従業員が業務に関連してプライバシー侵害を行った場合、使用者責任(民法715条)により、企業も損害賠償責任を負う可能性があります。
また、企業が個人情報の管理を怠り、漏洩や不正利用を招いた場合は、安全管理措置義務違反として企業の直接的な責任が問われかねません。
近年では、企業の社会的責任(CSR)の観点から、プライバシー保護への取組み姿勢が企業評価に直結するようになってきました。
そのため、コンプライアンス体制の整備や社内での継続的な教育・監督が不可欠となっています。
万が一、違反が発覚して対応が遅れたり隠ぺいしたりすれば、企業の信用は、さらに大きく損なわれる可能性があります。
被害の長期化・世代継承問題
デジタル時代のプライバシー侵害は、被害がいつまでも残る、子や孫の代まで続くなど、これまでの報道被害とは決定的に異なる特徴があります。
一度インターネット上に公開された情報を、完全に削除するのは極めて困難です。
複数のサイトやアーカイブサービスなどを通じて、情報が半永久的に保存され続けるケースも珍しくありません。
特に問題なのは、被害者だけでなく、家族や子孫にまで影響が及ぶことです。
たとえば、親の前科や不祥事に関する情報が検索で表示されることにより、子どもの就職や結婚に支障をきたす事例も報告されています。
このような世代継承リスクは、従来のメディア報道では想定されなかった、新たな人権問題と言えるでしょう。
また、AI技術の発達により、個人の断片的な情報からその人物像を詳細に推測する「プロファイリング」が現実のものとなりつつあります。
これによって、プライバシー侵害のリスクがさらに拡大する懸念があります。
だからこそ、私たち現代人は、軽い気持ちで発信したことが、予想をはるかに超える長期的な被害を生む可能性があることを十分に認識するべきです。
企業・個人が取るべき具体的対策


企業は個人は、具体的にどのような対策を取るべきなのでしょうか?
 弁護士
弁護士プライバシー侵害を防止し、かつ発生した場合の被害を最小限に抑えるためには、予防策と事後対応の両方を視野に入れた対策が必要です。
特にデジタル時代では情報拡散の速度と範囲が飛躍的に拡大しているため、従来以上に慎重かつ迅速な対応が求められます。
社内ルール・研修の徹底
企業におけるプライバシー保護の基盤は、全従業員への教育と明確な社内ルールの整備です。
プライバシーポリシーの策定とともに、プライバシー情報の取り扱いに関する社内規程を整えることが重要です。
収集・管理・利用・第三者提供等の各場面で遵守すべき事項や手続きを、しっかりと明文化する必要があります。
また、定期的な研修も欠かせません。
一定期間ごとに、自社のプライバシーポリシーや社内規程の内容、関係法令の改正、プライバシー侵害を生じさせないために日々の業務で注意すべき点などについての研修を行うことが推奨されます。
研修内容には、以下の内容を含めるとよいでしょう。
- 具体的な判例・事例の紹介
- SNS利用時の注意点
- 情報発信前のチェック体制
- 問題発生時の報告ルール など
また、従業員の個人的なSNS利用についても、留意が必要です。
たとえ私的な投稿であっても、会社との関連が推測される投稿により企業の信用が損なわれるリスクを説明し、適切な利用方法を指導することが重要です。
このように、継続的な教育によって、プライバシー保護への意識を組織全体に浸透させられます。
セキュリティ対策
技術的なセキュリティ対策は、意図しない情報漏洩を防ぐための重要な防護策と言えます。
サイバーセキュリティを強化するためには、アクセス制限、データ暗号化、監視システムの導入が不可欠です。
まず、基本となるのが、アクセス制限です。
個人情報や機密情報へのアクセス権限を業務上必要最小限の範囲に限定し、定期的な権限見直しを実施することで、不要な情報へのアクセスを未然に防ぎます。
データ暗号化も重要です。保存データと通信データの両方に暗号化を適用することで、万が一の情報漏洩時にも不正使用を防ぎます。
また、監視システムの導入によって、不正アクセスの検知や異常な通信の監視、ログの記録・分析により、セキュリティインシデントの早期発見と対応を可能にします。
加えて、従業員の端末管理も欠かせません。
USBメモリなど外部記憶媒体の使用制限、メール送信時の暗号化や誤送信防止システムの導入も重要な対策です。
クラウドサービス利用時は、提供事業者のセキュリティ体制を十分に確認し、自社に合ったサービスを選択する必要があります。

削除依頼・謝罪・法的対応等の初動対応
プライバシー侵害が発生した場合、被害の拡大を防ぐうえでのカギとなるのが、初動対応の速さと正確さです。
問題の投稿を発見した場合は、早めにサイトやSNSの運営会社に削除を依頼しましょう。
削除依頼する際には、各プラットフォームの利用規約や削除基準を理解し、それに基づいて具体的な権利侵害の内容や被害の実態を明確に主張することが求められます。
企業が加害者側となった場合は、事実確認と原因分析を速やかに行い、被害者への謝罪とともに、再発防止策を示す必要があります。
法的対応については、被害の程度や拡散状況に応じて、民事上の損害賠償、刑事告発、発信者情報開示請求といった手続きを検討することになります。
また、報道機関への対応や社内外への説明についても、二次被害を防ぐため慎重な検討が必要です。

専門家・弁護士への相談
プライバシー侵害問題の複雑性と専門性を考慮すると、できるだけ早く専門家へ相談することが被害の最小化において不可欠です。
法的判断が必要な局面では専門的知見が重要になります。
弁護士相談では、プライバシー侵害の成立要件の検討、損害賠償請求の可能性、削除依頼の戦略、発信者情報開示請求の要件充足性などについて具体的なアドバイスを得られるでしょう。
削除依頼や損害賠償請求などを検討した場合、弁護士へ相談すると比較的スムーズな対応が可能です。
特に、自力での手続きに少しでも不安がある方は、弁護士への相談をおすすめします。
また、企業が関与する場合は、コンプライアンス体制の整備、社内規程の策定、従業員研修の内容についても専門的な助言を得ることで、より効果的な予防策を構築できます。
無料相談を実施している法律事務所も多いため、早期相談によるリスク軽減効果は高いと言えるでしょう。
プライバシー情報の管理体制の構築
組織的にプライバシー保護体制を構築するには、責任者の明確化と定期的な監督が不可欠です。
まずは、プライバシー情報についての取扱責任者を定め、定期的に状況をチェックすることで、継続的な管理が可能になります。
取扱責任者には、プライバシー保護に関する十分な知識と権限を持つ者を選任し、全社的な情報管理を統括させるのが望ましいでしょう。
具体的な運用方法としては、業務の場面ごとに確認すべき項目を整理したチェックシートを活用し、確認漏れが生じないよう徹底します。
チェック項目には、以下の内容を含めると効果的です。
- 個人情報の収集・利用状況
- 第三者提供の記録
- 安全管理措置の実施状況
- 従業員の教育実施状況
- システムのセキュリティ状況 など
また、プライバシーインパクトアセスメント(PIA)を導入し、新しいサービスやシステム導入時に事前にプライバシーリスクを評価する体制も重要です。
問題発生時の報告ルートと対応手順を明確化し、迅速に初動対応ができる組織体制の整備も整えましょう。
個人レベルでの自衛策と情報リテラシー向上

デジタル時代のプライバシー保護には、個人レベルにおいても積極的な自衛策が必要です。
具体的な対策は以下のとおりです。
- SNS利用時のプライバシー設定の適切な管理
- 個人情報を含む写真や文書の取扱い
- パスワード管理の徹底 など
 弁護士
弁護士特に重要なのは、他人のプライバシー情報を安易に投稿しないことです。
友人との写真投稿、会話内容の公開、第三者の個人情報の言及などについて、事前に本人の同意を得る必要があります。
また、一度インターネット上に公開した情報は、完全な削除が困難であることを常に意識することが重要です。
加えて、フィッシング詐欺やマルウェア感染を防ぐためにも、怪しいリンクのクリックは回避する、ソフトウェアを定期更新する、セキュリティソフトを導入するなどの基本的な対策も継続的に実施する必要があります。
デジタルリテラシーの向上は、自分自身のプライバシーを守るとともに、他人の権利を尊重し、責任ある情報発信者としての意識を高めることにもつながります。

自分が被害者にも加害者にもならないために、常にリスクを考えて行動すべきですね。
誤解しやすいケース・グレーゾーンの判断

プライバシー侵害の判断には、多くの人が誤解しやすいグレーゾーンが存在します。
特に「既に公開されている情報」「著名人の私生活」「私的なやり取りの公開」などの境界線は複雑で、表現の自由や公益性との微妙なバランスが問題となる領域です。

例えばどういったケースがグレーなのでしょうか?
 弁護士
弁護士一度公開された情報を再び拡散する・芸能人のプライバシー範囲等、個々のケースによって判断が分かれることもあります。
公開済み情報の再拡散はOKか?
既に公開されている情報の再拡散について、多くの人が問題ないと誤解していますが、実際の法的判断は一様ではなく、極めて慎重な判断が求められます。
たとえ、新聞やインターネット上のブログで公開された内容でも、読者層の違い等を理由に非公知性の要件を再度認められる判例が出ています。
すなわち、一度公開されても永続的に保護が失われるわけではありません。
典型的なNGの例として、過去の新聞記事をSNSで再拡散する行為が挙げられます。
元記事が削除され閲覧不能となった後に、第三者が記事内容を転載投稿した事例では、最高裁が削除を命じる判決を下しています。
また、限定的な範囲で公開されていた情報(会員制サイトの記事など)を不特定多数に拡散する行為も、読者層の拡大によりプライバシー侵害となる可能性があります。
一方で以下の内容は、公益性や報道の自由の観点から再拡散が許容される場合が多いとされています。
- 政治家の公的な発言
- 公開討論の内容
- 企業の公式発表
- 既に広く報道されている事件の概要 など
著名人・有名人のプライバシー範囲
著名人のプライバシーについては、「公人だから仕方ない」という誤解を受けやすい分野です。
しかし実際には政治家、著名人に関する、公共性・公益性のある情報を公開する場合でも「知る権利の優先」が認められるのは限定的で、私生活領域は原則として保護されます。
政治家については、政策判断や政治的発言は公益性が認められやすいものの、家族関係や健康状態、個人的な交際関係などは私的領域として保護される可能性が高いでしょう。
たとえば「政治家Aには前科がある」という情報でも、投票判断において有用な情報として公益性が認められる場合と、単なる興味本位の暴露として違法とされる場合に分かれます。
芸能人については「芸能人はイメージを売る商売であり、イメージに反するような不倫などはこれを裏切るものなのだから報道してよいのだ」といった見方がありますが、これは法的には通用しない主張です。
本人の同意なく私生活を暴露することは、原則として違法とされています。
スポーツ選手や経営者についても、競技成績や経営判断は公的側面を持ちますが、私的な交際関係や家庭の問題など、個人のプライベートな情報については保護されるべき領域です。
LINE・DMの公開はどこまで許される?
LINEやダイレクトメッセージなどの私的なやり取りの公開は、プライバシー侵害の中でも特に判断が難しい分野です。
これは、「私人間のやり取りであり、公開を前提にしたもの」ではないため、私事性・秘匿性・非公知性を満たす場合にはプライバシー侵害が成立する可能性が高くなります。
たとえば、元交際相手からのラブレターやLINEのやり取りを「おもしろいから公開しよう」「嫌いな人からもらったから晒してみよう」という理由で投稿する行為がありますが、これはNGです。
たとえ相手が有名人であっても、私的な感情を表現したメッセージは高度にプライベートな情報として保護されます。
また、ビジネス上のやり取りであっても、注意が必要です。
契約交渉の詳細や内部的な意見交換などは、仮に機密情報に該当しなくても、一方的に公開することで、相手方の信用や利益を害する可能性があります。
一方で、例外的に公開が許容されるケースも存在します。
たとえば、相手方の違法行為の証拠として司法手続きで使用する場合、ハラスメントや脅迫の証拠として第三者に相談する必要がある場合などが考えられますが、これらも必要最小限の範囲に留めるべきです。
企業・組織内部の情報公開における境界線
企業や組織の内部情報の公開については、労働者の権利保護と企業秘密・個人情報保護との間で、繊細なバランスが求められます。
内部告発(公益通報)として正当化される場合と、単なる情報漏洩として違法と扱われる場合の境界線は非常に微妙です。
適法な内部告発として認められるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
- 公益性のある違法行為の存在
- 他に有効な手段がないこと
- 告発により生じる不利益と保護される利益の均衡 など
例えば、食品の安全性に関する隠蔽、環境汚染の事実隠し、労働法違反の常態化などは公益通報として保護される可能性があります。
しかし、個人のプライバシーに関わる人事情報や他の従業員の私生活、取引先の機密情報などの公開は、公益性が認められない限り、違法行為となるので注意が必要です。
また、SNSでの不用意な投稿により、意図せず企業の機密情報や同僚のプライバシーを公開してしまうケースも増加しており、投稿前の慎重な判断が求められています。
労働組合活動との関係でも、正当な組合活動の範囲内での情報公開と、個人攻撃や名誉毀損に当たる投稿の区別が重要になります。
報道・ジャーナリズムにおける取材・報道の限界
報道機関による取材・報道活動においても、報道の自由とプライバシー保護の調整が常に問題となります。
たとえ公益性のある事実に基づいた報道であっても、無制限に個人情報を公開してよいわけではありません。
個人のプライバシーに配慮した取材・報道が求められており、その境界線の判断は複雑です。
適法な報道として認められるためには、一般的に以下の要件を満たす必要があります。
- 事実の公共性
- 報道の公益目的
- 取材・報道の相当性
たとえば、事件報道では、被疑者の氏名・写真の公開、被害者のプライバシー保護、関係者への取材方法などにおいて、きめ細やかな配慮が必要です。
特に性犯罪事件では、加害者の情報公開が適法でも、被害者の身元が推測される報道は厳しく制限されます。
また、事件に無関係な家族や知人のプライバシーを侵害することは、NGです。
インターネット上の報道は、従来の新聞・テレビとは異なり拡散力が極めて高いため、より慎重な判断が求められています。
取材過程でのプライバシー侵害(無断録音・録画、私有地への侵入、執拗な追跡など)についても、報道目的があるからといってすべて許容されるわけではありません。
取材方法自体が社会的に相当と認められるものであるかどうかも、報道の適法性を判断するうえで重要な要素となります。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
デジタル社会において、プライバシー侵害は、従来とは質的に異なる深刻な人権問題となっています。
インターネット環境が持つ発信の容易性、情報の拡散性、残存性、粘着性という4つの特徴により、一度発生した被害は長期化し、被害者の人生に永続的な影響を与える可能性があるのです。
プライバシー侵害は被害者が「泣き寝入りせざるを得ない」構造的問題を抱えているため、加害者となることを避ける予防的視点と、万が一の際の適切な対応準備の両面から、継続的な取組みが求められます。
個人においても組織においても、日常的にリスクを意識し、日頃から判断力と行動力を養っておくことが、デジタル時代のプライバシー対策の要となります。

東 拓治 弁護士
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822
【弁護士活動20年】
御相談に対する迅速,正確かつ多面的な解決策の提供を信条としています!
話しやすく、アットホームな雰囲気を心がけておりますので安心して気軽にご相談下さい。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










