「突然、内容証明が届いた」
「身に覚えのない請求をされた」
「嘘の内容が書かれている」
こうした内容証明郵便のトラブルに見舞われることは、決して珍しくありません。
多くの方は、このような状況に遭遇すると「どう対応すべき?」「無視しても大丈夫なの?」「反論すべき?」と不安に感じるでしょう。
特に、事実と異なる内容や嘘の主張が含まれている場合、どう対処すればよいのか迷ってしまいます。
結論から言うと、内容証明郵便に法的強制力はありません。
その内容が嘘であった場合、慌てず冷静に対応すべきです。
ただし、中には無視せずに反論した方が良いケースもあり、場合によっては弁護士に相談することが望ましいでしょう。
本記事では、嘘・事実無根の内容証明が届いた際の具体的な対応方法から、パターン別のトラブル解決方法まで、弁護士監修のもと詳しく解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
「内容証明」とは?3分でわかる基礎知識
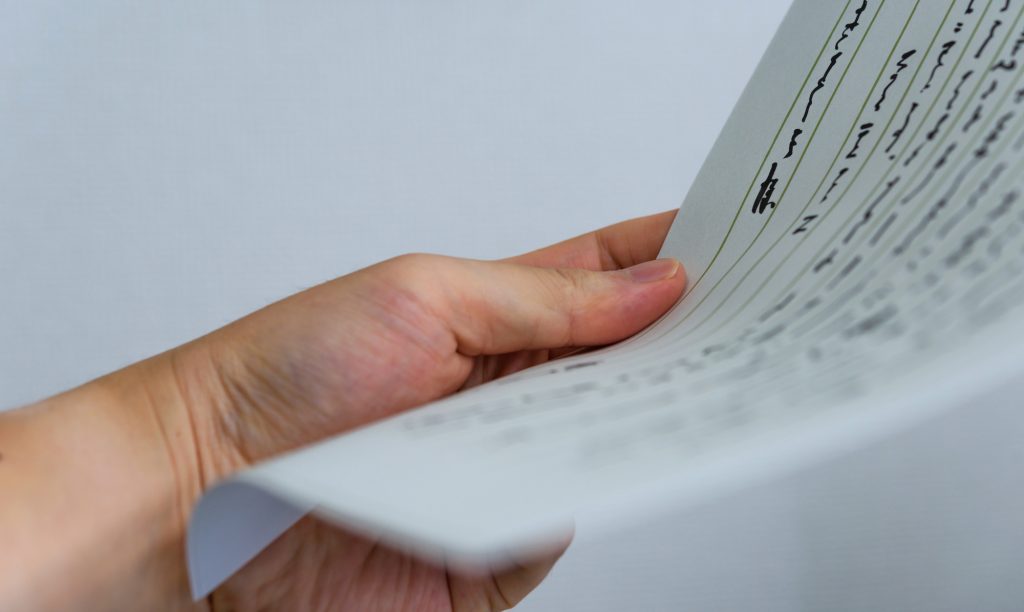
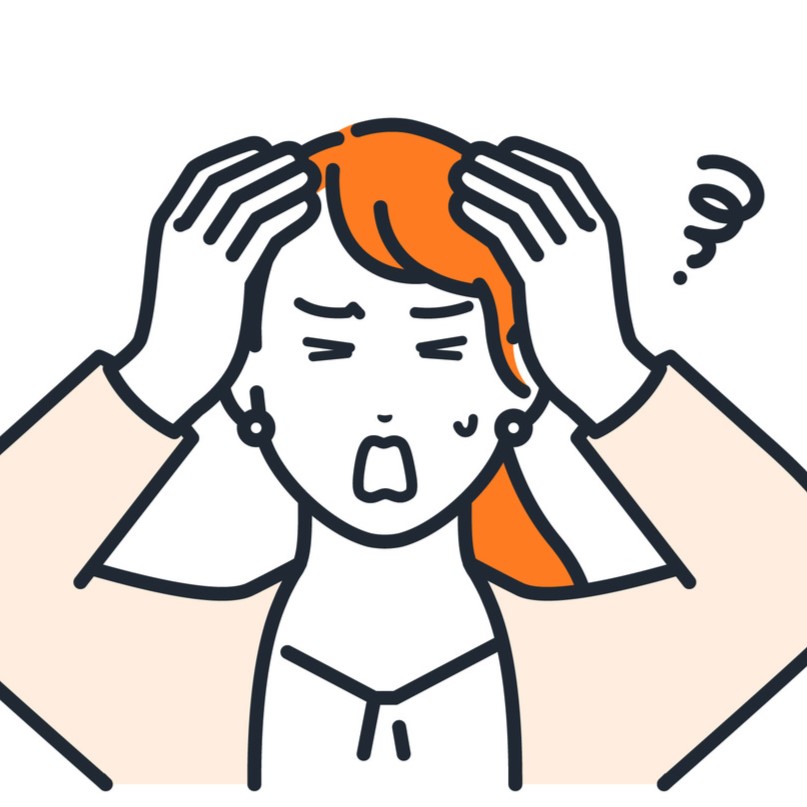
内容証明郵便が突然送られてきました…。どう対応していいかわからないためとても不安です…。
 弁護士
弁護士内容証明郵便の仕組みや目的を正しく理解しておけば、冷静に対応できるようになりますよ。
ここでは、内容証明の基本的な知識について紹介します。
内容証明郵便とは何か
内容証明郵便は、以下の内容を郵便局が証明するものです。
- いつ送ったのか
- 誰から誰あてに送ったのか
- どのような内容の文書が差し出されたか
つまり、内容証明郵便の主な目的は「法的な意思表示・通知の存在や日付を証拠として残すこと」にあるのです。
具体的には、差出人が作成した謄本(同一内容の文書の写し)によって証明されます。
送る際には3通の同一文書を用意し、1通は受取人へ、残り2通は差出人と郵便局がそれぞれ保管します。
送付した日から5年以内であれば、差出人は郵便局に保管されている謄本の閲覧請求が可能です。
内容証明が送られる典型的なパターン
内容証明郵便が利用される場面には、典型的なパターンがあります。
最も多いのは、「請求」に関するものです。
例えば、借金の返済を求める督促状や、慰謝料などの損害賠償請求、未払い賃金の請求などです。
また、法的な意思表示を明確にするケースもあります。
たとえば、契約解除や取消通知、クーリングオフの申し出などがこれに当たります。
債権譲渡通知のように、確定日付を得る目的で送られることもあります。
さらに、職場や対人関係のトラブルに関連して送られるケースも少なくありません。
「無理矢理退職させられた」という主張や、離婚協議中の配偶者からの請求など、相手に心理的プレッシャーを与える効果を狙う場合もあります。
内容証明は「内容の正確性を保証するものではない」
重要なのは、内容証明郵便は「内容の正確性を保証するものではない」ということです。
郵便局が証明してくれるのは、特定の日付に特定の人が特定の相手に対して、特定の文書を送ったという事実だけです。
その文書の内容が真実かどうか、記載されている主張に妥当性があるかどうかは証明されません。
つまり、内容証明郵便で嘘の内容や事実と異なる内容が送られてくることも十分にあり得るのです。
たとえば、慰謝料を上限まで引き上げたいがため、弁護士に事実とは異なる内容記載させることも不可能ではありません。
弁護士は依頼者からの聞き取りをもとに内容証明を作成するため、依頼者の主張がそのまま記載される場合もあるのです。
ただし、受け取った内容証明の内容が事実と違っていても、通知自体が無効になるわけではありません。
あくまでそれは「相手側の言い分」に過ぎないものとして捉える必要があります。

嘘や事実無根の内容証明が届いたときの対応方法

 弁護士
弁護士事実と異なる内容証明が届いたとき、多くの方が不安や焦りを感じますが、落ち着いて冷静に対応することが重要です。

まずは落ち着くことが大事ですね。
ここでは、嘘の内容証明が届いた際の対応方法について解説します。
【STEP1】冷静に文面を確認する
内容証明郵便を受け取ったら、まず落ち着いて文面をよく読み、内容を正確に把握しましょう。
後の対応方針を決める重要なポイントとなるため、特に「脅迫文言」や「金銭請求」があるかどうかに注目してください。
例えば、「支払いをしなければ裁判を起こす」と書かれているケースや、「期限内に返答しなければ法的に動く」といった記載がある場合は、相手がどの程度本気で法的手続きを検討しているかを見極める必要があります。
また、内容証明の中に「第三者に口外するな」という記載がある場合は、相手が問題解決よりも脅しに重点を置いている可能性も考えられます。
内容証明に書かれている主張が全く事実と異なる場合でも、どの部分が事実でどの部分が事実ではないのかを冷静に整理しましょう。
【STEP2】反論すべきか無視すべきかを判断する
内容証明の内容を確認したら、次に「反論すべきか」「無視してもよいか」を判断します。
判断するポイントは、無視することで後々不利益を被る可能性があるかどうかです。
反論すべきケース
金銭請求や訴訟予告がある場合は、基本的に反論を検討すべきです。
特に、「期限までに支払わなければ訴訟する」といった記載がある場合、その期限を過ぎても無反応でいると、相手が実際に法的手段に出る可能性が高くなります。
また、弁護士名義で送られてきた内容証明には、特に注意が必要です。
弁護士が関与している場合、単なる脅しではなく、実際に法的措置を検討している可能性が高いからです。
弁護士からの内容証明を無視すると、いきなり訴訟を起こされるリスクがあります。
さらに、たとえ内容に虚偽があっても、借金の返済請求や未払い賃金の請求など、一部に事実関係があるケースも反論を検討すべきです。
STEP1の文面の確認時同様、どの部分が事実で、どの部分に異議があるのかを明確にすることが重要になります。
無視してよいケース
明らかに嫌がらせ目的の脅し文書や、完全に事実無根である場合には、無視しても大きな問題にはならないことがほとんどです。
例えば、架空の不倫事実を主張して交際停止を求めるような内容で、慰謝料請求が含まれていない場合などが該当します。
また、相手の性格や過去の行動パターンから判断して、単なる脅しに過ぎず、実際に裁判などの法的手段に出る可能性が極めて低いと判断できる場合も同様です。
ただし、無視する場合でも、受け取った内容証明の記録は必ず保存しておきましょう。
後々のトラブルに備えておけば、証拠として役立つ可能性があります。
【STEP3】必要に応じて弁護士に相談し、証拠を保存する
内容証明を受け取った後は、専門家である弁護士に相談することが重要です。
特に、内容が複雑で自分だけでは判断しにくい場合や、高額な金銭請求が含まれている場合は、早急に法律の専門家の意見を求めるべきです。
弁護士は内容証明の法的な意味を正確に読み解き、その後の対応方針について的確な助言ができます。
また、反論が必要な場合、どのような内容をどのように伝えるべきかについてもアドバイスしてくれるでしょう。
また、証拠の保存も重要です。
内容証明の原本はもちろん、関連する会話や取引の記録、メールのやり取りなども含めて、できる限り多く保存しておきましょう。
これらは、訴訟に発展した場合に極めて重要な証拠となります。
完全に無視せず冷静な対処を
虚偽の内容証明を無視することは、必ずしも最善の選択となるわけではありません。
特に法的な請求が含まれている場合、無反応でいることで「争う意思がない」と解釈され、不利な立場に立たされる可能性があります。
また、一見すると嫌がらせ目的に思える内容証明でも、法的に対応すべき問題が隠れている場合もあります。
したがって、基本的には冷静に対処し、必要に応じて専門家の助けを借りることをお勧めします。
弁護士名義で内容証明を返信するメリット
反論が必要と判断した場合、個人で返信を作成するよりも、弁護士名義で内容証明を返信するほうが効果的です。
弁護士へ依頼することには、複数のメリットがあります。
まず、弁護士名義の返信は相手に対する心理的効果が大きく、「本気で対応する意思がある」というメッセージを伝えられます。
これによって、相手の不当な要求をけん制する効果が期待できるでしょう。
また、返信内容の法的な正確性が担保されるため、誤った表現や言い回しによって後に不利な立場に立たされるリスクを減らせます。
弁護士は法的な観点から言葉を選び、必要な主張を過不足なく記載することが可能です。
さらに、その後の交渉や対応もスムーズに進められます。
万が一訴訟に発展した場合も、初期段階から弁護士が関与していることで、一貫した対応が可能になります。
よくある質問

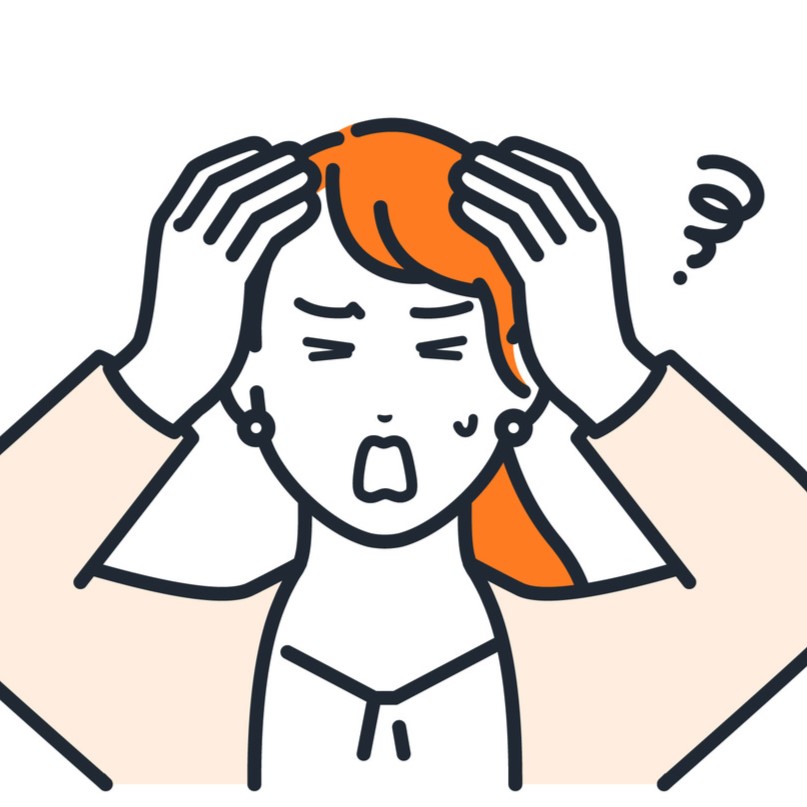
いきなり内容証明郵便が届いたら、疑問や不安でいっぱいになってしまいます…。
 弁護士
弁護士ここでは、嘘や事実無根が書かれた内容証明に関するよくある質問について、法的観点から回答します。
嘘の内容証明を送った相手を訴えられる?
嘘の内容証明郵便を送られただけで相手を訴えることは、一般的に難しいとされています。
内容証明郵便は基本的に「意思表示」の一種であり、その内容が虚偽であるというだけでは犯罪には当たらないケースがほとんどです。
ただし、内容証明の内容に「脅迫文言」が含まれている場合は、脅迫罪または強要罪に該当する可能性があります。
例えば、強要罪の場合、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」(刑法222条第2項)したことが要件となります。
内容証明に、このような内容が含まれているかどうかがポイントです。
また、内容証明に書かれていることが、明らかな名誉毀損や侮辱に当たる場合も、民事上の損害賠償請求が認められる可能性があります。
特に、第三者に対しても虚偽の事実を広めるなどの行為があった場合には、名誉毀損として訴えられるケースもあります。
しかし、単に「ありもしない不倫に対する交際停止を求める」程度の内容証明では、一般的に犯罪や不法行為として訴えることは難しいでしょう。
このような場合、警察が積極的に動く可能性も低いと考えられます。
身に覚えのない請求を無視して問題ない?
身に覚えのない請求内容の内容証明を受け取った場合、無視して良いかどうかは一概には言えません。
状況によっては無視することでリスクが生じる場合もあるからです。
まず、内容証明がまったくの事実無根や架空請求のような明らかに詐欺的な請求であれば、基本的には無視しても大きな問題にはならないでしょう。
特に相手が偽名や虚偽の住所を使用しているような不審なケースでは、真摯な法的請求とは考えにくいためです。
しかし、弁護士名義で送られてきた内容証明や、具体的な訴訟予告が含まれている場合は注意が必要です。
裁判所では内容証明も証拠として扱い、内容証明による請求を行うだけの理由があったと見解を示す可能性があります。
特に、相手が実際に訴訟を提起した場合には、反応しなかったことが裁判において不利に働く恐れもあります。
また、身に覚えがなくても、法的に何らかの関係性がある場合(例:契約関係、雇用関係など)は、無視せずに反論することをお勧めします。
その際は、「全く身に覚えのないことである。今後一切請求しないこと」という趣旨の反論を内容証明で送ることで、後の訴訟などに備えての証拠を残しておくことが重要です。
結論として、身に覚えのない請求でも、その内容や送り主、状況によって対応を変える必要があります。
判断に迷う場合は、弁護士に相談して対応を検討しましょう。
【ケーススタディ】典型パターン別対応シミュレーション

 弁護士
弁護士内容証明郵便のトラブルは様々なパターンがあります。

例えばどんな内容があるのでしょうか?
実際の対応の参考となるよう、典型的なケースごとの対応方法を解説します。
以下のケーススタディは、典型例をわかりやすく解説するためのフィクション(架空事例)です。ご自身の状況に正確に当てはめるには、専門家(弁護士等)への相談をおすすめします。
【架空事例1】不倫を捏造されたうえで交際禁止を迫られたケース
Aさんは突然、見知らぬ人物から内容証明郵便を受け取りました。
そこには「Aさんが既婚者Bさんと不適切な関係にある」として、今後Bさんと一切接触しないよう要求する内容が書かれていました。
しかし、AさんはBさんという人物を全く知らず、完全な身に覚えのない内容だったのです。
差出人は「Bさんの配偶者」としか記されておらず、慰謝料請求はなく、交際禁止の要求のみでした。
このような架空の事実に基づく内容証明は、基本的に無視しても問題ないケースが多いでしょう。
脅迫や金銭要求がなければ、法的強制力もありません。
ただし、万が一のために内容証明は保管しておき、同様の連絡が続くようであれば、法的対応を検討した方がよいでしょう。
このようなケースでは、相手は嫌がらせ目的で偽名や虚偽の住所を使用している可能性もあり、送り主を特定するのは困難であることが多いです。
 弁護士
弁護士警察に相談しても、具体的な脅迫や被害がなければ、積極的な対応は得られないケースが一般的です。
【架空事例2】元従業員から「無理やり退職させられた」と嘘を書かれたケース
会社経営者のCさんは、元従業員Dさんの代理人弁護士から内容証明郵便を受け取りました。
その内容は「Dさんは会社の業務命令を拒否したことで退職を強要された」というもの。
しかし、実際はDさんが「この仕事が嫌だから辞める」と自ら申し出て退職したという経緯があり、会社側は引き留めさえしていたのでした。
このケースでは、弁護士が関与している以上、単なる脅しではなく実際に法的措置を検討している可能性があります。
無視すると、相手の一方的な主張だけが証拠として残り、訴訟に発展した場合に不利になるリスクがあります。
適切な対応としては、事実関係を明確にした反論の内容証明を送ることが重要です。
退職に至る経緯や、退職意思の表明があったことなどを具体的に記載し、可能であれば客観的証拠(メールのやり取りや第三者の証言など)についても言及すべきでしょう。
 弁護士
弁護士特に雇用関係のトラブルは訴訟リスクが高いため、弁護士への依頼をお勧めします。
【架空事例3】歪曲した過去で元配偶者から誹謗中傷されたケース
別居中のEさんは、配偶者Fさんの代理人弁護士から内容証明郵便を受け取りました。
その内容は10年間の結婚生活を全面的に否定するような内容で、「子どもの前での暴言」「暴力的な振る舞い」など、Eさんにとって全く心当たりのない行為を列挙したものでした。
離婚調停中にこのような内容証明が届いたことで、Eさんは精神的に大きなダメージを受けています。
このような人格攻撃型の内容証明は、離婚調停や裁判において相手に不利な印象を与えることを目的とする場合があります。
特に親権や財産分与が争点となっている場合に使われるケースが見られます。
対応としては、感情的にならず、事実と異なる点を明確にした反論を準備することが重要です。
ただし、あまりにも事実を歪曲した内容の場合、「全て否認する」という簡潔な反論にとどめ、詳細な反論は調停や裁判の場で行うという選択肢もあります。
このようなケースでは、心理的負担も大きいため、単独で対応するよりも弁護士のサポートを受けることが望ましいでしょう。
 弁護士
弁護士弁護士は冷静かつ客観的な視点で法に則った対応方針を立て、解決策を見出すお手伝いをします。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
嘘や事実無根の内容が含まれる内容証明郵便を受け取ると、多くの方が不安や焦りを感じますが、基本的には冷静に対応することが重要です。
まずは内容をよく確認し、脅迫文言や金銭請求の有無などに注目しましょう。
弁護士名義の内容証明や訴訟予告を含むものは、より慎重な対応が必要です。
一方で、明らかに嫌がらせ目的と思われるケースは、場合によっては無視するという選択肢もあります。
判断に迷ったときは、法律の専門家に相談しましょう。
また、必要に応じて証拠を保全しておくことで、万一の訴訟にも備えられます。
内容証明は「内容の正確性を保証するものではない」という点を理解し、感情的にならず法的視点から適切に対応すれば、多くの場合は問題の解決が可能です。

東 拓治 弁護士
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
電話 092-711-1822
【弁護士活動20年】
御相談に対する迅速,正確かつ多面的な解決策の提供を信条としています!
話しやすく、アットホームな雰囲気を心がけておりますので安心して気軽にご相談下さい。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------









