「突然、内容証明郵便が自宅に届いた…」
「身に覚えのない差出人からの通知だけど、受け取るべき?」
「法的な書面を受取拒否したら問題になる?」
日常生活において、こうした内容証明郵便を初めて受け取る方にとっては、「何か重大な問題が起きたのでは」と心配になるのではないでしょうか?
そうした時、受け取るべきか、それとも拒否すべきか迷ってしまうのも当然だと思います。
まず、内容証明郵便そのものには法的強制力はありませんが、受取拒否は問題解決にはなりません。
かえって状況を悪化させる可能性が高いのが実情です。
また、身に覚えがない場合でも、受け取って内容を確認することが適切な対応の第一歩となります。
一方で、明らかに詐欺的な内容や事実無根の主張については、専門家のアドバイスを受けながら対応することが重要です。
本記事では、内容証明郵便を受取拒否した場合の法的リスク、適切な対応方法、そして差出人別の具体的な対処法について、実際の判例や事例を交えて詳しく解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
内容証明郵便はどんな目的で送られるのか
内容証明郵便とは「いつ(日時)、誰が(差出人)、誰に(宛先)、どんな文書を送ったか(内容)」を郵便局が証明する郵便物のことです。
内容証明郵便は受け取った日時等の履歴を確認でき、かつその中身がどんなものであったかも証明されるため裁判上の証拠能力があります。
通常の郵便と違い受け取った人が「そんな郵便は届いていない」「そんな内容は書いていなかった」等の言い逃れができなくなります。
そのため、差出人が「自分の意思を相手に伝えた」という事実を証明したい場合に用いられることが一般的です。
送った日付や受取人が受け取った日付が重要になるケースには、以下のようなものがあります。
- クーリングオフ
- 契約の解除通知
- 金銭の請求
- 債権譲渡
- 時効の中断等
また、通常の郵便と違ってポスト投函ではなく配達員が直接手渡しを行い、受領の際に押印(サイン)が求められます。
文書の最後には「この郵便物は令和○○年○月○日、第×××××号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 郵便事業株式会社」と押印されます。
通常の郵便よりはるかに格式張ったものになっているため、受け取った側に「重大な事態になっているのではないか」という心理的プレッシャーを与える目的でも利用されることが多いです。

内容証明郵便が届いたときの心理的影響と実践的な対処法
内容証明郵便が突然届くと、多くの方が不安や恐怖を感じます。これは自然な反応であり、心配する必要はありません。
一般的な心理的反応
内容証明郵便を受け取った時の一般的な心理的反応には、次のようなものがあります。
- 「深刻な問題が起きたのでは」という不安や恐怖
- 「すぐに対応しなければ」という焦り
- 「何が起きているのか理解できない」という混乱
- 「理不尽な要求をされている」という怒り
これらの感情は自然なものですが、冷静な判断を妨げる可能性があります。
具体的な対処法
重要なのは、感情的にならず冷静さを保つことです。内容証明郵便は単なる通知手段であり、それ自体に法的強制力はありません。ただ、相手があなたに意思を伝えたいという意図の表れです。
不安を感じたら、次の手順で対処しましょう。
- 深呼吸をして冷静になる:決して慌てて行動しない
- 内容をしっかり確認する:要点をメモしながら、何が求められているのかを整理する
- 関連資料を集める:過去の契約書や請求書など、関連する書類を集めておく
- すぐに返信せず、専門家に相談する時間を確保する:感情的な返答は事態を悪化させることがある
心理的プレッシャーへの対応
内容証明郵便は、受取人に心理的プレッシャーを与えることも意図されている場合があります。しかし、多くの場合、即日対応が必要なわけではありません。冷静に内容を検討し、必要であれば法的助言を得るための時間は十分にあります。
「すぐに支払ってください」「直ちに対応してください」といった文言があっても、数日程度の検討期間を設けることは合理的です。その間に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
内容証明郵便を受け取ることで必ずしも相手の主張を認めたことにはなりません。受け取りは単に内容を確認したという事実を示すだけです。
内容証明郵便に法的効力や強制力はあるのか

内容証明郵便はあくまで「どんな内容の文書が送られたか」を証明するものであり、その内容の正確性・正当性を証明するものではありません。
例えば、「○月○日までに○○○円を支払って欲しい」という旨の内容が記載されており、それを無視したからといって直ちに差し押さえといった事態にはなりません。
内容証明郵便の法的効力は「裁判上の証拠能力がある」という点です。
「いつ、誰が、誰に、どのような内容の意思表示を行なったか」ということが、送った日時、受取人が受け取ったまたは受け取りを拒否した日時とあわせて全て証明できます。
内容証明郵便が送られてきたということは、差出人が後々裁判で争う際の証拠を残したいという意思の表れであり、何かしらの法的措置を準備しているということです。
身に覚えがない内容証明郵便は受取拒否できる?
内容証明郵便は、配達員が直接受取人本人に受領印か署名をもらった上で手渡すことが定められています。そのため、受取人が「自分宛ではない」「サインはしない」と主張すれば、受取拒否が可能です。
この場合、配達員は郵便物を持ち帰り、差出人へと返送されます。その際に「○月○日受取を拒否」という記録が残ります。
また、受取人が居留守を使っても、配達員が勝手にポストに内容証明郵便を投函することはできなません。そのため、不在通知がポストに投函されることになります。
その後は7日間郵便局に保管されま、受取人からの再配達の依頼がなければ差出人に返送される仕組みです。
内容証明郵便の督促から法的手続きへの移行タイミング
内容証明郵便による督促を無視し続けると、どのようなタイミングで法的手続きに移行するのでしょうか。一般的には以下のような流れになることが多いです。
1回目の内容証明郵便
1回目の内容証明郵便は、相手に対して問題の存在を正式に伝え、任意の解決を促す目的で送られることが多いです。この段階では、まだ訴訟などの法的手続きは開始されていません。
文書には通常、「〇日以内にご連絡ください」「〇月〇日までにお支払いください」といった期限が設定されています。この期限は法的に絶対のものではありませんが、無視し続けると次のステップに進むこととなります。
2回目の内容証明郵便(催告)
1回目の内容証明郵便に反応がない場合、一定期間(通常1〜2週間)経過後に2回目が送られることがあります。この段階では「最終通告」として、法的手続きに移行する可能性を明示してくることが一般的です。
文面は厳しい表現となり、「本通知をもって最終通告とします」「次回は法的手続きに移行します」といった文言が使われることが多いでしょう。
訴訟提起や支払督促などの法的手続き
2回目の内容証明郵便にも反応がない場合、差出人は裁判所を通じた法的手続きに移行することが多いです。具体的には以下のような手続きが取られます。
- 支払督促:簡易裁判所から支払い命令が届く
- 少額訴訟:60万円以下の請求で簡易な裁判手続き
- 通常訴訟:裁判所からの訴状が届く
これらの書類が届いた場合は、無視せず応じる必要があります。特に支払督促に対して2週間以内に異議申立てをしないと、債権者が強制執行の手続きに進むことが可能になりますので、注意が必要です。
強制執行の段階
訴訟で敗訴した場合や支払督促が確定した場合、さらに支払いがないと強制執行の手続きに進むことがあります。この段階では、給与や預金口座の差押え、財産の競売などの法的措置が取られる可能性があります。
そのため、内容証明郵便の段階で解決を図ることが、時間・費用・労力の面においてもっとも効率的です。法的手続きに進むと、解決までにかかる負担は格段に大きくなります。
内容証明郵便は受取拒否したらどうなる?

先述の通り、受取拒否をした場合は差出人へ返送され、受取拒否の記録が残ります。
しかし、受取拒否に関しての記録はただその事実が記録として残るだけで「受取人が身に覚えのない差出人と申し出たため」といった受取拒否の理由は記録されません。
例えば、借金をしていてその督促で送られてきた場合、差出人(債権者)は回収代行業者や弁護士に書類作成を依頼することもあります。
差出人が会社名や弁護士名になっていると、債権者の名前ではない=身に覚えのない差出人だと誤った判断してしまう可能性も。
差出人側(債権者)には督促行為を行なっていたという記録が残り、督促があったにもかかわらず受取人(債務者)が無視し続けたとなると、強制執行等の手続きが取られてしまう可能性があります。
内容証明郵便は、受け取らないとどういった内容の文書が入っているかはわかりません。自分が知らない間に事態が悪い方向に進むリスクを無くす意味でも、内容証明郵便は受け取った方がよいでしょう。
先程の借金の例でいえば、返済が苦しくても連絡が正常に取れる状態と債権者に認識されていれば、交渉によっては返済期日が延長される可能性もあります。
内容がデタラメの場合は無視してもいいの?
内容証明郵便の内容が不当なものであれば、仮に訴訟を起こされたとしても裁判所が認める可能性は低いため、詐欺のような明らかに不当な内容であれば無視しても構いません。(※ただし、後々差出人が訴訟を起こした場合、裁判所からの通知を絶対に無視してはいけません)
しかし、自分が把握していないだけで、内容証明郵便に記載されている内容が事実である可能性もあります。その場合、無視したという事実だけが残り、後々不利になる可能性が高くなります。
近年は架空請求詐欺のような悪質な詐欺にも内容証明郵便が利用されるケースもあり、内容が明らかに事実と異なるとわかる場合は無視しても法律上不利益を被る可能性は高くありません。
明らかに不当といえない内容であれば不利益を被る可能性があるため、弁護士に相談し、どういった手続きをとるべきかを相談しましょう。
また、自分で返事をすることが一番リスクの高い選択肢になります。
例えば、契約書なしで100万円を借金していて、「500万円の返済を請求する」という文書が届いた場合に、「500万円も借金していない。自分が借りたのは100万円だ」という返事をすれば、結果的に、100万円の借金を本人が認めているという証拠になってしまいます。
内容が不当か否かは非常に判断が難しく、受取人側が不当だと思っても差出人側からしてみれば正当であることは少なくありません。
いずれにしても、弁護士に相談の上で内容が不当であるか、差出人に対して返信をするべきかといった行動を起こしておいた方が後々大きなトラブルに巻き込まれるリスクは減るでしょう。
【パターン別】内容証明郵便を受取拒否した場合の対応方法
内容証明郵便の受取拒否を考える場合、以下のパターン別の対応と結果を理解しておくことが重要です。
差出人が個人の場合
差出人が個人名で、内容が全く予測できない場合でも、受取拒否は慎重に判断すべきです。個人間のトラブルでも、後に法的手続きに発展する可能性があるからです。
例えば、近隣トラブルや貸し借りのトラブルに関する内容証明郵便の場合、受取拒否をすると相手の態度が硬化し、直接的な対立に発展するリスクがあります。まずは内容を確認し、必要に応じて弁護士に相談するのが賢明です。
差出人が企業・団体の場合
企業や団体からの内容証明郵便は、契約関係や取引に関わる重要な通知である可能性が高いです。受取拒否をすると、相手方企業の対応が厳しくなることが予想されます。
特に、金融機関や通信会社などからの内容証明郵便の場合、支払い遅延や契約不履行に関する重要な通知かもしれません。内容を確認せず拒否すると、事態がさらに悪化し、裁判手続きに移行するスピードが速まる可能性があります。
差出人が弁護士・法律事務所の場合
内容証明郵便が弁護士名義の場合、受取拒否は避けるべきです。
弁護士名義の内容証明郵便は、すでに法的対応の準備段階であることが多く、拒否すると裁判所からの書類が届く可能性が高いです。弁護士に代理される相手との交渉では、あなたも法的なサポートを得ることが望ましいでしょう。
差出人が公的機関の場合
官公庁や自治体からの内容証明郵便の拒否は、行政手続き上の不利益を招く恐れがあります。公的機関からの通知は必ず確認すべきです。
例えば、税務署や市役所からの内容証明郵便の場合、期限付きの重要な通知である可能性が高いです。そのため、受取を拒否すると法定期限を逃し、さらなる罰則や不利益を被る可能性があります。
これらのケースでは、基本的には受け取って内容を確認し、専門家に相談することをおすすめします。受取拒否は一時的な問題回避にはなっても、根本的な解決策にはなりません。
内容証明郵便の受取拒否に関する法的判例
内容証明郵便の受取拒否が法的にどのように扱われるかについて、実際の判例を見てみましょう。
意思表示の到達に関する判例
最高裁判所第二小法廷平成10年6月11日判決では、不動産取引における意思表示の到達時期が争われました。この事件では、マンション分譲契約の解除通知が内容証明郵便で送られましたが、受取人が不在で郵便局に留め置かれていた間に期限が経過した事例です。
最高裁は「意思表示は相手方が通常了知し得べき状態におかれたときに到達したとみなされる」との基準を示し、郵便局での保管期間内に受け取る機会があったにもかかわらず受け取らなかった場合は、法的には「到達した」と判断されうることを明らかにしました。
賃貸借契約解除通知の判例
東京地裁平成17年9月14日判決では、賃料滞納を理由に賃貸人が内容証明郵便で解除通知を送付しましたが、賃借人が意図的に受取拒否したケースが扱われました。裁判所は「賃借人は普段から同住所で生活しており、郵便物を受領可能な状態であったことが認められる」として、受取拒否があっても法的に到達したとみなしました。この判例により、内容証明郵便を故意に拒否しても、契約解除などの法的効果を妨げることはできないことが示されています。
契約解除意思表示の判例
大阪高裁平成20年2月28日判決では、建設請負契約の解除通知が内容証明郵便で送られたものの、受取人が「差出人に心当たりがない」として受取拒否したケースが審理されました。高裁は「相手方の住所地に配達され、相手方が受け取ろうと思えば受け取れる状況にあった」として、意思表示が有効に到達したと認めています。
さらに、「受取拒否は相手方が自ら作出した事情であり、その不利益は相手方が負うべき」との考え方も示されました。 これらの判例から分かるように、単に受取拒否をしたというだけでは法的責任から免れられないケースが多いのです。内容証明郵便を受け取らないことでかえって不利な立場に立つ可能性があることを理解しておきましょう。
内容が事実である場合の必要な対応

通常の郵便ではなく内容証明郵便で送ってきたということは、差出人はこの書面を証拠とする意思があると考えられます。つまり、後々の法的手段のための一手を打ってきた状態であり、受け取った側もなるべく早く手を打つ必要があります。
弁護士名等で送られてきた場合は、差出人が弁護士に依頼し法律に基づいて行動しているので、迂闊な対応を取ると差出人が望む通りに話が進むことになります。
借金の督促等、金銭が絡む問題の場合であれば、借り手側に連絡がつく状態とそうでない状態では印象が全く異なり、債権者の対応もそれに伴って変わってきます。
しかし、先述の通り、下手に回答してしまうとその回答を証拠として取られることになり、不利益が大きくなる可能性があります、電話で急ぎの確認をしたとしても、相手方が録音している可能性が高いため、弁護士に相談する前にすぐに相手と連絡を取るのは得策ではありません。
訴訟を起こされ、それを放置してしまうと相手方の主張をすべて認めたとみなされるため、差出人の言い分が全て通る形で判決がなされます。
内容証明郵便の適切な受取方法と保管の重要性
内容証明郵便を受け取った後の、適切な取り扱いと保管方法について説明します。
受け取り時の注意点
内容証明郵便を受け取る際は、封筒や書類の状態をしっかり確認しましょう。破損や開封の形跡がある場合は、配達員の前でその旨を伝え、メモを残しておくことをおすすめします。
受取日時も重要な情報になりますので、受け取った日付をメモしておきましょう。また、配達証明付きの内容証明郵便が届いた場合、受取人の署名やハンコが必要となります。
内容の記録と整理
内容を確認したら、受け取った日時や内容の要点をメモしておきましょう。特に以下の点に注目して記録しておくと良いでしょう。
- 差出人の名前と住所
- 郵便の差出日と受取日
- 文書に記載されている重要な期日や金額
- 求められている対応や回答
適切な保管方法
内容証明郵便とその関連資料は、湿気や直射日光を避け、クリアファイルや専用のフォルダに入れて保管しましょう。デジタル化(スキャンやコピー)しておくと、紛失リスクを減らせます。
特に重要なポイントは以下のとおりです。
- 原本はそのまま保管し、折り曲げたり破ったりしない
- 封筒も一緒に保管する(消印や宛名が証拠になることがある)
- 関連する書類と一緒にまとめて保管する
- 時系列順に整理しておくと後で確認しやすい
保管期間の目安
内容証明郵便は、案件が完全に解決するまで、あるいは関連する法的時効が完了するまで保管することをおすすめします。一般的な債権の時効期間は5年ですが、内容によっては10年以上保管が必要な場合もあります。
特に重要な内容証明郵便(契約解除通知や督促状など)は、関連する権利義務が完全に消滅するまで保管することが安全です。不動産や相続関係の内容証明郵便は、より長期間の保管が必要になる場合があります。
適切に保管された内容証明郵便は、将来的に法的トラブルが発生した際に重要な証拠となります。
必ず返信しないといけないケース、不利になるケース

何かしらの返答を求められている場合は、無視すると不利益を被る可能性が高い内容証明郵便で送られてくるものの多くは、受取人に対して何かしらを請求することがほとんどですが、中には返答を求めてくるものがあります。
これに関して、返答しないということが意思表示とみなされるケースがあるため、
文中に返答を求めるあるいは「返答がなければ〇〇」といった文がある場合は必ず返答しましょう。
例)契約を解除するか否か
受取人が何らかの理由で契約を解除できる状態にあるにもかかわらず解除しないままの時に、契約の相手方から契約を解除するか否かの判断を求める内容証明郵便が届くケース。
「○○年○月○日までに契約を解除するか否かの連絡を求める」といった旨の内容が届き、これに返答しないままであれば、その日付以降、受取人はその契約を解除することができなくなってしまいます。
(民法547条 催告による解除権の消滅)
例)商取引の通知
受取人が商人であり、受取人が通常取り扱っている商品について「○○について、○○円での購入を申し込みます」等の取引の申し込みが内容証明郵便で送られてきたケース。
受取人がこれに対して特に返答がなければ、その申し込みを承認したとみなされ、その取引(差出人の条件)が成立します。
(商法509条 契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
例)相続を受けるか否かの通知
内容証明郵便の受取人が、遺言により相続財産の受取人となっている場合に、関係者からその遺言を受けるか放棄するかの返答を求められるケース。
「〇〇年○月○日までに遺言を承諾するか放棄するかの返答を求める」という旨の内容が通知され、
これに対して返答がない場合は相続を承諾したとみなされます。
(民法987条 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
まずは弁護士に相談しよう

「内容証明郵便を無視するという選択は可能だが、リスクが大きい」ということがここまでの解説でお分かりいただけたと思います。
自分にとって不当と思える内容でも、相手方にとっては正当であり、それが法律的に見ても妥当という可能性は大いにあります。
繰り返しますが、内容証明郵便を出すという時点で、差出人は法律的手段に出る意向があり、その書面を証拠とする意図があります。
弁護士に相談の上で作成された可能性は高く、場合によっては依頼済みで弁護士を代理人としています。
法律のプロに対抗できる手段は、こちら法律のプロに頼るということです。特に、金銭問題の場合は対応方法を誤ると窮地に立たされることもあります。
まずは相談してみて、どこまで弁護士の力が必要か、どうすればより良い結果となるのかを慎重に検討しましょう。
内容証明郵便の受取拒否に関するよくある質問(FAQ)
内容証明郵便の受取拒否について、多くの方が抱える疑問に回答します。
内容証明郵便を受け取らなかった場合、法的にどうなりますか?
受け取らなかった場合でも、状況によっては「到達」したとみなされる可能性があります。特に意図的に受け取りを避けているとみられる場合は、裁判でその点が不利に働くことがあります。判例では、受取人が受け取ることができる状況であったと認められる場合、受取拒否をしても法的効果が発生するとされています。
内容証明郵便の不在通知を無視し続けるとどうなりますか?
不在通知が投函された場合、約1週間保管された後に差出人に返送されます。しかし、これにより問題が解決するわけではなく、差出人は別の手段で連絡を取ろうとするでしょう。最終的には訴訟に発展する可能性もあります。また、「意図的に受け取りを避けている」と判断されると、裁判において不利に働くことがあります。
身に覚えのない差出人からの内容証明郵便は無視しても大丈夫ですか?
基本的には受け取って内容を確認することをおすすめします。差出人名が見知らぬものでも、実際は知っている相手からの委任や代理の可能性があります。例えば、債権者が弁護士や債権回収会社に依頼している場合などです。内容を確認せずに対応を誤ると、後々不利益を被る恐れがあります。
内容証明郵便を受け取った後、どれくらいの期間保管すべきですか?
内容証明郵便は重要な法的文書ですので、少なくとも該当案件が完全に解決するまで、できれば関連する時効期間が経過するまで保管することをおすすめします。一般的な債権の時効は5年ですが、案件によって異なりますので、弁護士に相談するとよいでしょう。重要な契約関係の文書は10年以上保管しておくと安全です。
弁護士からの内容証明郵便は必ず受け取るべきですか?
弁護士名義の内容証明郵便は、受け取るべきです。弁護士が送ってくる内容証明郵便は、法的手続きへの移行を検討している段階であることが多いので、無視すると状況が悪化する可能性が高いでしょう。早めに内容を確認し、あなた自身も弁護士に相談することをおすすめします。
内容証明郵便を受け取ると、相手の主張を認めたことになりますか?
内容証明郵便を受け取るだけでは相手の主張を認めたことにはなりません。受け取りは単に内容を確認したという事実を示すだけです。実際の対応は、内容を確認した後に決めることができます。むしろ、受け取らないことで状況を悪化させる可能性があります。
内容証明郵便を送ったが受取拒否、無視された場合の正しい対応方法
この項では、内容証明郵便を送付したにもかかわらず、相手に受け取りを拒否された、または無視された場合に、送付した側が取るべき対応について説明します。
内容証明郵便が受取拒否されたり、無視されたからといって、送付者にとって不利益が生じるわけではありません。受取を拒否された場合でも、内容証明郵便を送付したという事実自体が証拠として残ります。
そのため、必要な手続きを順を追って進めていけば問題ありません。
ただし、トラブルが想定されるような相手の場合は、一度内容を見直したうえで再送し、相手が冷静に状況を受け止められるよう配慮することも検討すべきでしょう。
弁護士名義で再送
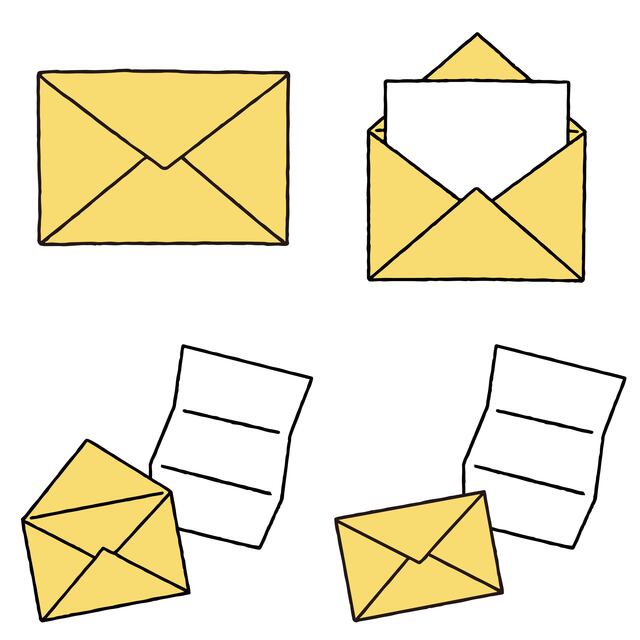
差出人を個人名で送っていたのであれば、弁護士に依頼し、改めて弁護士名で内容証明郵便を送ります。
受取人に対してより強く重要性を示すことができ、法的手段が視野に入っていると伝わりますので、それだけで受取人の態度が変わり、返答の連絡もより可能性が高くなります。
債権回収に関わる場合
支払督促
相手方の住所の管轄の簡易裁判所に申立をすることで裁判所から債務者に督促をしてもらうことができます。
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申し立てがなければ、債権者は裁判所に対して強制執行の申立をすることができます。
債務者から異議が出ると通常の訴訟に移行することになります。
少額訴訟
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できる、原則として1回の審理で判決をする訴訟手続です。
簡易的な手続きとはいえ訴訟であることには変わりないので十分な証拠を用意しておく必要があります。
ただし、少額訴訟は債務者(訴訟をおこされた側)が審理を拒否することができるため、異議申し立てが行われた場合は通常の訴訟に移行することになります。
支払督促も少額訴訟も、相手方に弁護士がついていない、または異議が出る見込みがない時に利用したほうがよいでしょう。
民事訴訟
民事訴訟は、通常の訴訟(裁判)です。
相手方に弁護士がついている場合は、最初から民事訴訟の方向で話が進むでしょう。
とはいっても、実際は裁判に行く前に和解に応じるケースが多く、早期に解決できる可能性も十分にあります。
最後まで争い判決が確定したあとは、判決に基づいて強制執行が可能です。
強制執行
上記の支払督促や少額訴訟、民事訴訟が終わった後に強制執行が可能になります。
強制執行により差し押さえられるだけの財産を債務者が持っていなかったり、差し押さえられる前に資産を移動・処分されたりしないように、仮差押さえの手続きをするのが通常です。
和解
訴訟に発展する前または訴訟中に債務者との和解もひとつの選択肢です。
和解の条件は双方で話し合い、公正証書にして残しておきましょう。
公正証書には裁判の確定判決と同じ効果があるため、和解条件を債務者が破った場合等、万が一のときに強制執行が可能です。
内容証明郵便を利用することで、債務者に対して事態の重要性をよりわかりやすく認識させることができるため、それ以降債務者が支払いに応じる可能性は高くなります。
円滑な債権回収のために弁護士に相談してみましょう。
まとめ
内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どんな内容を送ったか」を郵便局が証明する重要な郵便物です。受け取った時点で法的強制力が発生するわけではありません。
受取拒否すると差出人に戻り、「受取拒否」の記録が残ります。これにより差出人の印象を悪くし、より厳しい法的手段への移行を早めてしまう可能性があります。また、実際の裁判では受取拒否をしても、法的効果から逃れられるわけではないとの判例が出ています。
内容が不当だと思える場合でも、一度受け取って内容を確認し、弁護士に相談することがおすすめです。特に弁護士名義や公的機関からの内容証明郵便は、無視すると状況が悪化する可能性が高いです。
内容証明郵便を受け取った場合は、適切に保管し、記録を残しておきましょう。これは将来的にトラブルが起きた場合、役に立ちます。
内容証明郵便への対応は、その後の展開を大きく左右します。感情的にならず、冷静に対応し、専門家のアドバイスを受けるべきです。必要な場合は弁護士に依頼することで、トラブルを最小限に抑え、最良の解決策を見つけることができるでしょう。
また、今後の様々なリスクに備え、弁護士保険にご加入いただくこともオススメします。

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。
※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------










