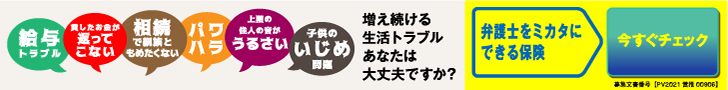「家族が亡くなって葬儀費用が必要なのに、銀行口座が凍結されて引き出せない…」
「遺産分割協議がまとまらず、母の生活費も払えない状況が続いている…」
「他の相続人が非協力的で、必要な費用すら引き出せずに困っている…」
相続が発生した際に、こうした状況に直面することは珍しくありません。
特に、相続人の一人が遺産分割に非協力的な場合、緊急に必要な葬儀費用や被相続人の配偶者の生活費さえも確保できないという深刻な問題が生じがちです。
そんなとき、『弁護士に相談して遺産分割調停を申し立てるべきか?』『法的に預金を引き出す方法はないのか?』『家庭裁判所に何らかの申立をすべきか?』といった疑問が浮かぶかもしれません。
2019年の民法改正により「遺産分割前の払戻制度」が新設され、遺産分割協議が成立していなくても、一定の条件下で相続預金の一部を単独で引き出すことが可能になりました。この制度により、各相続人は法定相続分の3分の1に相当する金額(ただし金融機関ごとに150万円が上限)まで、他の相続人の同意なしに払戻しを受けることができます。
ただし、この制度を利用する際には、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの必要書類を準備し、金融機関所定の手続きを行う必要があります。
本記事では、遺産分割前の払戻制度の具体的な要件、必要書類、利用時の注意点について、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
従来は遺産分割が成立するまで引き出す方法はなかった。

従来は、遺産分割が成立するまでの間は、たとえ葬儀費用や生活費がすぐに必要になる場合であっても、相続人が単独で亡くなった人の銀行口座の預貯金の払戻をすることはできませんでした。
なぜなら、平成28年12月19日の最高裁判例で、亡くなった人の預金口座からお金を引き出すことは、遺産分割が成立しない限りできないとされたからです。
(正確に言うと、相続された預貯金債権は遺産分割の対象になるため、共同相続人による単独での払戻しができない、ということが判示されました)
つまり、銀行口座に十分なお金が入っていたとしても、1人の相続人が応じないというだけで銀行口座のお金を使うことは一切できなくなっていたのです。
そのため、葬式やお墓を建てる費用を相続人の誰かが立て替えるしか方法がありませんでした。
民法改正で遺産分割前でも払戻ができるようになった!

(1)遺産分割前の払戻制度
しかし、2019年(令和元年)7月1日に施行された民法改正により、次の要件を満たす場合には相続人が単独で亡くなった人の銀行口座の預貯金の払戻しをすることができるようになりました。
これを遺産分割前の払戻制度といいます。
(2)どうして改正されたの?
相続人間で遺産分割協議がまとまらず預貯金が誰のものかが決まらないときでも、相続人が葬儀費用や当面の生活費に困るといったことが起こらないようにしよう、というのが今回の改正の目的です。
ただ、一定のルールを設けることで遺産分割における相続人間の公平を図ることも忘れていません。
(3)注意点-利用できない場合
なお、「遺言書」があって「預貯金についての権利が誰のものか明らかな場合」には、その預貯金は権利を持った相続人にしか引き出せず、他の相続人がこの制度を利用することができませんので注意が必要です。
具体的な「遺産分割前の払戻制度」の内容は?

条文にはどんなことが書いてあるの?
まずは改正民法909条の2の条文を見てみましょう。
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
漢字が多くて何を言っているのかわからないですね・・・
そこで、要件と効果をわかりやすく書いてみます。
要件 ~どういう場合に預金を下ろせるの?~
要件
①遺産に属する預貯金債権であること
②総額が、「法定相続分×3分の1」の範囲内で、
かつ、
1金融機関の引出額が法務省令が定めた限度額(当面は150万円)の範囲内であること
です。
① 遺産に属する預貯金債権であること
遺産に該当する預金口座ではないとダメなのは、ある意味当然の要件です。
② 総額が、「法定相続分×3分の1」の範囲内で、かつ、1金融機関の引出額が法務省令が定めた限度額(当面は150万円)の範囲内であること
法定相続分のすべてを引き出すことはできません。
あくまで「法定相続分×3分の1」の範囲内です。
しかも、1つの銀行の引出額は「150万円まで」とされています。
1つの銀行にたくさんの口座があっても150万円までです。
なお、この「150万円」はあくまで当面の数字なので、今後法務省令が変われば増減する可能性があります。
(限度額が増えることはあっても減ることはないように思います)
効果 ~払戻制度により払い戻したお金は遺産分割でどのように扱われる?~
効果
①単独で払い戻しができる。
②払い戻しをした預貯金債権については、その共同相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなす。
① 単独で払い戻しができる。
これまで説明してきたように、他の共同相続人の同意がなくても、1人で払い戻しができるようになります。
つまり、今回のケースでは
もしXが銀行から葬儀費用を引き出したいという場合には
Xの法定相続分は300万円なので、
Xはその3分の1である「100万円」までは引き出せるということになります。
また、母Zが葬儀費用を引き出す場合には
母Zの法定相続分は600万円なので、
Zはその3分の1である「200万円」までは引き出せるということになります。
ただ、「1銀行150万円まで」という制限があるので、
1つの銀行口座しかない場合には
葬儀費用150万円を引き出すか母Zの生活費として50万円を引き出すかの判断が必要になります。
② 払い戻しをした預貯金債権については、その共同相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなす。
払戻しを受けた相続人は、そのお金について「遺産の一部の分割を受けた」とみなされることになります。
したがって、その後の遺産分割のときには、そのお金を遺産の一部としてすでに受け取ったことを前提に、他の相続人と残りの遺産の分け方を話し合うことになります。
つまり、今回のケースでは
もしXが「100万円」を引き出した場合には
法定相続分である300万円のうち100万円は遺産分割を受けたとみなされますので
Xが相続できるのは残り200万円であることを前提に話をしていくということになります。
必要書類は?

銀行によって扱いが異なることもありますが、手続のためには以下の書類が必要です。
具体的には、電話等で確認するのがよいでしょう。
① 被相続人の戸籍謄本(原本)
- 1年以内に発行したものであること
- 生まれたときから死亡するまでの連続した戸籍謄本があること
に気をつけて取得しましょう。
今回のケースですと「亡くなった父A」の生まれたときから死亡するまでの連続した戸籍謄本が必要です。
② すべての相続人の戸籍謄本(原本)
- 1年以内に発行したものであること
- 亡くなった人との関係がわかるものであること
が必要です。
今回のケースですと、相続人である私X、妹Y、母Zの戸籍謄本が必要となります。
③払戻しを希望する相続人本人の印鑑登録証明書(原本)
発行より3~6か月以内のものを要求されることが多いです。
今回の改正民法はいつの相続から適用されるの?(改正民法の施行日はいつからか?)
今回の改正民法の施行日は「2019年(令和元年)7月1日」です。
しかし、施行日前に発生した相続であってもこの払戻制度を利用することは可能です!
ですので、今後すべての相続のケースで利用できる、ということになります。
これは嬉しい話ですね。
Q&A

(1)預金の権利を他人に譲った場合等はどうなる?
- 預金についての権利を相続人が他人に譲って、その他人が預金の払戻しを請求する
- 相続人の債権者が亡くなった人の銀行口座の預金を差し押えて払戻しを請求する
ということもできるのでしょうか?
結論から言うとこれは「できない」です。
上の「どうして改正されたの?」でも書きましたが、今回の改正は、遺産分割協議がまとまらないときでも、「相続人」が葬儀費用や当面の生活費に困るといったことが起こらないようにしよう、ということにありますので、「相続人」のために作られた制度なのです。
ですので、権利を譲り受けた人や債権者のために作られていないため、この人たちが利用することはできないのです。
(2)生前にたくさんもらっている相続人でも利用できちゃうの?
生前に亡くなった人から多額の贈与を受けていた相続人がさらに払戻制度を利用して預金の払戻しを受けても問題ないのでしょうか?
たしかに、もし払戻制度を利用してしまうと、「もらいすぎ」になってしまう可能性がありますよね。
相続人が生前に多額の贈与を受けたことにより具体的な相続分がないような場合には、法的な手段により払戻しができないようにすることが可能となります。
(3)ATMで勝手に引き出した場合は払戻制度を利用したことになる?
相続人が亡くなった人の銀行口座が凍結される前にATMから「勝手にお金を引き出す」ということはよくある話ですが、この場合には払戻制度を利用したことになるのでしょうか?
結論から言うとこれは「ならない」です。
払戻制度を利用するための手続を経ていないものについては、払戻制度を利用したということにはなりません。
ですので、ATMから勝手にお金を引き出して葬儀費用に充てるということは今後もできないわけではありません。
ただ、本当に葬儀費用に使ったかどうか、葬儀費用の額としては高すぎないか等といったトラブルになる可能性がありますので、そのような手段を使う場合にはしっかりと証拠を残しておく必要があります。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
終わりに
改正によって当面の生活費や葬儀費用のための預金の引き出しができるようになったということは意外とまだ知られていないように思いますので、今回記事にしてみました。
お役に立てたら嬉しいです。
弁護士保険で今後のトラブルに備えていただくこともオススメします‼
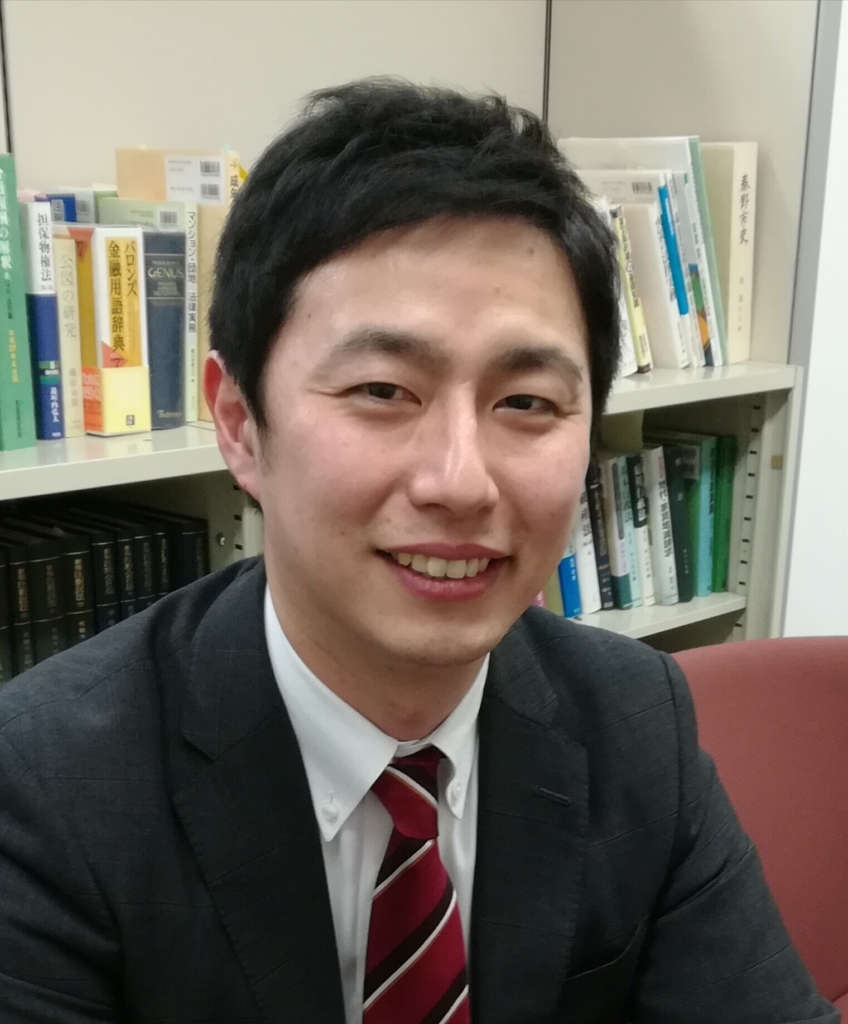
山田康平 弁護士
神奈川県弁護士会所属
谷法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町3-35 有楽ビル8階
TEL 045-641-0901
依頼者の考えと状況に応じて,依頼者と共に最良の方策を練って対応することを目標に, 不動産・相続問題を中心として個人・企業を問わず幅広く事件を扱う。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------