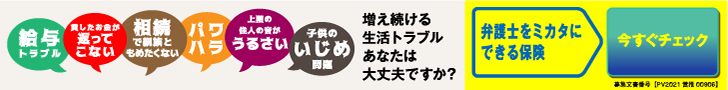義父母の介護を長年続けてきたのに、相続では何ももらえない…
相続人でない配偶者が介護に尽くしても、遺産分割では評価されない…
義理の家族の世話をしてきた苦労が報われない…
このような、相続人以外の親族による献身的な介護や看護が相続で考慮されないことに不公平感を抱く方は多くいらっしゃいます。
こうした状況に直面し、「長年の介護は何の意味もないのか?」「何らかの請求はできないのか?」「弁護士に相談すべきか?家庭裁判所に申し立てるべきか?」と悩まれる方もいるでしょう。
令和元年7月の民法改正により「特別寄与料」という新しい制度が創設され、相続人以外の親族であっても、被相続人への療養看護等に特別の貢献をした場合には、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになりました。ただし、一定の要件や期間制限があり、適切な手続きを踏む必要があります。
本記事では、特別寄与料制度の具体的な要件、請求手続きの流れ、金額の決定方法、権利行使の期間制限について、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス
1 遺産分割における寄与分制度

まず、相続人の中に亡くなった人の財産の維持や増加に特別な貢献をした人がいた場合、特別な貢献を実際の相続の場面において考慮して、その相続人に対して特別に与えられる相続財産への持分のことを「寄与分」といいます。
この寄与分の制度は、亡くなった人に特別な貢献をした相続人がいる場合に、その貢献の事実を相続において具体的な金額として評価することにより、他の相続人との間での実質的な公平を図ろうという趣旨によるものです。
もっとも、寄与分が認められるのはあくまでも亡くなった人の「相続人」のみです。
そのため、今回のケースのように相続人の妻が義理の母親の介護を長年にわたってしてきたような場合であっても、妻が義理の親の遺産分割において何かしらの財産の分配を請求したりすることはできませんでした。
もっとも、夫が健在であれば、妻の貢献を夫の貢献とみなすことによって相続において夫の寄与分として考慮することができる余地はこれまでもありました。
しかし、仮に夫が母親より先に亡くなってしまっていた場合には、そのような妻の介護に対する事実上の配慮をすることさえもできません。
これでは、妻の献身的な介護による母への貢献は一切報われることがなくなってしまいない、あまりにも不公平な気がしませんか。
なんとかしてその貢献に応じた権利を相続人の配偶者である妻にも認めてあげたいですよね。
これが今回の改正のお話です。
2 民法改正による特別寄与料制度の新設

2019年7月1日に施行された民法改正により、相続人以外の親族の貢献を相続において反映させるための次の条文が新たに作られました。
まずは基本となる条文を見てみましょう。
| 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は排除によってその相続権を失った者を除く。 以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。 |
法律の条文そのままですと難しくて分かりにくいですよね。
この条文は「相続人以外の親族」が、被相続人の生前に財産の維持や増加に特別な貢献をした場合、その貢献に応じた金額(これを「特別寄与料」といいます。)の支払いを「相続人」に対して直接請求することができるというものなのです。
この条文が新しくできたことにより、今回のケースの相談者も、相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました。
3 どうして改正されたのか?
では、なぜこのような規定が新たに作られたのでしょうか。
これは何度も書いておりますが、「不公平さの解消」です。
介護などで大きく貢献した親族が相続人ではないという理由だけで寄与分が認められず、相続財産から全く分配を受けられないのはあまりに不公平なので、その不公平さをできるかぎり解消しよう、というのが今回の改正の目的です。
また、今回の規定ができた背景には、療養看護を行うなどの貢献をした親族に対しては、その貢献に応じた一定の財産を分け与えるというのが被相続人の意思に基づくものだろうという基本的な考えもあるのです。
4 制度の内容

(1)どんな要件なの?
では、特別寄与料の請求権が認められるのは具体的にどのような場合なのでしょうかさっそく要件を見ていきましょう。
①「被相続人の親族」であること
②「療養看護その他の労務の提供をした」こと
③「被相続人の財産の維持または増加について」寄与したこと
④「無償で」あること
⑤「特別の」寄与であること
①「被相続人の親族」であること
「被相続人の親族」とは、被相続人の六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のことをいいます。
親族のうち、相続人は特別寄与料を請求できる主体とはなりません。
その理由は、相続人の場合にはもともと寄与分の制度があるため、被相続人への介護などの貢献については遺産分割の中で寄与分として考慮すれば十分だろうと考えられているからです。
また、相続放棄をした場合や相続人の欠格事由に該当することによって相続人にならなかったような場合には特別寄与料を請求することはできませんので、自分の意思で相続放棄をしようと考えている場合などには注意しましょう。
②「療養看護その他の労務の提供をした」こと
療養看護の他にも被相続人の事業を手伝った場合なども特別寄与料の対象となります。
ただし、被相続人に財産を渡したというだけの場合は「労務の提供」とは言えませんので、特別寄与料の対象とはなりません。
③「被相続人の財産の維持または増加について」寄与したこと
特別寄与者の行為がなかったとしたら支出が必要となって被相続人の財産が減っていた、被相続人の債務が増えていた、あるいはその行為がなければ被相続人の財産が増えなかったなどの金銭的な評価ができることが必要です。
そのため、精神的な援助や協力のような金額での評価ができない、又は難しい場合は特別寄与料として認められないことになります。
④「無償で」あること
特別寄与者が被相続人から労務提供の対価をもらっていたときには、特別寄与料の請求はできません。
では、対価をもらっていたかどうかはどのように判断するのでしょうか?
これは、当事者(被相続人と労務を提供した親族)の認識や労務の提供・財産の給付のタイミングや量などをふまえて、それぞれの事案に応じて具体的に判断されることになります。
例えば、労務を提供した親族が、被相続人が要介護状態になる前から被相続人と同居し、その親族の生活費も被相続人が負担していて、さらに療養看護開始後も引き続き被相続人が生活費を負担していたというケースを考えてみましょう。
このケースであれば、形式的には生活費の負担という内容でその親族が療養看護の対価をもらっていたといえそうにも思えますが、実際には要介護状態になる以前からの状態がそのまま続いていただけと考えることもできますよね。
そのため、そのようなケースでは、療養看護に対する対価をもらっていたといえるような他の事情があるかどうかなどといった様々な点が考慮されて、最終的に寄与行為が「無償」であったかどうかの判断がなされることになります。
このあたりの判断はなかなか難しいと思いますので、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
⑤「特別の」寄与であること
「特別」といえるには、親族としてのその人の貢献に報いることが相当であると認められる程度の顕著な貢献であったことが必要となります。
そのため、親族として通常期待されるような程度の貢献にとどまる場合には特別寄与料は認めてもらえません。
(2)請求はどのようにするの?
請求は誰に対してするのか?
特別寄与料は一体誰に請求すればいいのでしょうか?
特別寄与料は相続人に対して請求することになります。
請求はどのような方法で行うのか?
(ア)原則=協議(話し合い)
特別寄与料の請求を認めるのかどうか、また認めるとしてその金額をいくらにするかについては、まずは特別寄与者と相続人との間の協議(話合い)で決めることになります。
ただし、特別寄与料の額については、法律上、相続財産の価額から遺贈の価額を差し引いた残額以内にしなければなりませんので、その範囲内で相続人全員がお互いに納得する金額で話をまとめる必要があります。
(イ)例外(協議がまとまらないとき)
では、話合いではどうしても特別寄与料について折り合いがつかないような場合はどうしたらよいのでしょうか?
その場合には、家庭裁判所に「協議に代わる処分」を請求することができます。
寄与分の場合には遺産分割調停が裁判所に係属しているときにしか請求できないのですが、特別寄与料の場合にはそのような制限はありません。
(3)権利はいつまで行使できるの?
では、特別寄与料はいつまで請求できるのでしょうか?
特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内
又は
相続開始の時から1年以内
上記までに家庭裁判所に請求しなければなりません。
したがって、遅くとも相続開始時から1年を過ぎてしまった場合は特別寄与料の請求は原則としてできなくなります。
気付いたら権利を主張できなくなっていたといったことにならないよう、相続開始を知ったときには特別寄与料を請求することを忘れないで下さい。
(4)特別寄与料の額はどうやって決められるの?
特別寄与料は具体的にどのようにして金額が決められることになるのか、気になりますよね。
考慮要素
家庭裁判所では、寄与の時期・方法及び程度・相続財産の額・相続債務の額・被相続人による遺言の内容・各相続人の遺留分・特別寄与者が生前に受けた利益などの事情を総合的に考慮して特別寄与料の額を決めることになります。
算定方法(今回のケースの場合)
今回の相談者であるⅩさんのケースのような療養看護を行った場合、「介護報酬」が一つの目安です。
すなわち、「もしヘルパーさんなどの全くの第三者に療養看護を頼んでいたらいくらかかっていたか」をもとにして、相談者の介護により被相続人が支払わなくて済んだ金額が基準となります。
もっとも、看護や介護の専門家に頼んだ場合よりは費用を控えめに計算されるため、専門家に頼んだ場合の費用に対して0.5~0.8を乗じた金額となります(これを「裁量割合」といいます)。
以上の内容を計算式で表現すると次のようになります。
| 特別寄与料=介護報酬相当額×療養看護の日数×裁量割合(0.5~0.8) |
ただし、家庭裁判所で介護などの貢献による特別寄与料を認めてもらうためには、どのような内容の介護を、どのような頻度で、1日あたりどのくらいの時間をかけて、どの位の期間にわたって行ってきたのかといったことを何らかの方法で裁判所に認めてもらう必要があります。
そのためには、日常的に介護日記や介護日誌をつけたり、介護などのために支出した費用があればその領収書などを大切に保管したりするなどして、介護の痕跡を日頃から残しておくことが大切になります。
5 今回の改正民法はいつの相続から適用?(改正民法の施行日はいつからか?)

今回の改正民法の施行日は「2019年(令和元年)7月1日」です。
施行日後に発生した相続であれば、療養看護等の特別な寄与が施行日前であっても特別寄与料の請求をすることは可能です!
ですので、これから発生するすべての相続のケースで特別寄与料の請求ができる可能性がある、ということになります。
これは嬉しい話ですね。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2
- 離婚・男女トラブル
- 労働トラブル
- 近隣トラブル
- 誹謗中傷トラブル
- 相続トラブル
私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3
トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4
気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)
\ 累計資料請求100,000件突破 /
 丸山弁護士
丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。
*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
6 おわりに
いかがでしたか?
義理の両親の介護に尽くした配偶者の方は、ご自身がどのような場合にどのような方法で特別寄与料の請求ができるかがなんとなくわかっていただけたのではないでしょうか?
ご自身が請求できるケースに当たるのか、具体的にどのくらいの金額の請求ができるのかについては判断が難しい場合もあるので、そのようなときには弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
この記事が多くのみなさまにお役に立つことを祈っています。
あらかじめ弁護士保険などで、今後のリスクに備えておくことをおすすめします。
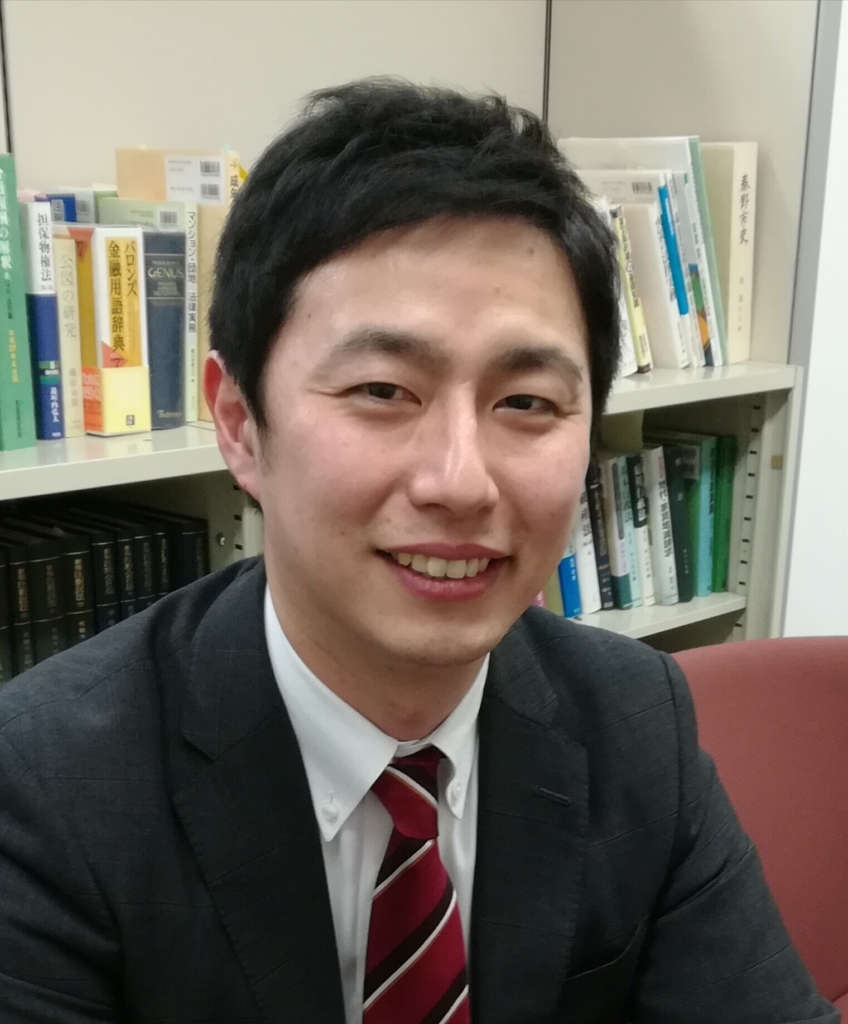
山田康平 弁護士
神奈川県弁護士会所属
谷法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町3-35 有楽ビル8階
TEL 045-641-0901
依頼者の考えと状況に応じて,依頼者と共に最良の方策を練って対応することを目標に, 不動産・相続問題を中心として個人・企業を問わず幅広く事件を扱う。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、
法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、
弁護士監修のもと発信しています♪
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------